

![]() 1月号 2018年
1月号 2018年
| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀漢賞銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男俳句 銀漢の絵はがき 掲示板 銀漢日録 今月の写真 |
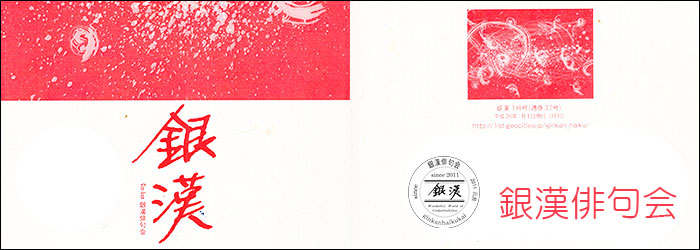
伊藤伊那男作品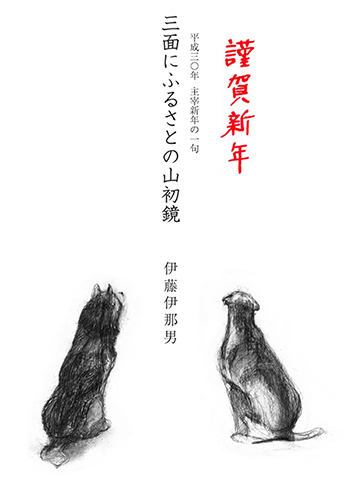 新年号・主宰の一句 三面にふるさとの山初鏡 伊藤伊那男
主宰の八句 秋思 伊藤伊那男
しみじみと見る体育の日の手足 子規庵に拾ふ秋思の種ひとつ 鉛筆を削る秋思の形まで 舌切られたるもをるらむ稲雀 鬼胡桃てふ縄文の面構へ 栗鼠は頰に子はポケットに木の実満つ 猪撃ちの猪首と会へる峠口 撃たれたる猪まだ逆毛立てしまま 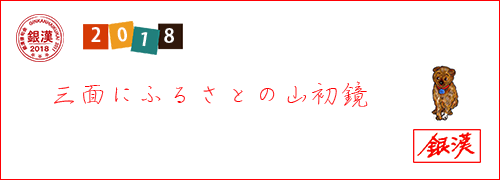 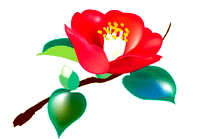  今月の目次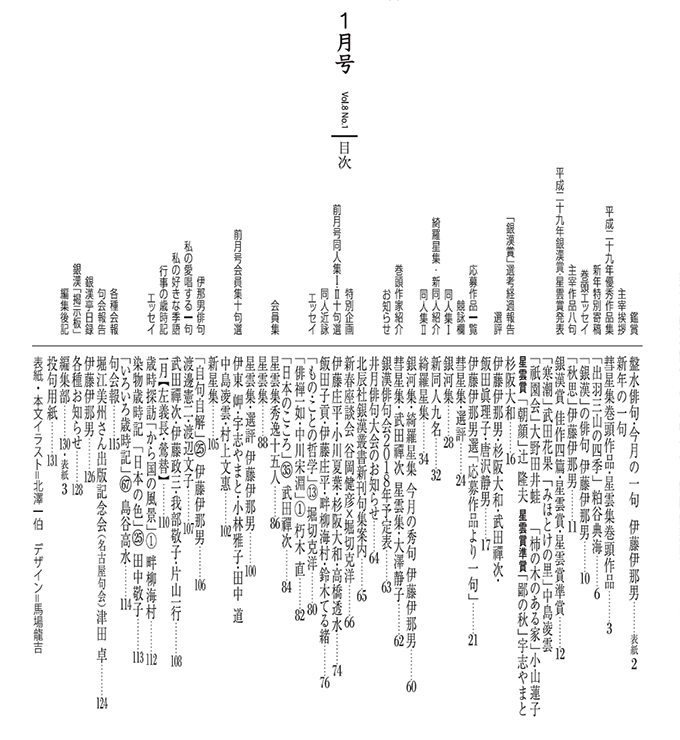  銀漢俳句会/1月号     銀漢の俳句伊藤伊那男
|
◎佐藤一斎と井上井月 同人堀江美州さんが『幕末の大儒学者「佐藤一斎」の教えを現代に』を出版された。佐藤一斎の『言志四録』を解読し、自身の人生観や所見を加えたものである。美州さんとの出会いは、岐阜県庁の職員で東京事務所長として単身赴任をされていた折、何か趣味を持とうと、インターネットで俳句について検索をしたところ、東京新聞の朽木直さんが銀漢亭の句会を紹介した記事にヒットして私を訪ねて来られたのであった。この度の出版に当たり、改めて聞いたところでは、当時から上司に薦められた『言志四録』を懐に愛読されていたとのことである。その後岐阜県に戻られたあと、一斎の本籍、岩村藩のあった恵那市に赴任された時期もあり、尚更親しみを深め、本書上梓の意志を固められたようだ。 幕末の小説などを見ると佐久間象山は実際に一斎に学び、西郷隆盛、吉田松陰などが深く私淑していたようだが、一斎の教えが如何なるものであったかは、私には知る由もなかった。ただ一つだけ私の記憶に残っていることがある。それは井上井月が絡む話である。下島空谷が纏めた『井月の句集』の中に、井月と交流のあった人達から聞き書きをした逸話集がある。その中の一つ──井月は襖に松尾芭蕉の「幻住庵記」をよく筆写したが、その中の「奥州」の読み方について句友の某が「オクシュウ」と言ったのに対し、井月が「アウシュウ」と直したが、某は納得せず言い募ったという。最後に井月が「これでもわしは一斎の弟子だからな」と言い──決着したようだ。 以上の逸話が残っているということは、一斎の名声を信濃の山奥の一般人も知っていたという証左である。ところで一斎は昌平坂学問所の総長を長く務めていたのだが、井月が江戸にいたと思われる頃の これまで一斎という碩学について、名前を知るのみであったが、この度の出版で、一斎の一端を知ることができたのは大きな収穫であった。美州さんが社会人としての仕事の傍ら、ずっと一つのテーマを抱え続けて一書を成したことは見事である。仕事とは別に一念を暖めてきた意志の強さはなまなかなことではない。その一念に拍手を送りたい。 一斎の言の葉永久に柿日和 伊那男
|


| 盤水先生は陶磁器にも一家言をお持ちであった。明治時代より前の伊万里焼を古伊万里と呼ぶようだ。金襴手の皿などが知られているが、その中の赤絵に着目されたのである。「喜色」の措辞が正月の雰囲気をいやが上にも盛り立てているのである。一族の祝いの行事などの時に出される大皿なのであろう。盛り付けた御節料理が元日、二日と減っていき、三日目になると、特に赤絵も目立ってくるのであろう。 (昭和51年作『板谷峠』所収) |





| 「思惟」とは心に深く考え思うこと。本来は「しゆい」と読んだようだ。我々の頭にすぐ浮かぶのは飛鳥・中宮寺や京都・広隆寺の半跏思惟像であろう。右手を頬のあたりに挙げて思考にふける姿の像である。その姿に触発されて、ぼんやりしていた作者の秋思が次第に「形」を成してきたのだという。目に見えない「秋思」が形になっていく、という所が眼目である。 |
| 根岸子規庵は確か二間が庭に面していた。作者が訪ねたのは萩の花の盛りの頃であったのであろう。丁度子規の終命もその頃だった筈である。子規は享年三十六歳。しかも不自由な身であれだけの業績を残したのだから、そのエネルギーには驚嘆するほかはない。「明るさに」は子規への手向けの言葉であろう。子規には〈萩咲いて家賃五円の家に住む〉があるが、この句はそれを踏まえているのかもしれない。 |
| 菊人形の弁慶を詠んで秀逸である。高館の最後の戦いで弁慶は自らが義経の盾となり、仁王立ちをして百本の矢を身に受けたという。その菊人形の仕上げに矢を刺したというのだが「貰ふ」の措辞が決め手である。弁慶は「刺された」のだが、菊人形は「刺して貰ふ」——この差がこの句の命である。 |
| 現代の「鳥渡る」の風景である。摩天楼の間を縫って北の国から飛来する鳥達。ビルの谷間の公園に羽を休めるのであろうか。高層ビルの無数の窓が光を撥ね返す。 |
| 霞ヶ浦あたりの風景であろう。歌垣は |
| 出羽三山の峰入りで、三光院の粕谷典海氏が山伏姿で法螺を吹いてくれたことを思い出す。その音色が周囲の山に響く。山は秋色を深めていくのである。 |
| 少し悲しいが人の世の節理でもある。季語の斡旋の良さ。 |
| 実感である。私もこの季節、名簿の何人かに線を引く。 |
| 擬人化であろうか。服のお下がりを言うのか、面白い。 |
| ステンドグラスの教会の色彩に色鳥も加わったか。 |
| 私の子供時代がそうであった。一家揃って一日がかり。 |
| 最も若者が集まる町であるからこそ。青春への哀惜。 |
| 運動会の華、玉入れの嘱目。「飲み込む」の表現力。 |
| 素人芸のおかしさ。女役も男の扮装であるかもしれない。 |
| 「物みな長き」と一歩踏み込んだ表現がいい。 |
| もはや本来の風を送る機能ではない秋扇である。 |
| 昔の風呂は表面だけが熱かった。「沸きむら」が可笑しい。 |
| どぶろく祭の嘱目か。湿った莚の様子を的確に捉えた。 |
| 東海道の一宿だけを歩く小さな旅。数字を用いた妙。 |
| 清水寺の茶店か。「身に入むや」に幕末の悲しい歴史が。 |



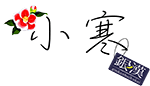

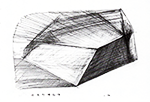










伊藤伊那男
| 確かに、まだ寒風が吹く日々の中で、庭の土を盛り上げて吹く水仙には力を与えられるものである。それも一つ二つではなく群落として出現するので尚更である。作者はこれを見て「励まねば!」と自らに呼びかける。百歳を越えられた作者が、このように力強い句を発信するのである。我々もこの句から「励まねば!」と力を与えられるのである。 |
| もともと柿は全てが渋柿であったが、日本において突然変異で甘柿が誕生し、以降改良が重ねられてきたとのことである。そういう歴史を踏まえると、「柿のしぶしぶ」がユーモアを持って伝わるのである。柿としては渋いままでいたかったのに無理矢理甘くさせられていくというのである。「しぶ」の音が四つ入ったのも巧みな技。 |
| 句会でこの句を見たときは、あまりにも舞台設定が決っていることや、その構成の見事さに、もしかしたら類句があるのでは……と選句をためらってしまったのだが、こうして改めて見ると、うまい!と思う。近江富士とは滋賀県野洲郡にある432メートルの |
| 夏休みが終って教室に入り、改めて見廻すと、教室というものは四角なのだな――と実感するという。この感覚が句の凄さである。感性の高さ、ということになろうか。誰がこんなことを今さら感じるのであろうか、という所を詠み取るのが「感性」である。 |
| 記憶は朧であるが、宮澤賢治記念館と同じ敷地に「山猫軒」というレストランがあった。もちろんその名前は賢治の著作の題名『注文の多い料理店』から取られている。物語は、そのレストランに入るといくつものドアがあり、潜るたびに、だんだん自分が食材にされていく恐怖が募っていく、というものである。「登る階段」――と気分を高めていくのが句の面白さだ。「木の実降る」までで留まっており、そのあとの恐怖はまだ知らないのである。同時出句に〈曲家にテープの民話秋うらら〉〈さやけしや未だ魚信なき河童淵〉〈座敷わらし待ちて遠野の夜長かな〉と、いづれも味わいの深い力作が並び、楽しませて貰った。 |
| なるほど!傾斜を利用した千枚田であるから、水を落すとすれば高い所から低い方へ流れ落ちていき、最後は一ヶ所の田に集約されて落ちていく――ということになる。千枚田というものに、落すほどの水が有るのか、実態は知らないが、理論的に納得できる、うまい句なのである。「千」が「一」になるという句の構成は見事、というほかはない。 |
| 季語の斡旋のうまさである。確かに米だけでなく、豆、芋、栗……様々な穀物、果実が稔る季節だけに、圧力鍋はフル稼働である。祭や寄合いなどがあれば尚更である。圧力鍋が噴く蒸気の音が聞こえてきそうな句だ。 |
| 盛岡駅のすぐ近くを北上川が流れている。そこまで鮭が遡上したのかどうか解らぬが、岩手県人の心のふるさとであるこの川を配したところが句の眼目だ。「鮭の川」の措辞で、帰るべき川、帰るべき土地であることを暗示しているようである。 |
| 私の子供の頃は、近くの川に障子ごと浸けて洗ったものだ。家の仕様も変ったし、そのようなことはもはや出来ることもなく、絶滅へ向う季語の一つであるかもしれない。それにしても「山河を小分けして」とは、何とも見事な表現ではないか! 洗い終わって、紙の無くなった骨格からは周囲の山河が丸見えだ。その山河は桟によって仕切られている。「小分けして」――何とも秀逸な言葉の斡旋である。 |
その他印象深かった句を次に











| 秋の草々の咲く花野は浄土のようでもある。冬が近いことも感傷を呼ぶようだ。やや冷たくなり始めた山風に吹かれると、今日の一日がもう過去のものになっていくのだな‥‥と感慨を深めるのである。上五の「ひたすらに」には単に花野の散策を言うばかりではなく、作者のこれまでの懸命な生き方の回顧も籠められているのであろう。同時出句の〈鶏頭を抜きて庭より秋を消す〉も「秋を消す」の措辞が何とも異色な表現であった。両句共独自の抒情感。 |
| 句中に「惜」の字を二回使っているのだが、「惜しみなく」の否定形と「惜しむ」の肯定形を用いて、また意味も違えて見事な構成を決めている。剣山に溢れるばかりの秋草を活けて、秋を惜しむ。豊饒であることによって哀惜が一層深まるのである。 |
| 現代の世の中で、猪除けなどは無くなっていく季語かと思っていたのだが、逆に猪や鹿が増え続けて、切実な物になっているようだ。その猪除けが動いたので、出たか!と見ると、父の姿であったという。俳諧味のある句だが、また実感も深いところがいい。 |
| 「俳諧は三歳の童に聞け」――という芭蕉の言があるが、この句などはまさに、そのことを具現した句といえよう。「今日の月」を画用紙に描くのに、黄のクレヨンは一本全部を使い果たしてしまうだろう、という子供心に戻った感慨である。 |
| 若い頃は毎日何か刺激のある出来事を待ち、また作っていったものである。私自身も古希を間近にすると、変化が少なくても無事息災であればいいな、と思う。千載一遇の好運は無くても穏やかな日々であればいいと思う。この句のように「小鳥来る」に十分喜びを感じるのである。 |
| 一読、心に残る美しい風景である。鈍行で行くという時間の使い方が、かえって贅沢である。車窓から見る月、海に映る月が何とも好ましい。満月ではなく、一日遅れの僅かに欠けた月、少し出の遅い月であることで興を深めている。 |
| 一夏使った寝茣蓙には汗の滲みや、体圧による凹みなどが出ているのであろう。「体型のままに」の表現がユニークで、寝茣蓙を珍しい視点で捉えたことを称えたい。 |
| これも現代風景であろう。電話、パソコンなどの普及により、いつでも仕事の連絡が入る。暇を見付けたほんの僅かな夜食の時間にも仕事の問合せが入る。そのような繁忙の様子が過不足なく描かれている。 |
| 深夜ラジオに耳をかたむけると、鮭の遡上が始まったという地方の声が流れる。行ったことのある河であれば、ラジオの向うにありありとその風景も浮かび上るのである。同時出句の〈秋思ふと置いてけ堀の話聞き〉なども、肩の力を抜いた淡々とした作風で、味わいを深めている。 |
| ああ、このようにして酔芙蓉は紅を深めるのであろうか。あの薄い花びらの内側から紅が湧いてくる――と微細な変化に目が行ったのである。 |
| 前述「酔芙蓉」の句と同様、この句にも驚いた。確かに梨の皮は外側から雫が垂れることは無い、剝いた内側から汁が湧くのであり、当然ではあるのだが、誰もそんなことを俳句にしたことは無く、一つの発見である。剝いたからこそ「実の裏側」ということになるのであろう。 |



| 伊那男俳句 自句自解(25) 雪嶺に声を飛ばして達磨売
郷里伊那谷の高遠町の入口、鉾持神社の旧正月の行事に達磨市がある。高遠藩は、武田信玄と諏訪御寮人との間の息子、仁科五郎盛信が守り、信玄の死後、織田信長軍の猛攻に立ち向い、全滅した。後、三代将軍徳川家光の弟、保科正之が入城。正之は家光の補佐役としてその功を認められ、後に松平氏に改姓し会津に転封する。替って内藤氏が幕末まで治めた。絵島生島事件の絵島が遠流され、ここに生涯を閉じたことや、藩校進徳館から、明治期に活躍した伊澤修二、伊澤多喜男の兄弟を輩出したことや、新宿御苑を今に残したことや……少しだけ歴史に痕跡を留めている。さてこの句、町の入口から細い石段を延々と登った山頂が鉾持神社で、当日は周辺に達磨市が立つ。登るにつれて赤石山脈(南アルプス),木曾山脈(中央アルプス)が眼前に開けてくる。日頃淋しい町だが、その日は活気に溢れ、賑わいの声は二つの山脈に響くようである。「声を飛ばして」が眼目である。 炭住に煤けて生まれ雀の子
福島県いわき市は盤水先生の故郷。閼伽井岳や白水阿弥陀堂に先生の句碑を建立したり、同人総会を開催したりと、私も度々訪ねている。句はある時の集まりで、盤水先生の姪御さんの嫁ぎ先である温泉旅館に宿泊した折の嘱目である。旅館から裏を眺めると、平屋建ての棟割長屋が何棟か見えた。地元の俳人が、あれが「炭住」ですよ、と教えてくれた。常磐炭鉱の最盛期には、このような炭住が密集していたのであろう。全国から集まった労働者や家族で溢れていたであろう。先生の父上は鉱山技師であったから、もう少しランクの高い住宅で暮らしていたのであろうか……などと石炭産業最盛期の様子を空想している中で胸裡に浮かんだ句であった。「煤けて生まれ」という措辞は、もしかしたら失礼に当るのではないか、と恐る恐る出句してみたが、好意的に選句して下さった。映画「フラガール」が封切されたのはそれよりも後のことであった。 |

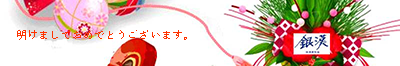




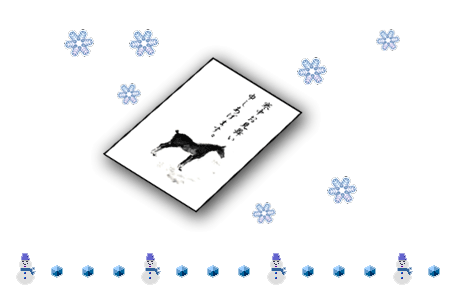

 h
h
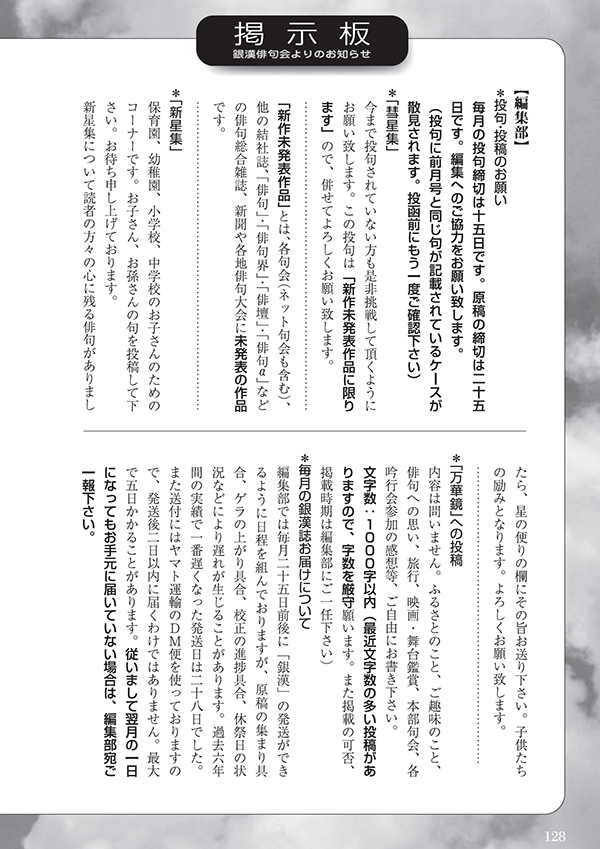
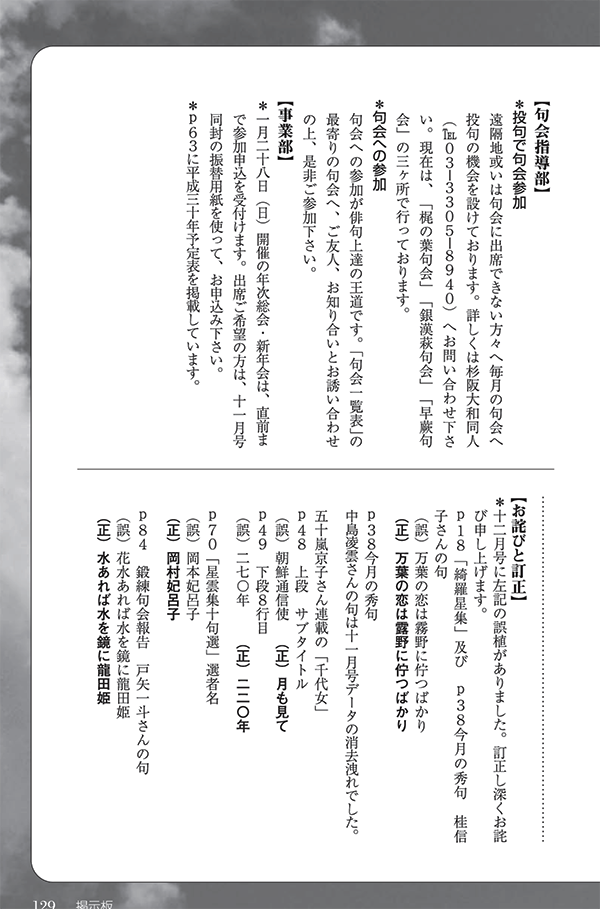


10月 10月9日(月) 10月9日(月)午前中、「春耕賞」選句。応募42編。志村昌さんから「運慶展」の券いただいたので上野東博へ。予想ほどの混み方ではなく、3時間ほど楽しむ。折角来たので茶器の部屋も。あとアメヤ横丁の「大統領」で煮込と串焼でビール。 10月10日(火) 超結社句会「火の会」休みの方多く、太田うさぎ、天野小石、齋藤朝比古、山崎志夏生、阪西敦子、峯尾文世の面々。あとは閑散。  10月11日(水) 10月11日(水)高幡不動 尊の川澄祐勝大僧正遷化の報。「銀漢」にも基金その他、御支援を戴いた恩人。 10月12日(木) 「極句会」あと9人。新しい方も入会している。  10月13日(金) 10月13日(金)藤森荘吉さんの「閏句会」8人。遅くにうさぎさん来たので「大金星」へ。そこへ一斗さん。 10月14日(土) 9時半、発行所にて拡大編集会議と運営委員会。18人集合してくれる。午後、麹町会館にて「銀漢本部句会」62名。馬場龍吉さんも参加して下さる。あと中華料理店にて親睦会。  10月15(日) 10月15(日)「春耕賞」選句終える。店、「演劇人句会」の10人。他、閑散。7日ほど冷たい雨が降り続く。  10月18日(水) 10月18日(水)久々の快晴。11時、高幡不動尊へ。第三十三世貫主・川澄祐勝大僧正の告別式へ。導師は川崎大師の御貫主。享年87歳。店「三水会」5人。閉めて、5、6人で「ふくの鳥」。 10月19日(木) また雨。「銀漢句会」あと13人。寒い一日。  10月20日(金) 10月20日(金)発行所、「蔦句会」あと店は3人。入れ替わり「天城句会」(唐沢静男さん)一行9人が吟行あと句会。終わって店へ。小野無道、大西老林さんには初めてお目に懸かる。大西さんは私と生年月日が同じ。「松の芯」の創刊20周年パーティーあとの小暮陶九郎、しなだしん、佐怒賀直美、今井肖子、阪西敦子さんなど。  10月21日(土) 10月21日(土)雨。「銀漢鍛練句会」の日。一応、本郷に来たので東大赤門を潜る。13時、ホテル機山館。30人。持ち寄り10句で1回目句会。17時夕食。19時半から2回目句会10句。22時、終わって少し飲む。 10月22日(日) 9時より、3回目句会。10句。11時半、終わって近くの台湾料理店にて打上げ。台風が近づいている。  10月23日(月) 10月23日(月)久々、晴れていたものの店閑散。21時閉める。 10月24日(火) 堀切克洋君、今年度の「北斗賞」受賞と。快挙! ひまわり館に「萩句会」選句。店、法政大学高柳先生と飯田高校の方々5人。  10月25日(水) 10月25日(水)「雛句会」13人。発行所は谷岡健彦・堀切克洋さんの座談会。前回はいつだったか記憶がないが久々の休肝日とする。 10月26日(木) 店、ORIXの後輩3人。皆川丈人、文弘さんひょっこり。22時閉めて久々「天鴻餃子房」。  10月27日(金) 10月27日(金)「金星句会」あと6人。堀切克洋君の「北斗賞」、小田島渚さんの「角川俳句賞」候補にヴーヴクリコで乾杯! 「青垣」の石井さん、大王製紙の田中役員など。 10月28日(土) 12時、名古屋。栄の「囲み屋」。堀江美州さんの『幕末の大儒学者「佐藤一斎」の教えを現代に』の出版記念会。武田さんと。「名古屋句会」のメンバー集合。萩原空木さん元気。中村紘子さん久々。定例句会の披講も併せて。 〈一斎の言の葉永遠に柿日和 伊那男〉 あと喫茶店で歓談し別れる。  10月29日(日) 10月29日(日)台風到来の中、9時、新百合ケ丘駅。「早蕨句会」の吟行会に招かれて。何と20数名集合。バスにてあざみ野。電車にてセンター北。「大塚の歳勝土遺跡」~「茅ヶ崎城址」~「正覚寺」と雨中を歩く。秋元さんの案内。町田に戻って昼食あと句会。何と、駅近くで島谷操さんとばったり会う。3句出し。終わって沖縄料理店「ニライカナイ」にて親睦会。凛子さんお世話になりました。 10月30日(月) 12月号の選句、執筆。店「雲の峰」の高野清風同人会長、酒井多加子、京子、次郎、庄平さんなど。吟行あと。高井戸時代の整体師中村先生、7人。「天為」の笹下蟷螂子さん。島織布句集『犬の瞳に』、田中敬子句集『機の音』完成。発送業務。 10月31日(火) 有澤志峯さん久々。「春耕吟行会」あとの池内けい吾、柚口満、蟇目良雨、窪田明、奈良英子さん他、寄って下さる。須磨の石井さん、京都の笹下蟷螂子さん。21時半閉める。 11月  11月1日(水) 11月1日(水)「宙句会」あと11人。全体閑散。 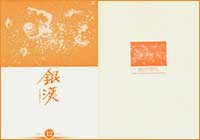 11月2日(木) 11月2日(木)彗星集評書いて12月号終了。やっとこさ。店、村上鞆彦(「南風」主宰)、今泉礼奈さん、婚姻届けの保証人に記名捺印。おめでとう。来合わせた皆川文弘さんがヴーヴクリコ開けて乾杯! 水内慶太(「月の匣」主宰)、亀戸弥助寿司の鯖鮨の太棹二本持参で。環順子さん。  11月3日(木) 11月3日(木)午前中エッセイ一本。15時、銀漢亭お手伝いの会第2回を森下の馬肉屋「みの家」。うさぎ、小石、いづみ、凱さんに、伊那北同期の井蛙、光汪君。堀切君も誘う。四句出し句会。馬刺、鍋とよく飲み、よく食べる。すぐ近くのパブにて2句出し句会、1句出し句会。お開きで駅に向かうと休業日と思っていた「山利喜」が開いていて、席が空いているというので上がり込む。ひれ酒、名物の煮込みとパンなど。 10時、発行所にて運営委員会。麹町会館にて「銀漢本部句会」54人。早めに切り上げて、杉阪、禪次、眞理子さんで銀漢賞の第1回選考。あと親睦会に合流。  11月5日(日) 11月5日(日)昼過、中野サンプラザにて「春耕同人句会」。50数名。終わって親睦会は失礼し、帰宅。桃子さんの誕生日の前夜祭。清人さん経由で気仙沼大島の剝身の牡蠣3キロ。帆立10枚。 11月6日(月) 12月号の校正。店、「かさゝぎ勉強会」あとの8人。梅田津(「銀化」)さんグループ定例会4人。王子製紙の田中役員6人など。羽黒三光院より庄内柿到来。 11月7日(火) 広渡敬雄さん、九州大学時代の友人と、5人。昨年、「俳壇賞」受賞の蜂谷さん個展のあとの小島健、鴇田智哉、「玉藻」の方々。  11月8(水) 11月8(水)発行所の「梶の葉句会」選句。16時半、毎日新聞の「俳句あるふぁ」の編集部中島さん、来年の料理と俳句についての連載の打ち合わせ。国会議員のT先生来店。総選挙勝ち抜いて議員生活は27年目へ。乾杯!  11月9日(木) 11月9日(木)14時、発行所にて「銀漢賞」「星雲賞」についての最終選考。禪次、静男、眞理子、大和と全員揃う。あと静男さん店へ。発行所「極句会」あと10人店。  11月10(金) 11月10(金)19時過、家族来店。孫の一人は初めて。20時半「大倉句会」あとの17人。清人さんの鮪刺身、焼きそばなど。 11月11日(土) 12時、日暮里本行寺。「一茶山頭火俳句大会」の選者として。銀漢から10数名参加。当日句選句の間、有馬朗人先生の講演あり。1時間立ったままの講演には頭が下がる。終了後は、「又一順」にいて慰労会をして下さる。銀漢の仲間は違う所で飲んでいて、追って水内慶太氏とそこへ合流する。  11月12日(日) 11月12日(日)終日家。「俳句」1月号の「四週間で切れを使いこなせ」の特集の「上五で切る」について八枚書く。へとへと。夕食、家族で鶏鍋など。 11月13日(月) 「銀漢賞」「星雲賞」の応募作品各一句選後、評など。店、予約等なく閑散。色々と仕込み。久々に来店の客、本屋で私のエッセイ集見つけ5冊買って知人に配ったと。有り難い。  11月15日(水) 11月15日(水)店「京鹿子」の方々4人。「俳句」元編集長の鈴木忍さん夫妻、8か月の栞ちゃんと。岸本葉子さん句会巡りのエッセイ集出版。「火の会」の実況も入っており、届けて下さる。19時、石寒太先生の「炎環」宮本佳世乃さんの現代俳句協会新人賞受賞祝賀会。寒太先生はじめ、「炎環」の方、佳世乃さんの俳句仲間の鴇田智哉、田島健一、四谷龍さんなど46人で祝う。 |

