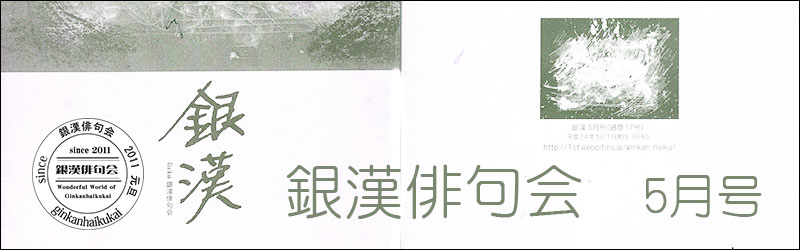伊藤伊那男作品
男雛
伊藤伊那男
二月尽く日記の余白多きまま
一連の目刺余せり妻亡くて
長崎に降り立つすでに絵踏めき
おらんだ坂猫のよこぎるおぼろかな
かまくらといふ雪洞を覗きけり
飯蛸を加へてみたき玩具箱
生家売る茎立つものもそのままに
み吉野に遠流の顔の男雛かな



今月の目次
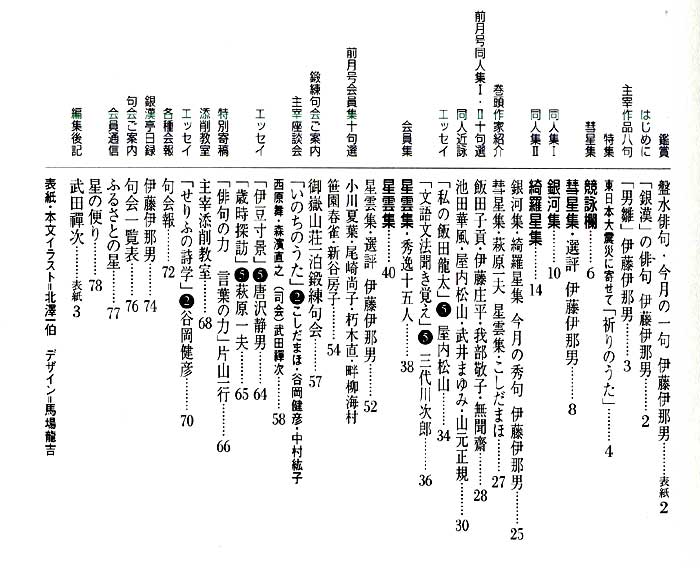

銀漢俳句会・5月号


銀漢の俳句
俳句を心の糧に
伊藤伊那男
東日本大震災が起った時、銀漢亭で仕込みの最中であった。暫く柱に寄って耐え、外に出ると電線は波を打ち、車は弾んで見えた。当日は避難してきた仲間と電車が回復するまで待機した。帰宅後、津波の映像を見て戦慄を覚えた。特に気仙沼は数年前の「みちのく海の全国俳句大会」の講師で訪ねており、昨年も仲間と大挙して参加した。その気仙沼が火の海になっている。その湾内にある大島は、同人の小野寺清人、俳友の菊田一平さんの故郷であり、二回とも泊まってお世話になっている。幸い途切れていた情報も少しずつ入り、ほとんどの知人は無事であった。
私は数日後の夜中に京都へ向った。福島原発の事故に娘達の不安が募ったからである。長女は子供四人、四人目は生後五カ月。次女は三歳児がいて本人は臨月の妊婦である。結局、亡き妻の友人の許に転がり込み五日間を過ごした。聞きつけた「雲の峰」朝妻主宰から、手持無沙汰だろうと声を掛けて貰い、被災者の方々には申し訳ないけれど奈良に遊んだりもした。朝妻氏は阪神大震災の罹災時に〈闇に呼ぶ妻の名子の名冬の地震〉〈豆撒くや傾く柱裂けし壁〉などの句を残している。そうした人の、思い遣りのある誘いであった。そして関西は嘘のように穏やかであった。
一方、3月中の句会のほとんどは中止せざるを得なかった。交通や電力の問題、また公共施設である会場の使用上の問題もあり、四月の運営も不確かである。しかしメールや電話には「次の句会の題を出してほしい。それを励みにしたい。安らぎになる。」とか「こんな時こそ俳句をやっていてよかった!」というような言葉が寄せられている。創刊間もなく銀漢俳句会も打撃を受けたのだが、被災地の方々に較べたら、掠り傷とも言えない。俳句は「夏炉冬扇」の文芸であり、災難時の糧にはならない。しかしその後の復興過程においては必ず「心の糧」になる筈である。天然自然の脅威と包擁力、人間の驕りの果かなさを今回身にしみて味わい、人は奇跡のように生かされているのだということを実感するのである。その気持の中から自ずと「いのちのうた」が湧きあがってくるのではないかと思う。被災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、1日1日を大切にしていきたい
|



盤水俳句・今月の一句
花曇り工員が消す残置燈 皆川盤水
私が生れた年、戦後復興期の句である。「残置燈」という言葉を今使う人はいないだろう。節電が切実な時代であることが解る。まだまだ花見を楽しむ時代ではない。そんなことが句から解ってくるのである。俳句は浮世離れした文芸のように見えながら、実は常に世相の影響を受けるものなのである。このあと先生は社会性俳句を標榜する「風」に参加していくのだが、その片鱗が既にあるように思う。(『積荷』昭24)
|
| 伊藤伊那男 |



祈りのうた・
東日本大震災に寄せて・・・
特集 東北・関東大震災に寄せて
「祈りのうた」 銀漢俳句会同人一同
平成23年3月11日午後2時42分、三陸沖を震源地とするマグニチュード9.0の未曾有の大地震が襲いました。この地震・津波による被害は言語に絶するものがあり、多くの犠牲者と被災者が生じています。
銀漢俳句会会員の方々は幸い全員がご無事ではありましたが、ご親族、ご親戚、ご友人の安否が不明の方々もおられます。そのような中ではありますが、銀漢俳句会と致しましては、犠牲者の方々への心からの哀悼の意を表し、被災された方々へのお見舞い、そしてわが身を顧みずに復興支援に働いておられる多くの方々への応援の気持ちを同人の皆さま方の一句一句に託して、ここに捧げたいと存じます。合掌
|
木蓮は祈りのかたち海凪げよ 伊藤伊那男
料峭や他人事ならぬ巨大地震 青木志津香
春の朝ヘリコプターの音逞し 飯田子貢
地震の後たしかに陸奥の木の芽張る 飯田眞理子
子供らの焚く火明るき春の闇 池田華風
涙なほ温しと一行着信す 伊藤庄平
黙祷から練習再開春寒し 大溝妙子
眉の雪悲しみを笑むおみなかな 大山かげもと
震災の子らたのもしく卒業す 小川夏葉
余震吹雪救援に発つ背に祈る 尾﨑尚子
貝寄風や吾は傍観者とならじ 片山一行
身の内に春灯ともせる日を祈り 我部敬子
龍天に登り告げこよ建つ国を 唐沢静男
卒業や目を真つ直に被災の子 朽木直
避難所に拍手のありて卒業す 畔柳海村
浅蜊採る網流れ着く二タ七日 柴山つぐ子
地震津波瓦礫の町に梅の芽や 新谷房子
被災地に真の春陽願ひけり 高橋透水
つつましく光を掴み花辛夷 武井まゆみ
春の海悲しみの顔見せしとき 武田花果
春の奇禍富士は真白き衣まとふ 武田禪次
雁風呂や未知の奥なる火を起し 多田悦子
風光る瓦礫の中に道生めば 多田美紀
列島に祈るかたちの白木蓮 谷口いづみ



彗星集作品抄
伊藤伊那男選
水脈を引く光となりし春の鴨 我部敬子
凧日和とは長崎のなつかしき 村上文惠
身ぬちより骨の鳴る音涅槃雪 谷口いづみ
胸に挿す入学式の万年筆 鈴木てる代
幼児の一言は詩よ桃の花 杉阪大和
包まるる鶯餅の重さかな 塚本一夫
天心らも鮟鱇鍋を囲みしか 小坂誠子
料峭や湖面を残し暮れる山 唐沢静男
セロリ齧るヘップバーンの映画観て 本庄康代
寒声の太々と来る長廊下 谷岡健彦
死してなほ光はなさず冬の蝿 こしだまほ
母の日の母その母をいつくしみ 小池百人
黙々とかげろふを噛む羊かな 松代展枝
鷹鳩と化して雀の中にゐる 脇行雲
鶯餅障子明りに目の慣るる 三溝恵子
ふくろふの定かならざる首廻す 大溝妙子
さざ波の音に春立つ湖国かな 山元正規
堰堤に水盛り上がる初つばめ 五十嵐京子
教室の声遠くなる目借時 大野田好記
炭爆づる音に諸子の香の立ちぬ 塚本一夫
彗星集 選評 伊藤伊那男
水脈を引く光となりし春の鴨 我部敬子
| 水脈の先端にある鴨が一瞬光を発したように見えたという。この表現で詩に昇華したといってよかろう。一物仕立てで対象物を詠み切っている。春の鴨の哀れさが絡む所がよい。 |
凧日和とは長崎のなつかしき 村上文惠
| 長崎の凧揚は有名。春の空を見上げて、その風の様子に「ああ凧日和だ」と思う。そして「長崎は‥」と連想に繋っていくのである。「凧日和」が味。 |
身ぬちより骨の鳴る音涅槃雪 谷口いづみ
| 「骨の鳴る」には生命の根源に通じる「音」が感じられるようである。内省、内観的な独自の観点の句となった。 |
胸に挿す入学式の万年筆 鈴木てる代
| 万年筆を持つというのは一つ大人に近づく出来事なのである。入学祝いに親から貰った万年筆であろうか、胸に挿して誇らしいのだ。単純明快さがよい。 |
幼児の一言は詩よ桃の花 杉阪大和
幼児の口をついた一語が詩のようであったという。桃の花は邪気を払い齢を延べるというーーそこから桃の節句があるようだが、季語の斡旋が秀逸の句である。
|
包まるる鶯餅の重さかな 塚本一夫
| <街の雨鶯餅がもう出たか 富安風生>がある。春になると様々な餅菓子が出るが、鶯餅が先駆けだ。最も重量感がありそうで、そこを捉えたところが秀逸。春を迎える喜びが横溢している句となった。 |
天心らも鮟鱇鍋を囲みしか 小坂誠子
岡倉天心、茨城県五浦に拠点を置いた。その六角堂も今回の地震で消失の報があるが‥。鮟鱇鍋でも有名な地。
|
料峭や湖面を残し暮れる山 唐沢静男
| この句から私は諏訪湖を、また琵琶湖を思い出す。読み手の好きな湖を想起させる力がある。季感を的確に把握。 |
セロリ齧るヘップバーンの映画観て 本庄康代
| ヘップバーンとセロリ――その容姿といい雰囲気といい絶妙な組み合せだ。取合せの異色さを褒めたい。 |
寒声の太々と来る長廊下 谷岡健彦
| 寒中に喉を鍛えると美声になるという。さてこの句は、お寺であろうか?「長廊下」と具体的な物を置いて成功。 |
死してなほ光はなさず冬の蝿 こしだまほ
| 「冬の蝿」をよく観察している。死後も光っているという。嫌われものの蝿だけにいく分かの哀れさを伴うのだ。 |
母の日の母その母をいつくしみ 小池百人
| 言葉遊びの楽しさも俳句という文芸の特徴。二つのリフレインはあるが、三つで成功した珍しい例。 |
黙々とかげろふを噛む羊かな 松代展枝
| かげろふを「噛む」の機智的表現は好き嫌いが別れるかもしれない。「黙々」が「もぐもぐ」に通じる面白さ。 |
鷹鳩と化して雀の中にゐる 脇 行雲
| 七二候の中でも俳人好みの季語。群れ雀の中の一羽の鳩は実は鷹の化したものだという。平凡な風景からの想像。 |
鶯餅障子明りに目の慣るる 三溝恵子
春光の目映さの中から部屋に入って暫くの光景か。目が慣れると眼前に鶯餅が。光の変化をうまく捉えている。
|
ふくろふの定かならざる首廻す 大溝妙子
| 言われてみれば確かに羽毛に包まれていて首の様子ははっきりしない。それが良く廻るのだ。一つの発見がある。 |
さざ波の音に春立つ湖国かな 山元正規
| やはり琵琶湖あたりの風景か。さざ波の音に春到来を思う俳人の感覚が鋭い。「湖国かな」の古格も骨太でよい。 |
堰堤に水盛り上がる初つばめ 五十嵐京子
| すがすがしい句である。中七の「水盛り上がる」が手柄で初夏の兆しを掴んだ感覚は秀逸。初燕が効いている。 |
教室の声遠くなる目借時 大野田好記
懐しい。私などいつもこんな風な生徒であった。春の昼はとりわけ。ことに算数の時間などは夢か現か???。
|
炭爆づる音に諸子の香の立ちぬ 塚本一夫
琵琶湖の名物。義仲一族の亡魂が化したという。網焼きが一番。「爆づる音」がよい。京の粋人の垂涎.
|


銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
凍戻る百済滅びし城の山 飯田眞理子
うす紅の便箋買ふや寒の明け 池田華風
鳶口に乾ぶ鱗や冴返る 唐沢静男
不和の子を思うて打てり福は 内久保一岩
み仏の夫にバレンタインの茶を供ふ 柴山つぐ子
枝折れの谺遠くに凍豆腐 杉阪大和
春めくや胸板厚き甲斐の山 武田花果
如月を突切る電車海へ向く 武田禪次
わが影の辻に重なる寒夜かな 萩原一夫
歩み寄る孔雀の威に春うたがは ず 久重 凛子
行く年の空にアンテナ同じ向き 松川洋酔
背に余りゐる待春のランドセル 三代川次郎
翁といふ言葉はるけし鳴雪忌 屋内松山



綺羅星集作品抄
伊藤伊那男・選
待望の懐妊の報年明くる 青木志津香
からたちの棘より韓の凍戻る 飯田子貢
貨車つなぐ音の末尾を春の野に 伊藤庄平
栄転といふ別れあり春二 月梅沢フミ
鎌倉の恵方ことごと谷戸に尽く 大溝妙子
七日粥戦を知らぬはらからと 大山かげもと
立読のいつもの店は恵方なり 小川夏葉
残雪といふ美しき骸かな 尾﨑尚子
口開けの日の出を待てり鮑鉤 小野寺清人
手応への腰に伝はる桜鯛 片山一行
三椏の規則の中に咲きにけり 我部敬子
自画像のあいまいな笑み春立ちぬ 神村睦代
凍鶴の動かずにゐて際立ちぬ 川島秋葉男
春の雪軍靴の音を潜ませて 朽木直
香煙のたなびく先の白木蓮 畦柳海村
コロッケの衣の厚き万愚節 小滝肇
日脚伸ぶ暢気眼鏡の起草の間 權守勝一
繫留の船のあはひに春兆す 佐々木節子
国東の仏は野辺にやまざくら 笹園春雀
リヤカーで大根が着く川門かな 島谷高水
寒明けの十日厳しと信濃人 新谷房子
滾つ血の尾の先までも恋の猫 鈴木てる代
サイレンの真つ赤に吠える春の雪 高橋透水
土ばかりみつめて三椏の花は 武井まゆみ
臘梅に廃寺の慈悲の日ざしとも 竹内松音
ひとひらの葉をとぢこめし薄氷 武田千津
はぐれ来し鯨一湾どよめかす 多田悦子
叡山の百八ツの鐘湖に尽く 多田美記
藍甕の泡立ち盛ん春隣 田中敬子
母ひとり明治の雛にかしづける 谷川佐和子
さよならの手のひらひらと春隣 谷口いづみ
二輌車の世田谷線の春の旅 中村孝哲
豆まきを終へし力士が枡叩く 花里洋子
大橋と名乗るも小川水草生ふ 藤井?一
雪解風白樺の肌めくるかに 松浦宗克
悴みてイエスの肋仰ぎをり 松代展枝
どの兎にも分け隔てなき初日 無聞齋
京ことば間口をくぐり雛の店 村上文恵
老梅や朝な夕なの日をとどめ 村田郁子
朝光の移る早さよ寒卵 村田重子
金鈴めく花三椏の開きやう 山元正規
逢瀬の道亀裂あやなす御神渡り 吉田千絵
知床の海を突き刺し滝凍る 脇行雲


銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男
枝折れの谺遠くに凍豆腐 杉阪大和
| 私の育った信州では凍豆腐は日常食であった。豆腐を藁で結えたので干し上がったものにはその跡が残っていた。夜の寒気で凍らせて、昼間の暖気で水分を抜く。雪の日であったのだろうか、遠くで枝折れの音がしたという。作者,は飛?の育ちなので同じような体験をしたのであろう。取合せに臨場感がある。同時出句の,(ひらがなのやうに貸風花ただよへり)も、ひらがなの比喩が秀逸である。 |
不和の子を思うて打てり福は内 久保一岩
| これはもう一編の小説である。俳句というたったの十七音で、微妙な親子関係、会えば諍いがあるけれど、決して憎んだりはしていない、むしろ子の行く末を祈るような気持で心配しているーーそんな父親の心理が抽出されている。下五の「福は内」は作者の声だ。万感の思いが籠る。 |
春めくや胸板厚き甲斐の山 武田花果
| 固有名詞を生かすのは難しいものだ。安易に使ってもすぐ動く、底が割れる。そういう中でこの句は成功例といえよう。その地の「地貌」を捉えているのである。甲府盆地はまさに四方をすっぽりと山に囲まれている。信州方面は鉄壁の南アルプス、八ヶ岳。それを「胸板厚き」と詠み取ったのは見事。また「春めく」の季語の躍動感が良い。 |
翁といふ言葉はるけし鳴雪忌 屋内松山
| 鳴雪は松山藩士。明治後、常磐会寄宿舎舎監の頃、子規が入舎。二十歳年下の子規に俳句を学んだのである。子規没後も俳句の普及に務め、七九歳で没した。翁とは老人の尊称。温厚で謙虚であった鳴雪はその名にふさわしく、風韻のある句だ。私の師、皆川盤水も俳人協会の岡田日郎氏などが盤水翁と呼んでいた。そうした翁もいなくなった。 |
貨車つなぐ音の末尾を春の野に 伊藤庄平
| 「音の末尾」という表現は初めて目にした。なるほど、こういう比喩もあるのか!と感嘆した。行列とか手紙とか目に見える物の時に使う言葉を「音」に使った手柄だ。春の野にその音を残したという取合せも効いて、余韻が良い。 |
鎌倉の恵方ことごと谷戸に尽く 大溝妙子
| 地名を使った句のことを先述したが、この句も「鎌倉」を生かして、いや鎌倉でなければ成立しない句にしているようだ。谷戸という地形は関東特有で、鎌倉は顕著。その谷戸ごとに武将の館や菩提寺があった。狭い土地なのですぐに山に突き当る。歴史的感興を呼び起す句となった。 |
手応への腰に伝はる桜鯛 片山一行
| こういう句の場合、下五の季語が動かないかどうかが重要点となる。大型の魚なら何でも当てはまるかどうか?色々入れ替えてみて桜鯛は動かない!鯛がもっとも美しい時期、姿も良し。漁師なら高値で売れる期待もある。「腰に伝わる」に傍観者では描けない臨場感がある。 |
どの兎にも分け隔てなき初日 無聞齋
| 一読顔がほころぶ句である。今年が兎年であることもあり尚更。ただそのことを離れて、例えば学校で飼っている兎小屋でよい。「分け隔てなき」に優しさが混る。仏教思想のように遍満している初日にこの句の普遍性がある。 |
京ことば間口をくぐり雛の店 村上文恵
| 京ことば(の人が)省略されているのである。角川源義の(何求めて冬帽行くや切通し)と同じ俳句的省略である。中七の「間口をくぐり」の場面転換がよく、雅な雰囲気を醸し出しているようだ。 |
その他印象深かった句
み仏の夫にバレンタインの茶を供ふ 柴山つぐ子
鳶口に乾ぶ鱗や冴返る 唐沢静男
如月を突切る電車海へ向く 武田禪次
歩み寄る孔雀の威に春うたがはず 久重凛子
七日粥戦を知らぬはらからと 大山かげもと
土ばかりみつめて三椏の花は 武井まゆみ
二輌車の世田谷線の春の旅 中村孝哲
悴みてイエスの肋仰ぎをり 松代展枝
| 心の襞の出ている句である。人にはさまざまな思いや身に降りかかる難事がある。他人から見たらどうでもよいことでも自分にとっては曲げられないこともある。そんな様子がよく出ているので、主観が強い句柄ながら共感できる作品になったのであろう。同時出句の∧ショールの身ときに重たき秘密持つ∨も同様。写生派の作者には珍しい句群。 |
冬薔薇とは言はれ得ぬ開きやう 武田花果
冬蝶のかそけき日差持ち寄れり 同
| 両句共、対象物をよく観察した一物仕立の句。その写生の中におのづから滲み出る、この作者らしい抒情の水脈が良い。冬薔薇にしては奔放な咲き方だと言う発想には意外性がある。二句目は「持ち寄れり」と複数にしたところが味わいである。一物仕立で成功した句には、その対象物を詠み切っただけでなく、人間界への寓意が出るものだ |
東京に大川のあり都鳥 松川洋酔
| ここで言う大川は隅田川のことである。そして都鳥があるからには、『伊勢物語』の∧名にし負はばいざ言問はん都鳥わが思ふ人はありやなしやと∨が下地にあるのだ。わざわざ「東京」を持って来たのは、時空を越えても男の心情は変らないということを言うのであろう。日頃言い過ぎてしまうところのある作者だが、この抑制は良い |
茶柱を誰にも告げず桜餠 笹園春雀
| 茶柱が立つと吉事の兆しがあるとして喜ぶ。こういう小さな事でも、一日に張りがでることがあるものだ。これを人には言ってしまうとツキが落ちてしまうかもしれない。そこはかとない作者の心情がよく出ているようだ。桜餠という重量感のある季語が下五に据ったことで句が締ったようだ。少し浮き立つ春の季感も出て、取合せに成功した |
無線より登頂明日と冬銀河 多田悦子
珍らしい場面を詠んだ句である。聞けば作者は学生時代からの登山愛好家という。冬山にビバークしていた仲間からいよいよ明朝は登頂を目指すという無線が入ったのである。見上げると満目の冬銀河である。人知を超えた壮大な自然を詠みとっているようだ。体験の裏打のある臨場感
|
問へど答へぬ人にも告げむ春の月 村田郁子
すぐに思い出すのは、中村汀女の∧外にも出よ触るるばかりに春の月∨であった。作者のご主人村田脩先生はその中村汀女の主宰誌「風花」の編集長を長く努めた方であったから、当然この句が胸底にあったものと思われる。人の世の節理とはいえ「問へど答へぬ人」の措辞は心に響く。連綿たる師系を踏まえて亡き人を思う相聞歌である。
|
隣りよりレモン汁飛ぶ牡蠣の店 島谷高水
いろいろな食べ方があるが、生牡蠣はレモンを絞るだけというのが良い。牡蠣フライに塩とレモンというのも良い。句では臨席からレモン汁が飛んできたという。そこに混み合っている店の様子が如実だ。注文の声や皿の音なども聞こえてくるようである。「飛ぶ」で全てを活写した。
|
その他印象深かった句
湯ざめして妻の羽織れる男もの 池田華風
大津絵の仏に貰ふ初笑 杉阪大和
冬帽子銀座へ向かふ父の背 武田禪次
そこまでと言ひつつ駅へ冬夕焼 梅沢フミ
麗かや吹けばふくらむ紙の鶴 小野寺清人
立ち止まることも胆力月凍る 片山一行
永らへし命大事や寒卵 權守勝一
ここに老いここもふるさと初詣 武田千津
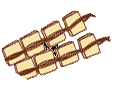


星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
三椏咲く大和は山も恋せりと 大河内 史
戯れにパンの耳買ふ啄木忌 加藤 恵介
水引の鶴結納の春を待つ 堀内 清瀬
友逝きし故郷を焦がす野焼かな 市毛 唯朗
裸婦の絵を未完のままに卒業す 松崎 逍遊
春浅し寄木細工のひみつ箱 中野 智子
尼さまの手から始まるてまり唄 杉本 アツ子
ふらここをまだ漕げぬ子の背へ手を 住山 春人
百色の色鉛筆や春待ちぬ 塚本 一夫
柳橋たもとにいくつうかれ猫 白濱 武子
荒東風に飛び散る波濤舞ふかもめ 小松 葵
蔵町に残る寒さや所酒 吉沢 美佐枝
鴨の水脈池の広さにひろがれり 戸田 礼子
城濠の鯉の動きも春めけり 原田 さがみ
三椏や小人のくすくす笑ひとも 島谷 操
暖簾上ぐ寒紅の濃き女将かな 相田 惠子
癌治療終ふ立春の光満ち 秋元孝乏
雪の朝轍の跡を譲り合ふ 穴田ひろし
早春の川瀬に光る飛沫かな 荒木 万寿
短命の母に手向けし雛明り 有賀 稲香
末黒野に立ちて一番星の綺羅 有澤 志峯
冬落暉たちまち起る帰心かな 飯田 康酔
存念の色と思へり寒紅梅 五十嵐 京子
ポピー一束茎の曲りのさまざまに 石川 眞江
折れさうなほどにますぐや冬薔薇 伊藤 政三
三椏の花に逢ひたく里がへり 今村 八十吉
踏青や海原果つる浜辺まで 岩崎 由紀
みぞ川の石のさざめき寒明ける 上田 裕
餅の黴けづれば祖母の声きこゆ 植村 友子
頬あつく野火の猛るを見てゐたり 大木 邦絵
受験子の親子の上りホームかな 大西 けい子
山頂に悴む自動販売機 大西 真一
中吊りの桜たどりて旅の夢 大野田 好記
白梅の盛りに受くる祝詞かな 岡村 妃呂子
机上にす聖書一冊春隣 小坂 誠子
風花の飛び交ふ彼方富士の見ゆ 尾崎 幹
くるくると鱵丸まる椀の中鏡山 鏡山 千恵子
梅が香や見上ぐる先の天主閣 亀田 正則
立ち止り来し方思ふ懐手 唐沢 冬朱
野火守の燃ゆる遠くをみてゐたり 北澤 一伯
恋猫の金物にまで爪の跡 北原 泰明
大島を紅で縁取る寒夕日 木部 玲子
黒板の匂ひ纏ひて卒業す 柊原 洋征
こだまする向かふ三軒福は内 黒岩 清女
岩山は神の依代山桜 黒河内文江
奈良井川洗馬といふ池に馬冷す 小池 百人
二人寝の足のとどかぬ行火かな こしだ まほ
其処此処に祭と聞けば血の滾る 小林 沙織
かかげ持つ傘の重さよ春の雪 小林 雅子
奇石あまた神なる技や冬の濤 阪井 忠太
別れ霜一村覆ふ遠浅間 佐々木 終吉
家々の雛飾り見て歩く鞆 佐々木 美智子
寒行の遠退きてゆく仕舞風呂 佐藤 幸子
まどろみの嬰にひひなの灯を点す 三溝 恵子
東風吹きて富士額なる少女かな 島 織布
水茄子を食む楽しさや昼餉時 白鳥 はくとう
海風に暴れし炎どんど焚く 鈴木 淳子
一言を語れば足りて春隣 角 佐穂子
初物と汐垂る若布提げて来し 高橋 アケミ
風花の風に素直でありにけり 竹本 治美
春寒や交す言葉も一様に 田中 寿徳
駿河路や茶の花の辺の暮れ残る 谷岡 健彦
スカイツリー見に行く話春隣 多丸 朝子
公園に?梅の香のひとところ 民永 君子
風花の一つを追へば軒に消ゆ 近松 光栄
寄す波に蹴りを一発寒稽古 千葉 薫
妻がゐてピザ焼きあがる如月に 津田 卓
卒業を祝ふ言葉の清々し 土屋佳子
白梅に水の匂ひの漂へり 坪井 研治
白鱚を箸の先にていただきぬ 徳永 和美
雪だるま子にも孫にも似ぬ美男 富岡 霧中
川音に春の兆せる嵐山 中川 孝司
別れ雪ふるひてもなほふるひても 中島 雄一
漕ぎ難きほどふらここの低きかな 中村 寿祥
海面に明るさありて春の雪 中村 紘子
先代と似たる法話を春彼岸 南藤 和義
新玉葱皿の花柄透かしたる 西原 舞
春寒し手乗りインコの足の裏 萩野 清司
顔だけに日に当たるなり籐寝椅子 橋本 行雄
坂道を走り抜けたる恋の猫 長谷川 千何子
白鳥の去る日は近し水光る 花上 佐都
大仏の螺髪も氷る余寒かな 播广 義春
音立てて掃除機拾ふ年の豆 藤田 孝俊
猫通ふ切り込みを入れ障子貼る 藤森 英雄
一つ見え次々と見ゆ蕗の薹 藤原 近子
待春の砂場に赤きシャベルかな 保谷 政孝
地下鉄のぬつと出て来る余寒かな 堀 いちろう
寒厨やかんの怒り収まらず 堀江 美州
倒木も仏に見えて草朧 本庄 康代
新緑や百幹あれば百の色 松崎 正
化粧塩纏ふ炉端の山女かな 松田 茂
早起きにふと探梅を思ひ立つ 松村 郁子
春の夕鴉ゆつたり羽煽る みずたに まさる
古稀にして古書店開く梅一輪 宮本 龍子
輪郭の薄き菫や窓際に 森濱 直之
友去りし時の隙間に柳絮飛ぶ 家治 祥夫
花芯へと渦巻き解いて蝶の口 安田 芳雄
雪吊の雪なき庭を飾りをり 山下 美佐
天秤の釣合ひ正す蜆売 山田 礁
三椏や水のたばしる紙の里 山田 康教
春泥へ轍のこして朝市女 山田 鯉公
図書館にしばし立寄る春時雨 吉田 葉子
春うらら弦の織りなすハープの音 和歌山 要子



星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
三椏咲く大和は山も恋せりと 大河内 史
| 三椏の三と大和三山を取合せた、技を潜ませた句。私ごとだが、昨年末、天香具山に登った。冬靄の中に畝傍・耳成が浮かんでいた。故事によれば三山に恋の争いがあったという。「山も」とあるので当然、神も人も太古より三角関係があったということを匂わせて、楽しい句となった。 |
戯れにパンの耳買ふ啄木忌 加藤恵介
| 石川啄木に〈友が皆われより偉くみゆる日よ花を買ひきて妻と親しむ〉がある。生涯を貧窮に悩んだ啄木の忌である。句は先述の歌に呼応するように、パンの耳という貧窮の象徴のような「物」を提示したところが面白い。「戯れに」には現代の目、遊びの目がある。忌日句として秀逸。 |
水引の鶴結納の春を待つ 堀内清瀬
知的興味を覚える句である。水引でできた鶴――季語ではない鶴、生き物ではない鶴――が春を待っているという。当然春を待っているのは、花嫁とその家族なのだが、それを鶴としたところが機知である。的確な季語の斡旋。
|
友逝きし故郷を焦がす野焼かな 市毛唯朗
| 一級品の追悼句である。野焼の炎は弔いの炎でもある。「故郷を焦がす」の把握は一見大袈裟な感じがせぬでもないが、逆に作者の嘆きの大きさでもあり、深さでもあり、この誇張は頷けるものである。 |
裸婦の絵を未完のままに卒業す 松崎逍遊
| 高校時代の回想なのであろう。「裸婦の絵」というところが出色である。何やら淡い恋も未完のままに終わったような青春の残像の象徴のように思われてくる。青春というものへの幽かな悔恨に読者は共感するのである。 |
春浅し寄木細工のひみつ箱 中野智子
| 小田原吟行の嘱目であると思われる。寄木細工というのはあの独特の木目を生かした箱根細工。ひみつ箱というのは仕掛けがあって簡単には蓋や抽出しが開かないというものを言うのであろう。中七下五の引き付け方がよく、春浅しの季語に若干の愁いと詠嘆が感じられるようである。 |
ふらここをまだ漕げぬ子の背へ手を 住山春人
| ほほえましい風景である。私にも憶えがあるだけに愛着を持った句である。この作者は句歴は浅いと思うが、子供を詠んだ句に出色のものがある。男の「子育て俳句」は珍しいが、是非その成長過程を詠み続けてほしいものだ。背(せな)へ手を」に父親の実感が深い。手の温みが伝わってくる。 |
柳橋たもとにいくつうかれ猫 白濱武子
柳橋は台東区にあり、地名は神田川の河口に架る橋の名に因む。江戸時代からの花街である。ちなみに新橋というのは明治初期官庁街近くに出来た花街で、新柳橋である。
さて花街であるだけに、うかれ猫の斡旋が楽しい。「たもとにいくつ」という素気ない表現がまた良い。
|
鴨の水脈池の広さにひろがれり 戸田礼子
池の広さにひろがれりーーの把握は秀逸である。鴨が一羽か二羽しかいないだろうということや、そもそも小さな池であること、風もなく鏡面のような水面であることなどが読み取れるのである。水脈が広がることは誰でも詠めるが、「池の広さに」は詠めなかった。良く物を観察する、
人が見なかった所への目配りがあるーー写生の良さだ。 |
ポピー一束茎の曲りのさまざまに 石川眞江
| ポピーは、ひなげし。私の好きな花だ。花束になったものは葉を持たず、長い茎の先に花と蕾をつけている。この句のように茎は真直ではなく、各々微妙な曲りや捻れがある。花にではなく茎に注目したところが、この句の手柄である。俳句は誰もが見ているけれど、見逃しているところを見る、一歩踏み込んで対象物の本意に迫るのが勘所。そうした意味でこの句は「物」を見ることに徹した句といえよう。だからこそおのづから詩情を醸すのである。 |
折れさうなほどにますぐや冬薔薇 伊藤政三
| 前の句で、写生の勘所に触れたが、この句も同様に評価できる句である。真冬に咲く薔薇を詠んでいるのだが、作者はその茎に注目している。花を支える冬薔薇の細い茎、しかし意外にも強靭で真直なのである。そこに発見がある。 |
蔵町に残る寒さや所酒 吉沢美佐枝
| 所酒――あまり使わない言葉だが、地酒のことである。蔵造りの商家の残っている町、そう私の思い出で言えば数年前柴山つぐ子さんの案内で小諸に遊び、土産の酒を求めたのだがこのような蔵町であった。後継が途絶えて醸造は止めて親戚の酒蔵の酒を小売していると言っていた。「残る寒さ」が句の味わいで、凛とした空気を思う。 |
その他印象深かった句を次に
存念の色と思へり寒紅梅 五十嵐京子
春うらら弦の織りなすハープの音 和歌山要子
百色の色鉛筆や春待ちぬ 塚本一夫
尼さまの手から始まるてまり唄 杉本アツ子
三椏や小人のくすくす笑ひとも 島谷操
みぞ川の石のさざめき寒明ける 上田裕


2011/5/20 撮影 TOKYO モッコウバラ




|

![]() 5月号 2011年
5月号 2011年