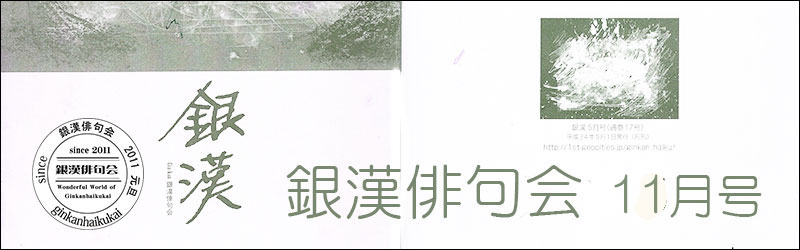伊藤伊那男作品
向日葵 伊藤伊那男
麦酒つぐ水平線の高さまで
風鈴の今宵は暴れん坊である
川床や京の女の生返事
七夕の金平糖は星の数
胡瓜もむ欲得の世の隅にゐて
向日葵の真正面といふ怖さ
花氷華燭の典に溶け出せり
頼りなき甘さだいじに枇杷熟るる



今月の目次
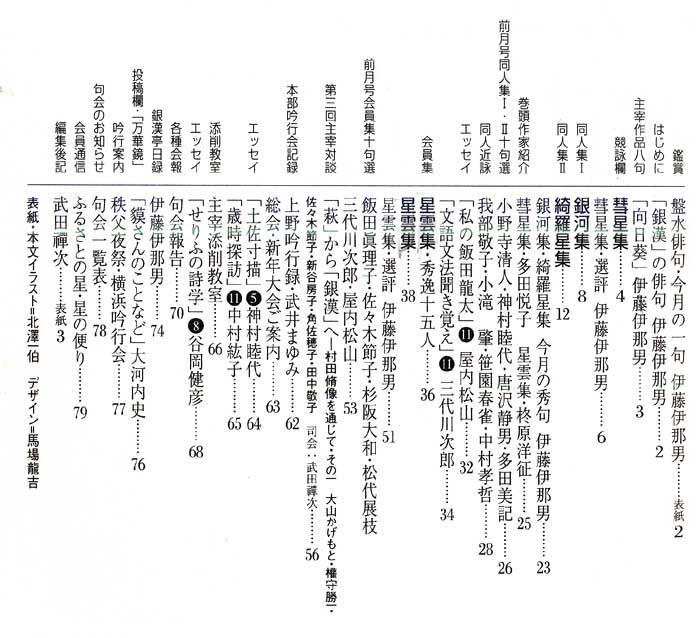

銀漢俳句会・11月号


銀漢の俳句
伊藤伊那男
実りの秋の「おいしい俳句」 (「俳句」十月号四季々彩より転載)
栗飯を子が食ひ散らす散らさせよ 石川 桂郎
切干やいのちの限り妻の恩 日野 草城
鳥渡るこきこきこきと罐切れば 秋元不死男
柿喰ふや命あまさず生きよの語 石田 波郷
葡萄食ふ一語一語の如くにて 中村草田男
新じやがをほかほかと食ひ今日を謝す 大野 林火
菊なます口中冷えて来たりけり 草間 時彦
越後人菓子食ふごとく鮎食へり 高木 良多
月山の見ゆと芋煮てあそびけり 水原秋桜子
梨白し白磁の中にとりて食ふ 皆吉 爽雨
おいしい俳句には二種類あるのだと思う。一つは純粋に美味を追求した俳句、一つはその食物に作者の思い出や感慨が絡むもの、ということになろうか。今は死語に近くなったが、「男子厨房に入らず」という諺がある。昭和30年代位までは、男子が料理を作ったり、口中の福を語るのは慎みがないという風潮があった。従って俳句にもそうした享楽は抑えられていたようだ。もっとも、戦後しばらくは飢えをどう満たせるかが最大の関心事であり、うまい、まずいなどということは埒外という時代であったことも事実である。
最初にあげた石川桂郎の句は、まさに戦争直後の窮乏時、たまさか手に入れた栗で飯を炊いた。こぼそうが、頬に付けようが構わない、ともかく食べて喜んでくれ、という親の思いがひしひしと伝わる。親はほんの少ししか箸を付けずに卓袱台の向う側から見守っている。子供はこの栗飯の味を一生憶えていることであろう。 日野草城の句も切干大根でさえ貴重な時代の句であろう。秋元不死男の句は、〈罐〉と言うだけで何の缶詰かは不明であり、食物のなかに入れてよいものかどうか迷った。ただその当時では缶詰も宝物のような存在であったからこその句だと思う。鯖か秋刀魚かであろうが。 石田波郷にも〈風の日は風吹きすさぶ秋刀魚の値〉があり、まだまだ日本も高度成長期に入る前の時代が彷彿する。
一方中村草田男の句は、葡萄の味には無関心であり、人間探求派の句だな、と思う。大野林火、草間時彦の句になると、しみじみその味を楽しんでいることが伝わってくる。住みよい時代になってきたのである。水原秋桜子の句は今では季語として一般化した〈芋煮会〉の嚆矢の句である。〈芋煮て〉に季語になる寸前の面白さが窺われる。
豊饒な世となった現在、食物俳句は氾濫している。だが、単に珍しいもの、うまいものを並べてもよい句にはならない。やはりその作者の境涯や人生に絡むか、その食物に触発されて思い出される感慨がなければ、人の心を打つ作品にはならない。食物俳句にも人生の裏打ちが求められるのだ
|



盤水俳句・今月の一句
枯芦のゆたかにけふの日をとどむ 皆川盤水
平成10年、茨城県稲敷郡美穂村の霞ヶ浦湖畔に先生の第九句碑として建立された句。除幕式には私も参加したが、その直会の席で先生が――昭和51年12月に「風」の沢木欣一らと一泊吟行をした折の句で、水原秋桜子に褒められた思い出の深い句だ――とのエピソードを披露された。「ゆたかに」は先生の句に時折見る言葉。先生が使うとおおらかな余裕が出て気分がいい。そのおおらかさを下五の「日をとどむ」のなみなみならぬ写生の眼できっちりと締めている。
(昭和51年作『板谷峠』所収)
伊藤伊那男
|


彗星集作品抄
伊藤伊那男選
たましひのかたちに撓ふハンモック こしだまほ
草取を繰り返し来し畑を売る 島谷 高水
すぐそこがまだまだ着かぬ秋暑し 榎本 陽子
雷を待たせてゐたる野外劇 隈本はるこ
終戦の日と言ふ貌のありにけり 矢野春行士
その果ては雲にまぎるる蕎麦の花 伊藤 庄平
天に地に残暑の出口まだ見えず 矢野春行士
蚊帳を吊るくらしを内に奈良格子 多田 美記
貼り終へて蜘蛛の孤独の始まりぬ 山元 正規
天上大風良寛の筆うちはかな 神村 睦代
色無き風虚子俳小屋の玻璃みがく 武田 花果
新涼や風信帖の風の文字 伊藤 政三
胴震ひしては昭和の冷蔵庫 唐沢 静男
横須賀の腰で縛れるアロハシャツ 小野寺清人
地下鉄の中の黙祷広島忌 脇 行雲
うぶすなの銀河恋しや生家売り 青木志津香
踊りの輪踊る仕草でそつと抜け 有澤 志峯
子規庵の明治の風に糸瓜揺る 藤井 紘一
追慕の念つのる一とせ萩の花 和歌山要子
坂東太郎銀漢の尾を源流に 中村 孝哲
彗星集 選評 伊藤伊那男 伊藤伊那男•選
たましひのかたちに撓ふハンモック こしだまほ
| ハンモックであるから当然身体の線に沿って撓う。そう詠むのが普通であり、しかしそう詠んだら面白さも何もない。とにもかくにも「たましひ」を持ってきたところが手柄である。物理的な身体の形ではなく、その人の生い立ちや思想、人生観、生きざまが身体の形になって撓うのだと言う。そのことによって写生から一歩踏み出して作者の心のありどころ、精神性が浮かび上がってくる。作者名を聞くと、4月号の巻頭が<,たましひのはづれかけたる日向ぼこ>であった。「たましひ」は一先ずここまで。 |
草取を繰り返し来し畑を売る 島谷 高水
今日的社会事情であるのかも知れない。少子化時代でもあり、また人口の一局集中時代でもあり、過疎化は進む一方である。先祖から引き継いできた畑も売らざるを得ない。
「繰り返し来し」にその人物像が鮮明に描出されていてここが眼目。売ることが決って、明日引き渡すという直前まで草を毟っているのではないか、と思わせる。 |
すぐそこがまだまだ着かぬ秋暑し 榎本 陽子
| 「涼し」という夏の季語がある。夏の日の思いがけない涼しさを喜ぶ季語だ。「新涼」は秋。夏はその心構えがあるがが、秋の暑さはとりわけこたえるものだ。例えばいつも行く郵便ポスト、いつもの駅がずい分遠く思える。「秋暑し」の季語の本意をしかと摑んでいるのだ。もしこの下五を「大暑かな」「暑さかな」としたら全く興趣がないことが解るであろう。ここが季語の配合の勘所である。 |
雷を待たせてゐたる野外劇 隈本はるこ
| 「待たせてゐたる」が俳諧味である。人を待たせているのではなく、人智の及ばない自然現象の雷であるところが面白いのだ。野外劇が終るまでは何としても雷雨を避けたい、という切なる思いがよく出ている。悪い雲がで始めているのだが「待て待て」と祈る。 |
終戦の日と言ふ貌のありにけり 矢野春行士
| 戦後も60年以上となると経験をした語り部も少なくなっている。前にも書いたが、若者に「かつて日米は戦ったのだ」と言うと、「で、どっちが勝ったの?」という笑えない質問が返ってきたという話がある。戦場を体験した方といえばもう85歳以上ということになろう。やはりその日は特別な感慨にひたることであろう。おのずから哀情が違うのだ |
その果ては雲にまぎるる蕎麦の花 伊藤 庄平
| 良い蕎麦は霧の湧く痩せた傾斜畑。見上げるとその頂きの上は雲の中。美しい風景で静かな躍動感がある |
。
天に地に残暑の出口まだ見えず 矢野春行士
| 残暑の「出口」を天と地に求めた異色の発想。独自の目。 |
蚊帳を吊るくらしを内に奈良格子 多田 美記
| 奈良格子が何ともいい。「くらしを内に」が慎ましい。 |
貼り終へて蜘蛛の孤独の始まりぬ 山元 正規
| 待つことが仕事の蜘蛛を「孤独が始まる」とみた機知。 |
天上大風良寛の筆うちはかな 神村 睦代
| 三段切れに近い危さも味わいのうちか。良寛の庶民性。 |
色無き風虚子俳小屋の玻璃みがく 武田 花果
新涼や風信帖の風の文字 伊藤 政三
胴震ひしては昭和の冷蔵庫 唐沢 静男
| 昭和が終って二三年。「は」の助詞が効果を発揮した。 |
横須賀の腰で縛れるアロハシャツ 小野寺清人
地下鉄の中の黙祷広島忌 脇 行雲
うぶすなの銀河恋しや生家売り 青木志津香
踊りの輪踊る仕草でそつと抜け 有澤 志峯
いい所を詠んだ。下五は「抜け出せり」位に抑える事も。
|
子規庵の明治の風に糸瓜揺る 藤井 紘一
| 明治の風がいい。この庵には明治が染み付いているのだ |
。
追慕の念つのる一とせ萩の花 和歌山要子
坂東太郎銀漢の尾を源流に 中村 孝哲



銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
積めるだけ積みて驢馬車の西瓜売 飯田眞理子
踊りの輪暗き方へと膨らめり 池田 華風
夏痩せて眼光ばかりものを言ふ 唐沢 静男
校庭の対角線を蝗飛ぶ 久保 一岩
明日帰る夜更の椅子に帰省の子 柴山つぐ子
水よりも風に流されあめんばう 杉阪 大和
猿田彦の衣装干しある青野かな 武田 花果
端居して常世へ戻る階一つ 武田 禪次
原爆忌路面電車の歪み過ぐ 萩原 一夫
暁の蟬に耳より寝覚めけり 久重 凛子
夕立のあつけらかんと過ぎにけり 松川 洋酔
夕立の国境に出すパスポート 三代川次郎
子の夢路灯してゐたる蛍籠 屋内 松山



綺羅星集作品抄
伊藤伊那男選
嬰児は手の五指ひらき若楓 青木志津香
をみなへしさかりの色にむせにけり 飯田 子貢
田を捨てて麦藁帽子捨てきれず 伊藤 庄平
百日紅路地曲るまで見送りて 梅沢 フミ
みすずかる信濃の朝を夏つばめ 大溝 妙子
鵜篝に金色の眼の逸るかな 大山かげもと
川底の雲に乗りたる青大将 小川 夏葉
オルメカ展幾千年の晩夏まとふ 尾﨑 尚子
ハンモックたうたう降りて張り直す 小野寺清人
夕凪のみぞおちにある微熱かな 片山 一行
夏至のまま日付変更線越ゆる 我部 敬子
波の音の静かなる日の新松子 神村 睦代
遠雷やパズルに足りぬひとかけら 川島秋葉男
夕立を連れ来る山の郵便夫 朽木 直
佐渡を向く鐘撞堂の冬構 畔柳 海村
朽ち舟の沈まぬ舳先秋の蝶 小滝 肇
枝豆のころがり影もころがれり 佐々木節子
紫陽花の青の迷路に奥の院 權守 勝一
義経の覇気いまひとつ菊衣 笹園 春雀
古里も旅館泊りや遠蛙 筱田 文
苦瓜の結局行きたき方へ伸ぶ 島谷 高水
父母は会へているのか星祭 新谷 房子
片蔭の動きて象の動きけり 鈴木てる緒
阿呆と言ふ元気いただく阿波踊 高橋 透水
更衣とて一枚をぬぎしのみ 武田 千津
空蟬の一脚は力脱けてをり 武井まゆみ
向日葵やモスクの町を発てばすぐ 多田 悦子
かなかなや躓き下る柳生道 多田 美記
蚊一匹敵の小ささこそが敵 田中 敬子
夏帽子ゆく燈台の螺旋階 谷川佐和子
友の忌の無音ひとしほ遠花火 谷口いづみ
大川の左岸に遊ぶ巴里祭 中村 孝哲
尿前の関に風音葛の花 花里 洋子
秋立つや足は自つと小倉城 藤井 綋一
冬夕日焦点は今時計塔 松浦 宗克
思ひきり昼寝の顔も定年後 松代 展枝
夜の秋や櫂に乱るる星の影 無聞 齋
坂あれば港が近し長崎忌 村上 文惠
忘却といふも果敢なし秋の星 村田郁 子
三輪山の風の存問茅の輪かな 村田 重子
ふるさとの顔に戻りし盆休 山元 正規
あしむらを抜けて飛び交ふ草蛍 吉田千絵子
箸一本立てて金魚を葬りけり 脇 行雲


銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男
端居して常世へ戻る階一つ 武田 禪次
| 濡縁を見かけなくなった今日、また皆が時間に追われる今日、端居とは贅沢な!しばし端居の時間を過すと何やら浮世離れをした気分になったのであろう。おもむろに現実の世界―常世―に劣る。その結界が濡縁と居間との境のわずか一段の段差。そこに目を付けたところが味わい。 |
夕立の国境に出すパスポート 三代川次郎
| どこへの旅か、地続きにある検問所で入国審査を受けているのである。そこへ夕立が。句からはそれほど開放的ではない国へ入る緊張感が漂っているように思われる。感情を入れず淡々と作っていることでむしろ凄身が出てくるのである。俳句的湿度を払拭した作句法。 |
明日帰る夜更の椅子に帰省の子 柴山つぐ子
| 俳句は作者の手を離れて一人歩きをしていくと言われるが、また一方では作者名が「前書き」ということもある。作者は今夏30数回の放射線治療を受け、最後は声の出ない日々を過ごしたと聞く。嬬恋村に住む作者を子息が見舞ったのであろう。ほとんど会話することができないまま明日別れる。その細やかな親子の心情が籠められて滋味が深い。同時出句に<二人目の父となる子や銀河濃し>があった。昨日久々電話をいただいた。「先生声が出ました」と。 |
田を捨てて麦藁帽子捨てきれず 伊藤 庄平
| 今日的な風景ということになろうか。特に福島県の出身である作者には、今夏は特別な感慨があるのかもしれない。稲作を断念した農家が、ずっと被っていた麦藁帽子をいつまでも捨てられずにいる。短編小説を読んだような後味である。同時出句の∧扇風機うしろ寂しき形して∨も擬人化した手法で機会に哀感を持たせている。 |
義経の覇気いまひとつ菊衣 笹園 春雀
菊人形の句はさんざん詠まれており、類型は免がれがたいところだが、この句はそれを乗り越えているように思う。実像は知らぬが、物語では華奢な美男子のイメージの義経だからこその句で、固有名詞が動かない。吉野の静との別れの場面か、あるいは安宅の関の場面か、とも思ったが、いや、菊師の失敗作とみるのもまた楽しい。
|
古里も旅館泊りや遠蛙 筱田 文
| 身に入みる句だ。私も昨年、信州の生家を遠い親戚に譲渡した。たまに帰るときはホテル泊りである。そんな風にして故郷は遠くなって行く。この句の作者も同じような心境なのであろう。「遠蛙」という季語の斡旋が何ともよい。今も蛙の声は残っているのである。読み過ぎかもしれぬが「遠」の文字に回顧の念も滲んでいるようだ。 |
大川の左岸に遊ぶ巴里祭 中村 孝哲
| 大川はすなわち「隅田川」。その左側といえば上流に向かっていうと「浅草」となる。俳句という短い詩型なのに、「浅草」と言わず、わざわざ「大川の左岸」と言うところが、小説家志望であったこの作者の憎い手法。多分大川をセーヌ川とダブらせているのである。ちなみに「巴里祭」はフランス革命でバスチーユ監獄を占拠した7月14日のこと。しかし日本だけの呼称で、それは『七月十四日』という題の映画を日本で公開したとき、『巴里祭』と邦訳したことから定着したのである。「遊ぶ」がいい。 |
思ひきり昼寝の顔も定年後 松代 展枝
私は昭和24年生まれの団塊の世代のまん中だが、友人が次々に退職をしていく。集まりにもだんだん背広姿がなくなっていく。定年は人生の大きな節目である。「思い切り昼寝の顔も」とは言い得て妙。こんな表現の句は今までになかったのではないか。金を稼ぐための予定が入っていない安堵の顔なのであろう。「も」の助詞が効いている。
|
ふるさとの顔に戻りし盆休 山元 正規
| これも定年後であるかもしれない。就業中の二三日の休暇ではこうはいくまい。好きなだけいてよい盆休み。徐々に地元に和んでいくのである。訛なども出るようになり、盆踊の輪にも入ってみようかなと•••そんな場面であろう。 |
その他印象深かった句を次に
踊の輪暗き方へと膨らめり 池田 華風
夏痩せて眼光ばかりものを言ふ 唐沢 静男
父の日を吾に重ぬる鶏頭花 久保 一岩
画架を組むけふ一日の泉の辺 武田 花果
暁の蟬に耳より寝覚めけり 久重 凛子
遠雷やパズルに足りぬひとかけら 川島秋葉男
箸一本立てて金魚を葬りけり 脇 行雲



星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
面差しを父に重ねるパナマ帽 中野 智子
デザートの皿のうへなる遠花火 こしだまほ
座蒲団の上へ来てゐる夜の秋 谷岡 健彦
青萩のすみずみにある朝日かな 西原 舞
とほくなる音心地よき昼寝かな 伊藤 政三
地蔵会や蠟の匂ひを重ねつつ 有澤 志峯
ペン皿に異国のコイン夏の果 堀内 清瀬
盆の雨仏の父母に傘をさす 内山 寿子
団扇みな一瞬止まる土俵ぎは 大河内 史
遠雷や木彫りの象にガラスの眼 鈴木 廣美
裸子を錦江湾に放ちをり 柊原 洋征
墓洗ふ生涯島を出ぬくらし 高橋アケミ
でこぼこの薬缶が一つ滝行場 山田 康教
焚き殻の渦そのままに蚊遣香 吉沢美佐枝
父来たるらし玄関に今年酒 松崎 逍遊
画作する心給ひし朝の露 相田 惠子
秋扇座右の銘をしたためて 秋元 孝之
かなかなの声も混ぜ込み土を練る 穴田 ひろし
師を偲ぶ汗の賜物句座続く 荒木 万寿
かなかなや夕光滲みる海鼠壁 有賀 稲香
炎帝の伸しかかりたる故郷かな 飯田 康酔
外井戸に粗砥仕上砥稲の花 五十嵐 京子
梅雨明くる強き地震を伴なひて 石垣 辰生
甚平に風の和らぐ木蔭かな 市毛 唯朗
脳味噌を妻と貸し借り夏を越す 今村八十吉
釣り船の渡り終へたる月の幅 岩崎 由紀
夏雲の陣を向ふに千曲川 上田 裕
天上に届かんとして朴の花 植村 友子
肝心な言葉花火に掻き消され 榎本 陽子
これ以上焼けぬ顔してガードマン 大木 邦絵
棟梁の位置のたがはぬ三尺寝 大西 真一
苦瓜の蔓のわがまま妻のわがまま 大野 里詩
小鳥来て庭木のしなり音もなく 大野田好記
夏休み真つ最中の子ら燥ぐ 岡村妃呂子
夏休み生きもの係活躍す 小坂 誠子
婦人会みんな揃つて秋扇 尾崎 幹
振り向けば高野すつぽり虹の中 笠原 祐子
大夕立言ひそびれたる別れ時 鏡山千恵子
にんげんの体でこぼこ玉の汗 加藤 修
球音の上野の森や獺祭忌 加藤 恵介
ひぐらしの鐘に唱和し善光寺 亀田 正則
夏の朝照る山肌や陰る肌 唐沢 冬朱
稲の花みつめるばかり訃音受け 北澤 一伯
うたた寝や白南風に乗りフィンランド 木部 玲子
チロルダンス床ふみ鳴らす涼しさよ 隈本はるこ
検診後白蓮見たく遠回り 来嶋 清子
迎へ火の意味知らぬままはしやぐ子ら 黒岩 清女
中秋や夜空仰ぐ日多きかな 黒河内文江
天の川友の座りし星ひとつ 小池 百人
鬼灯につぼめた口で息を吹く 小林 沙織
もう一雨来るか風鈴けたたまし 小林 雅子
秋の水心底までも映し出す 小松 葵
髪洗ふ髪の薄さをしらぬまま 阪井 忠太
二の丸や狐の剃刀影深し 佐々木終吉
秋の朝あたり静かに時過ぎぬ 佐々木美智子
朝顔やけんぱ遊びの名残りあり 佐藤かずえ
明日開く朝顔の数たしかめる 佐藤 幸子
山掠め上がる花火の端を見る 三溝 恵子
本心はつひに明かさずかき氷 島 織布
爪先を揃へ見上ぐる花火かな 島谷 操
散り花に勝る咲き花百日紅 清水佳壽美
木洩れ日にしばし微睡む秋うらら 白鳥はくとう
出番待つ猿田彦役まだ半裸 白濱 武子
少年の膝に擦り傷かぶと虫 鈴木 淳子
夕顔や格子の奥に子守歌 鈴木 照明
いかづちの空を平して過ぎゆけり 杉本アツ子
処暑の朝父の字ありし句帖かな 角 佐穂子
こそばゆき父の頰擦り夏の雲 住山 春人
クレヨンの青ばかり減る夏休み 末永 恵子
鉄線花回り回つて花咲かす 曽谷 晴子
老鶯の声の太さに驚きぬ 竹本 治美
のうぜんの地に落ち色を失はず 田中 寿徳
鎮魂の我も語り部終戦日 田中丸真智子
絵日記と一緒に泊る夏休み 多丸 朝子
糠床の機嫌むつかし胡瓜漬 近松 光栄
蠅取紙旧道沿ひの乾物屋 塚本 一夫
新涼の風にまかせて旅に立つ 津田 卓
つまべにの爆ぜて華甲を惜しみけり 坪井 研治
点在の漁火やがて帯となる 徳永 和美
かなかなに彼岸を思ふ夕散歩 戸田 礼子
火取虫毒婦のやうな目付きして 富岡 霧中
泳ぐもの止まつて見ゆる油照 中島 雄一
秋高し国衙の倉に古代米 中村 寿祥
夕立や傘を両手に父を待つ 中村 紘子
打水の風少しくる町屋かな 南藤 和義
腹ばいて撮る綿菅に至仏山 萩野 清司
境内に目立たぬ謂れ禅寺柿 橋本 行雄
風鈴を耳に棲ませてうたたねす 長谷川千何子
疵一つ無きと言ふ空夏祭 花上 佐都
葭簀立て独りの起居流人めく 原田さがみ
空蟬の縋り付きをる下乗札 播广 義春
梅雨明けて湧く雲力みなぎれる 藤田 孝俊
歓声の田を渡り来る運動会 藤森 英雄
ゆるゆると小母の手を引く盆の寺 保谷 政孝
啄木鳥や木立はるかに浅間山 堀いちろう
新豆腐今宵は箸も改めて 堀江 美州
末法の世に深まらぬ午睡かな 堀切 克洋
鳥籠の鳥確かむる昼寝覚 本庄 康代
山荒れて鹿鳴く牧となりにけり 松崎 正
柏手のことさら響く留守の宮 松田 茂
芭蕉葉に雨打つ音の堅きかな 松村 郁子
冷奴茜に染まる夕餉かな みずたにまさる
種茄子の産み月ほどの太鼓腹 宮内 孝子
草茂るもう見えている次の駅 宮本 龍子
せせらぎの流れのままに秋の蛇 森濱 直之
新しき風鈴のあり下宿先 家治 祥夫
湯屋帰り浴衣の襟も広々と 安田 芳雄
教会の木椅子の重さ秋暑し 矢野春行士
願ひ事笹に重たき星祭 山下 美佐
海の香を畳みしままの砂日傘 山田 礁
昼寝覚め記憶いびつに夢辿る 山田 鯉公
いつしかに幼なに戻り天花粉 和歌山要子



星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
面差しを父に重ねるパナマ帽 中野 智子
一昔前の男達は帽子を被っていたものだ。作者の父上も被っていたのであろう。私の父もそうだった。うっすらとポマードの匂いがしていたものだ。冬は中折帽、夏はパナ
マ帽。パナマ帽の男の面差しに父の面影をふと感じたのである。そこから父と遊んだこと、あるいは叱られたことなどの思い出が湧き上る。「父に重ねる」でポンと切って「パナマ帽」を配合したところは技倆の高さ。同時出句の〈立葵上まで咲けば子の帰る〉〈形見分け遅々と進まず遠花火〉なども人事の機微に触れた独自の世界である。 |
デザートの皿のうへなる遠花火 こしだまほ
遠花火との取合せは思い出を絡めた予定調和の句になりがちだが、この句は固定観念を脱して新鮮である。皿の上の盛り合せも花火のようであるかもしれない。微妙な呼応があるのだ。同時出句の〈ビーチボール近づくほどに離れけり〉もよく「物」を見て、出色。片仮名使いの巧者。
|
座蒲団の上へ来てゐる夜の秋 谷岡 健彦
| 「夜の秋」の季語は、原石鼎の〈粥すする杣の胃の腑や夜の秋〉を、高浜虚子が「夏」と定めたことに始まる。その後、青木月斗が反対するなどの経緯があった。この句、そのような極めて微妙な季感をよく捉えている。この発想は熟考しても出てくるものではない。鋭敏な感性の賜物。 |
とほくなる音心地よき昼寝かな 伊藤 政三
| 解る。解る。実感だ。私ごとだが出勤の準備を終えて時計を見て30分程余裕があると座椅子に凭れ掛る。ふとテレビの音や犬の遠吠えなどがだんだん遠離ってゆく・・幸せな時間だ。同時出句の〈生返事ただ繰り返す昼寝かな〉も昼寝の状況をよく描き出していて実感がある。 |
盆の雨仏の父母に傘をさす 内山 寿子
やさしさに溢れた句である。盆の墓参に生憎の雨。作者は父母の墓に傘を差しかけて、来し方のことなどを語りかけるのであろう。私ごとだが年と共に死者の存在が身近になってくるように思う。命終を意識する年代に入ったということであろうか。このような句に親しみを持つ。
|
団扇みな一瞬止まる土俵ぎは 大河内 史
うまい句である。相撲と言わず、夏場所と言わず、夏の大相撲の大一番の極り手の瞬間を完璧に捉えたのである。客席の団扇や扇子の動きがピタリと止まった。うっちゃりか。読後、そのあとの歓声が聞こえてきそうである。
|
遠雷や木彫りの象にガラスの眼 鈴木 廣美
動詞を使わないで「物」だけで勝負した句。インド土産の象の置物か。日頃は棚の中で忘れ去られているのであろうが、遠雷に触発されてふと見上げると、象の目にはめられたガラスの目が光った。何でもない置物がにわかに生気を帯びて存在感を出したのであろう。微妙な心象の変化が表出されているようだ。
|
裸子を錦江湾に放ちをり 柊原 洋征
| 錦江湾は鹿児島の大隅半島と薩摩半島に囲まれた湾。正面に桜島の噴煙が見える。その海浜での海水浴である。「裸子を放つ」は省略の効いたうまい表現である。そして錦江湾の固有名詞が何とも雄大である。読者にはおのずから西郷隆盛など維新の志士たちの幼年時代の姿などが浮かんでくる。そこが固有名詞の凄味で、例えば有明湾、東京湾、仙台湾などと入れ替えても興趣は無い。 |
でこぼこの薬缶がひとつ滝行場 山田 康教
「でこぼこ」という俗な言葉が生きた句である。かって和歌などでは使えなかった言葉で、俳句という表現方法で市井の俗語が生きてくるのだが、そういう原点がこういう句だったのだと思う。滝行場の簡素な休憩所にある使い古した大きな薬缶。そうしたところへ注目するのが俳諧の目
である。そこにきっちりと焦点が絞り込まれているのである。 |
絵日記と一緒に泊る夏休み 多丸 朝子
この句の眼目は何といっても「一緒に泊る」の措辞。普通に詠めば「絵日記を鞄に」位にとどまるのであろう。一緒にと言ったことで、子供にとって極めて大切な存在ということになる。自分と絵日記帳が並列の関係になるのだが、そこが俳諧の妙。並列の不均衡が微笑を誘うのだ。
|
その他印象深かった句を次に
青萩のすみずみにある朝日かな 西原 舞
ペン皿に異国のコイン夏の果 堀内 清瀬
墓洗ふ生涯島を出ぬくらし 高橋アケミ
焚き殻の渦そのままに蚊遣香 吉沢美佐枝
父来たるらし玄関に今年酒 松崎 逍遊
夕立や傘を両手に父を待つ 中村 紘子
苦瓜の蔓のわがまま妻のわがまま 大野 里詩
釣り船の渡り終へたる月の幅 岩崎 由紀
脳味噌を妻と貸し借り夏を越す 今村八十吉


2011/11/11 撮影 TOKYO 藤袴




|

![]() 11月号 2011年
11月号 2011年