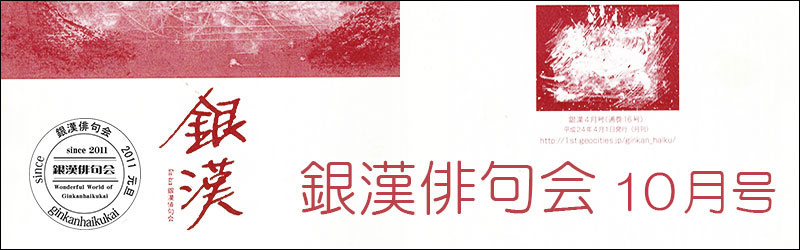伊藤伊那男作品
兜虫
梅雨鴉鳴き雨脚を繁くする
冷し汁昼餉といふもあつけなく
飛ぶまでの間合いながなが兜虫
夏帽を預つてゐる辻地蔵
牽牛のもたもたとして雨催
雨粒のありあり見ゆる夕立かな
鮎簗へ大きくしなふ渡し板
くちなはを打ち損なつてより怖し



今月の目次
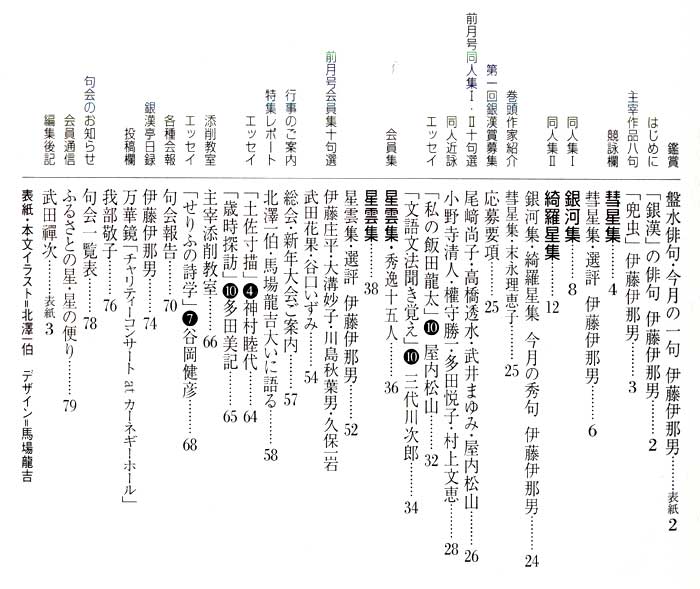

銀漢俳句会・10月号


銀漢の俳句
伊藤伊那男
不便を楽しむ時代に
「俳句」平成14年6月号が手許にある。創刊50周年記念号で「10年後の俳句」と題した特集があった。その中で私がアンケートに答えている。その10年後が近づいたので一部を採録してみる。
――10年後には結社はどうなるでしょうか、あるいはどうなるべきでしょうか。また句会等は?
俳句は「座の文芸」という特殊性をもつ。この固有の性格を失ったとしたら俳句は一気に衰退の道をたどることになろう。こころざしを同じくする連中の絆の中から思わぬ力を発揮できるのである。そのエネルギーの高まりが大切で、そこに結社の存在意義、必要性がある。特に自分より力の上の作家と鎬を削合い高め合うことができるのも結社という土俵があってこそのことである。
俳句は自分一人でできる文芸ではない。仲間と揉み合う座の力が大切である。そうした意味で指導者の存在は極めて大きく、10年後も結社制度は厳然として残るものと思っている。
――10年後には有季定型はどうなるでしょうか、あるいはどうなるべきでしょうか。また、仮名遣い等は?
特に戦後の(中略)旧仮名遣いについては学校教育でまったく教えなくなって半世紀以上過ぎたのであるから、現代仮名遣いとの併用を許容せざるを得ないであろう。ただし茶人が茶室で湯を沸かすのに電気やガスを使うのではなく、わざわざ炭を使うように、旧仮名という不便を楽しみたい人々が厳然として残るのである。
――10年後の俳句について総合的に考えること、そして現在ご自分が心掛けていることを記してください。
インターネットの普及で遥かな距離をへだてた人との句会が始まっている。今後もっと盛んになるであろう。が、すべてがそうなるわけではない。あくまでも補助手段。冒頭で述べたように人は対面することが大切。句会は一期一会の集いである。また座の文芸であると同時に個の文芸でもある。あざなえる縄のごとく衆と個で編み上げてゆくのが俳句である。座の水準を高めるのは個のこころざしの高さである。参加する各々が心と技術を練磨しなくてはならない。そうでないと座の中心に不協和音が生じる。幅広くかつ深いまなざしで自己の心と対象物を見詰めてゆきたい。俳句はいのちを詠む文学だから。
|



盤水俳句・今月の一句
★ 簗番が高嶺の星を褒めあへる 皆川盤水

彗星集作品抄
伊藤伊那男選
晩年の明け暮れ長し百日紅 多田悦子
手拍子で幽霊を呼ぶ夏芝居 津田卓
冷素麺居の腑を川にしてしまふ 大野里詩
カーテンよからめとれるかこの夏を 橋本泰
虫売りの闘ふ虫を引き離す 高橋透水
絵扇をたためば縮む大首絵 山田康教
遊船や津波の話題避けられず 矢野春行士
父母を山河に偲ぶ帰省かな 唐沢静男
ペン立てに隙間なかりし明易き 隈本はるこ
日傘より声のはみだす立話 中野智子
蛍籠まだ恋知らぬ子を灯す 屋内松山
夜遊びの証きらきらなめくぢり 宮内孝子
青萩のすみずみに日を捉へをり 西原舞
国敗るる日もひまはりの上を向く 谷口いづみ
晩年の父の中折れ麦こがし 五十嵐京子
絵扇の写楽の風をもらひけり 保谷政孝
夏草に廃線といふ記憶かな 飯田康酔
天麩羅の油注ぎ足す西日中 小野寺清人
青葦に夕風の湧く渡船跡 多田美記
玄関に白靴昭和の客が来て 中村孝哲
彗星集 選評 伊藤伊那男
★ 晩年の明け暮れ長し百日紅 多田悦子
俳句の上では様々な論議があるが、「取合せ」の辞書的意味は「調和するように配合すること」である。芭蕉の言うよそ「題号(季語)と余所」のものとの関係である。
その関係が近すぎても遠くてもいけない。
調和がとれているかどうか。ただしその調和も人の感性で違いがあるので選句に多様性が生じることとなる、ということであろう。さてこの句、私は見事な調和であると思う。
百日紅というだけに花期が長い。その時期はやりきれない程の暑さ。見上げれば衰えることなく百日紅は咲き続けている----。他の植物をあれこれ入れ替えてみても百日紅にはかなわないようだ。
(作者の名を聞いて 「まだ晩年ではなかろう!」) |
★ 手拍子で幽霊を呼ぶ夏芝居 津田 卓
| 夏芝居――暑い盛りで観客の入りが悪いので、中心の役者も休むことが多く、若手が出演する機会が多かった、とある。小屋も茹だっているし、芸も稚拙なので、客も半分やけ気味で、
幽霊の出る大事な場面にも「早く、早く!」などと手拍子が出たのであろうか。夏芝居のおかしみ。 |
★ 冷素麺居の腑を川にしてしまふ 大野里詩
| 先程取合せのことを言ったが、この句は「一物仕立(いちぶつしたて)の句である。一句一章とも言い、一つの事柄だけを読み切ることである。∧鶏頭の十四五本もありぬべし
子規∨ ∧冬菊のまとふはおのがひかりのみ 秋桜子∨などがそうである。季語と他の措辞が不離の関係にある。この句「胃の腑を川にしてしまふ」――何ともうまい表現である。目には見えないけれど、
きっと身体の中はそんなふうになっているのであろう。楽しませて貰った句。 |
★ カーテンよからめとれるかこの夏を 橋本 泰
| 俳句というよりも、西洋詩的発想と表現の句といえよう。カーテンに呼びかけているのだ。この夏をそのレースでからめとれるか?と。自由で伸び伸びとした発想である。 |
★ 虫売りの闘ふ虫を引き離す 高橋透水
| この虫は兜虫なのであろう。角を突き合わせている最中なのだが、客から「それを」と指ささると、虫売りは無造作に引き離す。虫はまだ戦っているので足掻くのであろうが
、お構いなしだ。そのギャップに作者は詩的興感を得たのであろう。事実を写生して、生き物の哀感を伝える。 |
★ 絵扇をたためば縮む大首絵 山田康教
| 「大首絵」は上半身を描いた浮世絵の人物画を言う。美人画と役者絵がある。この句の場合はどちらか?なんとなく東州斉写楽のあの目を剥いた役者絵が合いそうな気がする。
たたまれる様子を「縮む」と捉えたのが手柄だ。 |
★ 遊船や津波の話題避けられず 矢野春行士
| 先日隅田川を遡上したが、実感。「避けられず」がいい。 |
★ 父母を山河に偲ぶ帰省かな 唐沢静男
★ ペン立てに隙間なかりし明易き 隈本はるこ
| 寝そびれたのか、もう明易。垂直のペンとの取合せの妙。 |
★ 日傘より声のはみだす立話 中野智子
| 立話の好きな作者(星雲集でも取った)。はみだすが良い。 |
★ 蛍籠まだ恋知らぬ子を灯す 屋内松山
★ 夜遊びの証きらきらなめくぢり 宮内孝子
| 蛞蝓の歩みを「夜遊び」と見た手柄。寓意性も感じる。 |
★ 青萩のすみずみに日を捉へをり 西原 舞
| 「すみずみ」に夏萩の生態がある。写生の姿勢 がいい! |
★ 国敗るる日もひまはりの上を向く 谷口いづみ
| 確かにそうであろう。大震災のあとの今年は尚更の実感。 |
★ 晩年の父の中折れ麦こがし 五十嵐京子
★ 絵扇の写楽の風をもらひけり 保谷政孝
★ 夏草に廃線といふ記憶かな 飯田康酔
★ 天麩羅の油注ぎ足す西日中 小野寺清人
★ 青葦に夕風の湧く渡船跡 多田美記
| 利根川あたりの風景か。橋が架ったあとの哀愁、郷愁。 |
★ 玄関に白靴昭和の客が来て 中村孝哲
| 白靴というものも昭和の名残か。確かに––––うまい句。 |
|



銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
五合目は手のとどくほど富士詣 飯田眞理子
蟬の羽化翅のひしやげて出て来たる 池田華風
阿夫利嶺へ雲置き去りに梅雨の明け 唐沢静男
深川の炎天の堀縦横に 久保一岩
天蚕の仰向けのまま糞放つ 柴山つぐ子
錆といふ色を加へて七変化 杉阪大和
下駄箱に山蟻こぼれ御師の宿 武田花果
捕虫網立てかけてある道祖神 武田禪次
合はす手で藪蚊打ちたる五合 萩原一夫
憂き夜の闇ひるがへす熱帯魚 久重 凛子
大簗に水膨れ来て魚吐けり 松川洋酔
竹皮を脱ぎ一幹のたたずまひ 三代川次郎
捕虫網子がふるさとの空掬ふ 屋内松山



綺羅星集作品抄
伊藤伊那男・選
盆の月人生明暗繰り返し 青木志津香
捕虫網風の重さを測り行く 飯田子貢
瑠璃沼の瑠璃失せ夕立来る気配 伊藤庄平
一足に余る敷石母子草 梅沢フミ
落し文端の始末の几帳面 大溝妙子
うたた寝や蚊取線香滲む畳 大山かげもと
まづ頬に雨粒一つ夕立来る 小川夏葉
それぞれの年のいとしや虹の夕 尾﨑尚子
初蟬のこゑに残れるしめりかな 小野寺清人
郭公のこゑの曲がりし橅の森 片山一行
噴水に一日の澱を消しゆかむ 我部敬子
泥田より見上げては刈る太藺かな 神村睦代
麦酒注ぐ小言こぼれて来ぬやうに 川島秋葉男
夏帽や問はず語りに父のこと 朽木 直
名月やゆるゆるおりる九段坂 畔柳海村
羽抜鳥戒厳令の街の昼 小滝 肇
蘇鉄咲く島裏深き隠れ耶蘇 權守勝一
朝粥の熱きを夏至のつつがなく 佐々木節子
鬼灯を気長にほぐす指ぢから 笹園春雀
青柿の落ちたる夜半の目覚めかな 筱田 文
海風の吹き抜ける土間洗ひ鯒 島谷高水
安曇野の何処も瀬音麦熟るる 新谷房子
足掻くほど砂塗れなる蚯蚓かな 鈴木てる緒
夏蝶の鞘当てのごとぶつかれり 高橋透水
夏蝶の閉ぢ一枚の刃となれり 武井まゆみ
籐椅子に伏せある男の料理本 多田悦子
鰺を買ふどこの町にもある銀座 多田美記
暑き夜のパズルどうにも解けぬまま 田中敬子
蛍の夜逢ひたき人のいや遠に 谷川佐和子
江の島の端は隠るる夏座敷 谷口いづみ
血族のあらかたは亡し百日紅 中村孝哲
嘶きの馬現れず村芝居 花里洋子
持ち歩く写真の父の日なりけり 藤井綋一
夜の秋木偶の涙のさめざめと 松浦宗克
朗読の間といふしじま蚯蚓鳴く 松代展枝
成田山祗園会なればうなぎ食ぶ 無聞齋
富士の嶺ふと現はれて夏座敷 村上文惠
夕張のメロン掬へば匙に溶け 村田郁子
籐寝椅子きしむ亡父の資本論 村田重子
端居して忘れられたる木偶の坊 山元正規
佐久鯉の水跳ねとばす五月晴 吉田千絵子
夕立の叩くにまかす岬馬 脇 行雲



銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男
五合目は手のとどくほど富士詣 飯田眞理子
| 「駒込富士神社」の前書がある。江戸時代は富士講が盛んであった。ただし体力と資力が無ければ本物の富士山には登れないので、町内の神社の境内にミニチュアの富士山を造り、
陰暦六月一日に登ったのである。今も都内にその名残がある。「五合目は手のとどくほど」で、本物の富士山でないことが明瞭であり、そこが技倆。ユーモアもある。 |
錆といふ色を加へて七変化 杉阪大和
| 紫陽花は日々花の色が変化するので「七変化」の異名も持つ。俳句でもわざわざその副季語を使う人がいるが、たいがいは失敗をしているようだ。ただしこの句は
「七変化」の成功例。色に焦点を絞ったので、この季語が生きたのであり、本来の色から外れた「錆色」を加えたところが手柄である。紫陽花の朽ちた色を皆が知っているのだが、
詠めていなかったところを突いているのだ。これが発見。 |
合はす手で藪蚊打ちたる五合庵 萩原一夫
| 五合庵は良寛さんが隠棲した国上山の中腹の庵。その名は、一日を米五合で清貧に暮すという意から付けられたという。大正時代に再建しており、当時を偲ぶことができる。作者は良寛を思って手を合わせたのであろうが、その手で寄ってきた藪蚊を打ってしまったという。良寛を偲ぶその直後に殺生をしてしまった、いささかの悔い。 |
憂き夜の闇ひるがへす熱帯魚 久重凛子
| 心象の濃い句である。一人の夜の薄暗い部屋で、水槽の熱帯魚が翻へる。それを「闇をひるがへす」と捉えた。そのやや大袈裟な表現が、憂き夜の愁いを更に深めているようだ。
黒一色の基調の中に熱帯魚の極彩色が一瞬煌めく。 |
竹皮を脱ぎ一幹のたたずまひ 三代川次郎
「筍生活」という言葉があった。その意は「竹の子の皮をはぐように衣類や所持品を売って生活費に当てる暮し」。
戦争直後の流行語であった。それは余談だが、この句は竹の子が成育と共に自ら皮を脱ぎ捨てていく様子。「一幹のたたずまひ」に、竹と成った風格が漂う。品格の高さ。 |
夏帽や問はず語りに父のこと 朽木直
| 帽子の似合う作者である。父の残した帽子を見てのことか、いやいや自分で被った帽子に父の姿を重ねたのかもしれない。「問はず語り」に、父を回想する、しみじみとした味わいが籠る。そういえば昔の男は皆帽子を被っていたな。 |
夏蝶の閉ぢ一枚の刃となれり 武井まゆみ
| 「蝶」は春の季語。「夏蝶」と言うからには、それなりの夏蝶の特徴が出ていなければならない。夏蝶は多くの場合、揚羽蝶など大型で、羽ばたきも力強いものだ。
その様子をこの句では羽を閉ぢると「一枚の刃」となるという比喩で完成させた。力強い夏蝶の生態を捉えた秀逸。 |
江ノ島の端は隠るる夏座敷 谷口いづみ
| 鎌倉の七里ヶ浜か、鎌倉山あたりからの風景であろうか。江ノ島が見える。ただしその端は前面の何かにさまたげられて見えないという。そのいささかの瑕瑾がこの句の取柄であり、発見である。夏座敷の座りが堂々としている。 |
籐寝椅子きしむ亡父の資本論 村田重子
| 父の代から使われている籐寝椅子。使うたび、軋むたびに父のことをあれこれと思い出すのであろう。くつろいでいた時も資本論を読んでいた父。その資本論も脇に置いたままなのであろう。
亡父の人柄や生きざまも彷彿としてくるようだ。何よりも父への思慕の情に貫かれた点がよい。 |
端居して忘れられたる木偶の坊 山元正規
自画像なのであろうか。端居の季語では類例のない面白い仕立てである。最初のうちは家族からあれこれと声をかけられたりしていたのだろうが、次第に見捨てられていく。
自分は「木偶の坊」だと思う、男の悲哀だ。
|
その他印象深かった作品。
蟬の羽化翅のひしやげて出て来たる 池田華風
捕虫網子がふるさとの空掬ふ 屋内松山
捕虫網風の重さを測り行く 飯田子貢
落し文端の始末の几帳面 大溝妙子
初蟬のこゑに残れるしめりかな 小野寺清人
噴水に一日の澱を消しゆかむ 我部敬子
麦酒注ぐ小言こぼれて来ぬやうに 川島秋葉男
足掻くほど砂塗れなる蚯蚓かな 鈴木てる緒
夕張のメロン掬へば匙に溶け 村田郁子
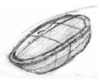


星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
捕虫網まづ家中を駆け巡る 柊原 洋征
山羊の仔のはね脚たかき雲の峰 隈本 はるこ
帰省子の胸にたためり母の老い 内山 寿子
両国の水の匂ひの釣忍 加藤 恵介
渓流のひびきに育つ青胡桃 滝沢 咲秀
日盛の影の動かぬ立話 中野 智子
摩天楼見上げつつ食ふパセリかな 谷岡 健彦
また一つ道具を増やし山開 こしだ まほ
国出でし父母の小さき墓洗ふ 中村 寿祥
石段の影につまづく終戦忌 松崎 逍遊
冷奴部下の悩みの根深くて 堀江 美州
パレットに絵の具残して夏終る 藤森 英雄
終戦日座敷の写真磨きをり 松崎 正
団欒の中切られたる西瓜かな 森濱 直之
ふんばつて風に吹かるる子蟷螂 大木 邦絵
日めくりの今日で半分山開き 相田 惠子
靴底に道路貼りつく酷暑かな 秋元 孝之
さくらんぼ粒ごとに日をとどめけり 穴田 ひろし
向日葵の照るにまかせて雲流る 荒木 万寿
路地裏の夜風が攫ふ祭笛 有賀 稲香
短夜や小声で急かす旅の宿 有澤 志峯
効きすぎる冷し中華の洋芥子 飯田 康酔
隠沼に日の斑風の斑みづすまし 五十嵐 京子
久久に見えて皓皓夏至の月 石垣 辰生
庭すみのねぢ花つみて卓上へ 石川 真砂江
万緑の底に眩しき流れ在り 市毛 唯朗
日除出す店の主の生欠伸 伊藤 政三
伊予簾ふるさとの香の座敷かな 今村 八十吉
兜虫飛んで来る間の長きこと 岩崎 由紀
風鈴のまた黙り込む真昼かな 上田 裕
盆の月徐徐に輝く海の上 植村 友子
穂芒の風任せなる伸び縮み 上森 敬子
山笠や洗濯籠に水法被 榎本 陽子
父の日の子の直球の手に重し 大河内 史
またひとつこぼす実梅のはかり売り 大西 真一
泉湧く国語辞典は言葉の森 大野 里詩
掃へどもどこかにひとつ藪虱 大野田 好記
合歓の花入日とともに葉を閉ぢる 岡村 妃呂子
庭番の如くに蟇の蹲る 小坂 誠子
夕立に煙る山並遠く見る 尾崎 幹
父の日に帰宅せし子も父の顔 鏡山 千恵子
風涼し九品の弥陀を映す池 笠原 祐子
畔道に足をとられつ蛍狩 桂 説子
向日葵は青空へ押す太鼓判 加藤 修
新茶ゆへ急須を選ぶ朝餉かな 亀田 正則
露座仏の横顔淋し青葉冷 唐沢 冬朱
いなたまが田を撃ちおろしつつ動く 北澤 一伯
訝しく見られて逸らすサングラス 木部 玲子
父の日やスリッパ届ける息子をり 来嶋 清子
葭簀越し川風渡る夕餉時 黒岩 清女
雷を遠くに聞きて母眠る 黒河内文江
払へども吾になつきて秋の蠅 小池 百人
卓袱台に祖父のアルバム終戦日 小林 沙織
里便り夢にも聴こゆ祭笛 小林 雅子
送り火を焚かずに父を留めおく 小松 葵
静寂を包みて放す夏の朝 阪井 忠太
夏の蝶始発電車に迷ひ込む 佐々木 終吉
新緑や錦帯橋の人の波 佐々木 美智子
バジルの香出勤まへの夏の朝 佐藤 かずえ
逝きし人の名を新聞に梅雨じめり 佐藤 幸子
竹煮草真昼の村に音絶えて 三溝 恵子
オペラグラス夏手袋の中にかな 島 織布
ねぢ花やつぼみしぼみもねぢのうち 島谷 操
一匹の蠅にふためく路地暮らし 清水 佳壽美
ドロップの缶のぞき見る残暑かな 白鳥 はくとう
雨後のごとこぞりて水を撒きし町 白濱 武子
通夜の日の鴨居に残る夏帽子 鈴木 淳子
万緑の風吹き抜けて神楽殿 鈴木 廣美
白南風を孕みカーテン走りだす 杉本 アツ子
小さき口更に小さく杏食ぶ 角 佐穂子
父の背追ひかける子の夕焼ける 住山 春人
起し絵の夜の大阪御堂筋 末永 理恵子
雲見てる梅雨の晴れ間の露天風呂 曽谷 晴子
白百合や母清貧に生きられし 高橋 アケミ
明易の雨戸繰る音ふるさとに 武田 真理子
端居して運命線を見てをりぬ 竹本 治美
あれこれの思考中断冷奴 田中 寿徳
ひまはりや順番待ちのすべり台 多丸 朝子
各々にめでる言葉や虹の橋 近松 光栄
一樹いま焼き尽くさんと油蟬 塚本 一夫
十薬の匂へば雨の匂ひとも 津田 卓
向日葵を好みし母の愛でし庭 土屋 佳子
向日葵や天動説の妻の留守 坪井 研治
月桃の香りも近し毛遊び 徳永 和美
夏椿土にこぼれて母の忌に 戸田 礼子
息をすることさへ辛き酷暑かな 富岡 霧中
初蟬に背中押さるる庭仕事 中川 孝司
口中に微熱生まるる草いきれ 中島 雄一
もどかしき音を鳴らせてラムネ飲む 中村 紘子
雲海の上に開拓村のあり 南藤 和義
喉鳴らし乳飲む稚の玉の汗 西原 舞
遠浅の砂に引きずる二連鱚 萩野 清司
雨の糸蛍の糸を遠ざける 橋本 泰
勝ち進む球児の親の日焼け止め 橋本 行雄
とりたてて話すことなし冷やつこ 長谷川 千何子
蠅一匹捕れば又来る蠅一匹 花上 佐都
裏返る葉裏の白き晩夏かな 原田 さがみ
柱絵の如来の紅や勝鬘会 播广 義春
山梔子の日を浴びぬまま褪る花 藤田 孝俊
庭草のよろこびさうな水を打つ 保谷 政孝
歯磨のチューブあたらし小鳥来る 堀 いちろう
田疲れを湯治の宿へかんこ鳥 堀内 清瀬
蟇鳴くやよれたるジャージ着て 堀切 克洋
すぐ直る子供の機嫌さくらんぼ 本庄 康代
分教場課外授業の蝗捕り 松田 茂
片蔭を尺とりながら歩きけり 松村 郁子
日に灼けし二の腕さすり竿じまひ みずたに まさる
夏の夜の夢や白紙で出すテスト 宮内 孝子
祈りにも似て伸びゆきし雲の峰 宮本 龍子
原爆忌誰が折りしか千羽鶴 家治 祥夫
掛声の間合ひの悪し夏芝居 安田 芳雄
バス停は汗の噴き出る社交場 矢野 春行士
彦星を雲居に探す女かな 山下 美佐
粗漉しにいぐね抜け来る青嵐 山田 礁
甲斐駒を屏風に見立て峡青田 山田 康教
横雲の離るる浅間草いきれ 山田 鯉公
十薬や十指に余る糖衣錠 吉沢 美佐枝
富士山へ登山道具の膨らめり 吉田 葉子
鎌倉は人の大波七変化 和歌山 要子



星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
捕虫網まづ家中を駆け巡る 柊原洋征
思い出すなあ、この光景。真新しい網を買って貰って嬉しさのあまり、家の中で振り回すのだ。昆虫を捕る練習をして姉や兄の頭に被せたり、
仕舞は障子に穴を空けて母に叱られて終り。ああ、懐しい。「まづ家中を」が味わいである。素直に伸び伸びと詠んでおり、無理も無駄もない。
|
山羊の仔のはね脚たかき雲の峰 隈本 はるこ
| 一読すがすがしい句である。中七の「はね脚高き」の躍動感が絶妙で、下五の「雲の峰」への展開がまたよい。遠近法が効いて
山羊の子が雲の峰の高さに跳ね上るような楽しさがある。おおらかに動物の生命力を捉えた。 |
両国の水の匂ひの釣忍 加藤恵介
| 固有名詞の使い方は難しいものだ。季語にも匹敵するインパクトを持つのが固有名詞であるから十分な注意が必要である。結社に
よっては地名俳句を忌避するところもあると聞く。私は容認派だし、自分でもよく使う。それだけに尚更厳しい目で見ていきたいと思うのだ。さてこの句の
両国の地名はかなりよい線に達しているようだ。武蔵、下総の両国の境、隅田川のほとりである。それだけに水の匂いがあり、また釣忍のある下町がある
。そうした生活感が両国の地名を得て読み手の眼前にありありと現出するのだ。 |
日盛の影の動かぬ立話 中野智子
| 男にはこういうことはなさそうだ。女性は話好きが多い。日傘を差したまま話し込んでいる。作者が用事を済ませて戻ると
、同じ姿勢のまま話は続いている。この日盛りのなかで!そんな驚きが伝わってくる。「影の動かぬ」が凄い。でも作者の名を知ると・・自画像かな、とも思う。 |
摩天楼見上げつつ食ふパセリかな 谷岡健彦
当然あの鷹羽狩行の〈摩天楼より新緑がパセリほど〉が根底にある、本歌取りの句である。狩行句は出張先のニューヨークで着想を得
た海外詠の先駆的作品。狩行句は錯覚しそうだが、季語は新緑。鳥瞰した公園の新緑がサンドウイッチの皿に添えたパセリのようだという見立て。一方谷岡句はパセリが季語で、逆に摩天楼を仰ぎ見ている構図。
パロディーであることを意識した余裕のある句で、これも俳句の一形式。ただしこればかりでは困る。
|
国出でし父母の小さき墓洗ふ 中村寿祥
| 戦後の日本の生活環境、家族関係は激変を重ねた。大都市への一局集中で地方は空洞化していく。都会に職を得て都会で死ぬ。この句も都会を生活の場とし
て都会の墓に眠る父母と、都会に住む作者がいる。「小さき墓」に、恐らくそれほど出世したわけでもなさそうな、市井に生きた両親の像が浮かび上る。この作者らしい、謙虚でほのぼのとした温かさが滲む句となった。 |
冷奴部下の悩みの根深くて 堀江美州
| 人事の難しさの伝わる句である。科学優先の世では、尚
更深まる人の悩み。そんな部下の様子を察して居酒屋にで
も誘ったのであろうか。とりあえず注文した冷奴にはまだ
手付かずだ。豆腐の四角な形、白さ、冷たさが部下の悩み
を象徴しているかのようにも思えてくる。季語の選択に暗
喩が籠められているようである。 |
団欒の中切られたる西瓜かな 森濱直之
最近の若手俳人の句を見ると、目新しいことを性急に追求する感じを受けてしまう。俳句は常に進化していかなくてはならないと思っているようだ。何が進化であるかは難しいところで、結局のところ言葉のレトリックに終ることが多いようだ。私は冒頭のような句を支持する。大西瓜を真中にした人の喜びが素直に無理なく描出されているのだ。生活実感や生かされていることへの感謝の気持ちが如実。
|
月桃の香りも近し毛遊び 徳永和美
毛遊び?――広辞苑を繰ると「沖縄の村々で行われていた男女の野外遊び。夜なべ仕事のあと、もう(野原)で円陣をつくり歌い踊った」とある。
筑波山の嬥歌と似たもののようだ。今はビーチパーティーとして残っているという。
月桃の「香りも近し」に臨場感がある。沖縄好きの作者。 |
その他印象深かった句を次に
もどかしき音を鳴らせてラムネ飲む 中村紘子
向日葵や天動説の妻の留守 坪井研治
通夜の日の鴨居に残る夏帽子 鈴木淳子
向日葵は青空へ押す太鼓判 加藤修
白南風を孕みカーテン走りだす 杉本アツ子
風鈴のまた黙り込む真昼かな 上田裕
バス停は汗の噴き出る社交場 矢野春行士
ひまはりや順番待ちのすべり台 多丸 朝子
端居して運命線を見てをりぬ 竹本治美
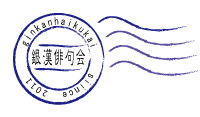
|

2011/10/9 撮影 TOKYO 金木犀




|

![]() 10月号 2011年
10月号 2011年