

HOME 句会案内 バックナンバー
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月号
![]() 10月号 2013年
10月号 2013年
| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 銀漢日録 今月の写真 |
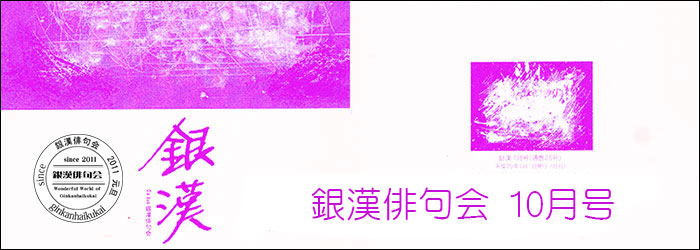

伊藤伊那男作品
花火 伊藤伊那男
嵯峨野なる水を閉ぢこめ冷奴 造り滝きのふの水をまた落す また向ふ側に落ちたるハンモック その端をがじゆまるに結ひハンモック 行水をして消炭のやうに寝る 百合活ける佳人支へる心地して 薬缶ごと冷す麦茶や納経所 山国に山の残れる花火あと   今月の目次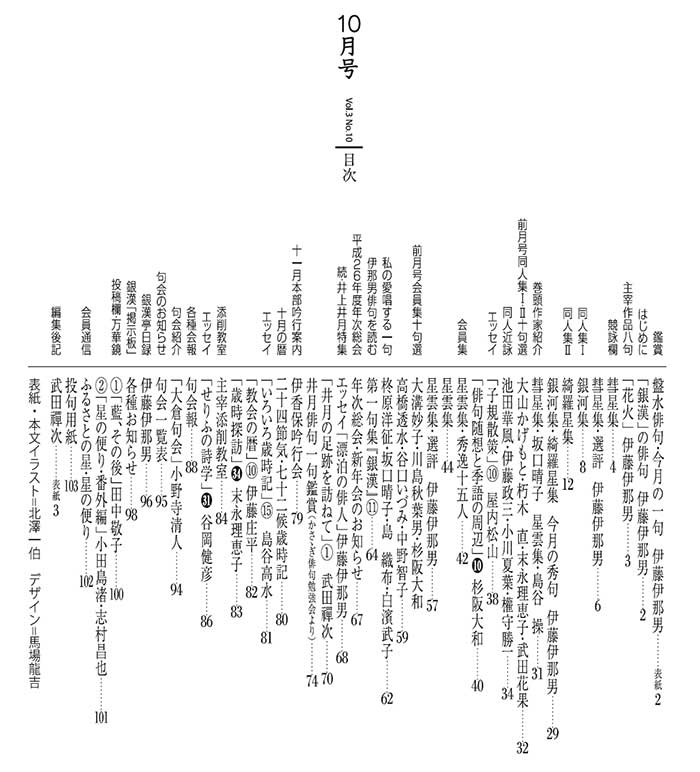  銀漢俳句会・10月号 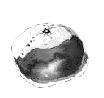  銀漢の俳句伊藤伊那男
|
| 伊勢神宮、お白石持行事 8月1日昼、近鉄宇治山田駅に武田禪次夫妻、朝妻力さんと落合い、二見浦へ向かった。伊勢神宮のお白石持行事は、その前に二見興玉神社の無垢塩草の幣で禊を受ける「浜参宮」をすませるのが慣わしだからである。 8月2日早朝、 私達はその奉献車を、お払い町を通って宇治橋まで運ぶ、一番華やかな最後の仕上げの場面に参加させていただく僥倖に恵まれたのである。地元民でない我々は「特別神領民」と呼ばれる。揃いの法被を着て、木遣唄を合図に「縁弥、エンヤ」の掛声に合わせて白綱を曳く。お払い町の商店街の方々が声を掛けてくれ、茶の接待もある。曳き終ったあと宇治橋を渡り、御手洗で清めた手の上の白布に一つずつお白石をいただき、内宮の新御敷地に入る。ここは二か月後の遷御のあとは天皇陛下も入ることのできない聖域となる。桧の香も匂い立つばかりの新正宮を目の当たりにして、祈りを籠めてお白石を奉献する。正宮は古代の高床式の穀物倉が原形と思われる白木造りだが、それは既にして、何とも神々しく輝いており、自ずから涙が湧き上がるのである。 西行法師が正宮の祭事を拝所から遠望して〈何ごとのおはしますかは知らねどもかたじけなさに涙こぼるる〉と詠んだが、まさにその思いを共有したのである。 鳥居、橋、全ての建物だけではなく、数千点に及ぶ宝物までの一切を二十年刻みで作り替える「御遷宮」の意味とは何か? 河合真如宮司の『伊勢神宮の智惠』によれば、 と説く。 |



| 先生の句はつくづく平明である。頭の中で言葉を搔き廻したり、欲張った表現というものが一切ない。無駄な言葉がない分、的確に対象物の本質をずばりと捉えており、読者の胸にすとんと入るのである。いつも正眼の構えで真っ向から真摯に自然を見詰めていて、軸がぶれることがない。遠野を訪ねて、雑茸を売る風景を見たのだが「燈を低くして」が眼目で、吊り下げた裸灯、覗き込む客、遠野の暗さなどが鮮明である。 (平成2年『随処』所収) |
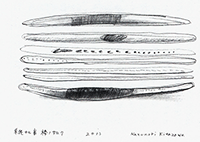

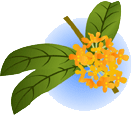


| ああ、何とも懐かしく、温かな気持にさせてくれる句である。祭の日に子供を伴って故郷へ帰ったのである。私も子供が小さかった頃、秋祭を見せたくて帰省したものだ。神社の狭い境内を筒花火を抱えた町衆が走り廻る祭で、長女を肩車に乗せていたら火の粉が私の髪の分け目に落ちた。熱いのだが、肩車の手を離して払うことも出来ず、少し火傷をしたのも思い出だ。------と、この作者、何と同郷の先輩であった!もしかしたら郷里の五十鈴神社のあの祭かも------。 |
| 蟻地獄を克明に観察した句である。私はそこまで見ていたことはないが、巣を整えるために時折顔を出して砂の傾斜などを整えるのであろうか。確かに風雨のあとなどは必要になるのであろう。その作業を「繕ひの砂」と詠み取ったのが手柄であり「飛ばしけり」の終り方もうまい。一物仕立の技法で対象物を、その行動の一部始終を過不足なく一息に詠み取った堅牢な写生句である。 |
| 今は普及しているのかも知れないが、私の小さな頃の伊那谷は丹波栗などはなく、いわゆる山栗、柴栗であった。嵐のあった翌朝、祖父と裏山に拾いに行ったことなどを思い出すが、小さな果実で食べるのが面倒なものだった。さてこの句、路線バスが止まると乗客と共に栗の花の匂いも入ってきたという。「乗り来る」と擬人化したところが面白く、里山の風景などが詠み手の胸にすとんと落る。 |
| 私の子供の頃は発泡性の飲料といえば、サイダーであった。今や様々な種類のものが販売されているが、このサイダー、激しい競争を生き抜いて今も健在である。でもさすがにあの分厚い壜と硝子玉の容器は珍しくなったようだ。句はサイダーの泡を見ると昔の思い出が湧き上ってくるというのだ。次々に上る小さく果無い泡に籠る思い出。サイダーの人気が衰えないのはそうした郷愁の飲み物だからかもしれないと思わせる句だ。 |
| 草いきれのする青野を散策していたのであろう。少し走ってみたりする。何だか自分も野生の馬(たてがみ)になったような気持がしてきて、ふと鬣があったらな------と思う。馬になるという奔放な発想を称えたい。 |
| あの動く宝石のような翡翠、水辺に張り出した木の枝に止ってじっと獲物を待ち伏せる。この句の翡翠は飽食してくつろいでいるのかもしれない。羽繕いの様子が水面にも映るという。この鳥だからこそ生きる表現である。 |
| 雷がまさに鳴る直前の空気を詠んで臨場感が出た。 |
| 仏法僧となくこの鳥だけに現し世との取り合せが生きた。 |
| 「豪雨」とは大胆に捉えたものだ。時雨に対応した機知 |
| 宿泊を拒めない登山宿だけにこんな風景となる。 |
| もう壊れる寸前なのに「自慢の」とは。俳諧味である。 |
| 夜通し看護した様子が「閉ぢぬまま」に表出している。 |
| そう、滴りにも必ず初めの一滴がある筈だ。なるほど! |
| 病院だけに「担ぎ込まれし」にほのかなおかし味が---。 |
| 美しく清らかな句である。「藍の香」がよく効いている。 |
| 私も湯殿山の道でついつい深入りした。実感の句だ。 |
| 活きのいい鰹、黒潮の色を縞目に湛えているのだ。 |
| 「十薬」という植物のありようがよく解る設定。 |



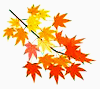


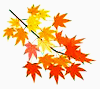

伊藤伊那男
| 私には幽かな記憶だが、茅葺屋根の父の実家では蚊帳を吊った。何か別世界に入るような不思議な気持ちになったものだ。この句の「くぐりて重き」には実際の裾の重さに加えて子供の頃のそうした情感が重なっているようだ。父ではなくやはり母なのだと思う。余談だが過日ニューギニアに行った時、ベッドはすっぽり蚊帳に包まれていて、翌朝ベットの周囲にはおびただしい虫の死骸があった。ああ------蚊帳の季語はまだまだ生きているのだな、と思った。 |
| 紫陽花は梅雨時の花。晴れの花もいいが、雨の日の花も味わいが深い。一日一日と微妙な変化があるので、同じ雨でも昨日とはもう色が違うのだ。そうした花だからこの句が生きるのであろう。 |
| 宮澤賢治の「雨にも負けず」の一節「ヒデリノトキハナミダヲナガシ サムサノナツハオロオロアルキ」を本歌取りした・である。この句の面白さは「村の賢治」――宮澤賢治その人ではなくどこの村にもいる宮澤賢治のような人――を詠んでいることだ。憂いを抱えて村中の水田を見て歩くその賢治は作者の分身なのであろうか。「歩ましむ」に切実な思いが籠っているようだ。 |
| 「たためば」があるので、最近まで羽織っていたのであろう。亡くなったあと畳んでみて、ああ------これも形見の一つになってしまった、と思う。「うすき」には単なる夏羽織の薄さだけではなく、人の世のはかなさや亡き人への深い哀惜の念が滲む。 |
| 「花火」をすっかり「花」そのものに見立てて詠み切ったところが出色である。線香花火は日本独特の、極限までいきついた繊細な花火だ。最後は真赤な玉となって終る。「雫となりて」にその様子が美しく捉えられている。「咲き終へる」花として詠み終えたのである。 |
| 箱根は東海道最大の難所、足柄越え、碓井越え、その他幾つもの変遷を経ており、今の石畳の道は江戸時代からの道である。鎌倉時代を舞台にした悲恋の「虎が雨」が箱根の固有名詞を際立たせているようだ。同時出句の〈鋭角の踵となりて飛び込めり〉にも感心した。ダイビング、高飛込みの競技の副季語で〈飛込みの途中たましひ遅れけり 中原道夫〉で一般化したが、「飛び込めり」には季語としては若干の危うさを思う。「踵」があるので解るが------。 |
| 野球の応援団であろうか。多分勝ったのであろう。応援旗を畳んでビヤホールで乾杯である。「畳みて入る」に規律正しさが窺えるが、そこをきっちりと詠んだところがいい。現代風景を切り取って巧みな句だ。私ごとだが大学一年の時であったか確か六大学野球で優勝したのだと思うが、銀座のライオンは我々学生で埋まり、大ジョッキを腕を組み合って一気に飲み干したことなどを思い出した。テーブルの上に立ち上がる者などもいたから、この句と違ってやや狼藉であった。 |
| 帰省を詠んで面白い句だ。まあ、そうなんだなと思いつつ今まで目撃していなかった句である。帰省子が戻ったことで寝息が増えたという。句からは一人ではなく、何人かの子供、もしかしたらその家族もどさどさと帰ってきたような趣を感じる。それがうるさい寝息ではなく豊かな寝息なのである。帰省子を迎えた一家のあたたかさが出ている句だ。 |
| 「半夏生」には七十二候の時候を指す場合と、植物の烏柄杓を指す場合とがある。この句は時候。まだ梅雨が明けない、実に鬱陶しい時期である。何をしても身体が重く、気も晴れない。この感覚を「つくづく重き」と言い、さて何を持ってくるのかな、と思ったら「手足かな」と少し外して軽いユーモアを漂わせている。 その他印象深かった句を次に |






| 外出から戻り脱いだ着物を衣紋竹に掛ける。まだ身体のほてりが着物に残っているのだ。それを「ほてり預けたり」と言った。「預ける」の措辞に脱帽である。上五が六音になった字余りだが、三段切れを避けるには必要な字余り。上五なので違和感は少ない。同時出句〈こゆるぎの磯の湿りや虎が雨〉〈川音やどこか濡れゐる青胡桃〉も上質の句であった。 |
| 「人間到る所青山あり」という言葉があるが、ここでいう青山とは、骨を埋める場所、墳墓の地の意味である。掲出句は本来生き物は土に還るもの、石一つあれば墓石に足るという句で、作者の死生観が根底にあるのであろう。取り合せた「草蜉蝣」は蜻蛉に似た昆虫で、透明な翅と弱々しい飛び方から、古来はかないものに例えられる。微妙な付合いのよさのある句だ。同時出句の〈たはやすくぞめき踊りの阿呆となる〉も阿波踊に知らず知らずに参加していく様子が実に巧みに、ユーモアを湛えて描かれている。 |
| 私の子供の頃は家の中で遊んだら「外で遊べ!」と叱られたものだ。あちこちに空き地や雑木林があり、日が沈むまで走り廻っていた。そんな頃を思い出させる句だ。「夏草の倒され」が具体的で景が鮮明である。子供達の嬌声、草いきれなどが読後の胸に立ちのぼる。 |
| 龍安寺の縁側にでも佇んでいるのであろうか。石と砂だけの庭で四角な塀に囲まれた空間である。その隅の方であろうか――そこを「余白」と見たのであろうが、暑さが籠っているという。石庭には禅の心が象徴されていて、思索の場所でもあるというが、この句は何だか「禅問答」に持ち込んだような面白味を持つ。その「暑さ」「余白」は作者の身の内――心理的な暑さ――と重なるのかもしれない、とも思う。 |
| 梅雨寒の頃の心細さがよく出ている句である。持病のことやこの季節の鬱屈感が、ついつい自分の手首の脈を取る行為へ動かしたということであろうか。俳句は日本の微妙な気候の変化が作らせるものなのだなということを実感させる句である。「己が」のリフレインも効果的。 |
| 「抱き合ふ」という生々しい行為なのだが、身体という中味の入っていない物干場のシャツであるところで俳諧味に持ち込んだのである。青嵐に揉み合うシャツから、生身の人間模様の寓意のようなものが滲み出てくるのが味わいだ。 |
| この半世紀で林檎の改良は目覚しいものがあった。私の子供の頃には見ただけで口中に唾が湧くような青林檎があった。多分この句は、久々に訪ねた父の郷里で青林檎を目にした瞬間、一気に色々なことを思い出したのであろう。ああ、この風の強弱、その匂いにも憶えがあるぞ、とその時代が蘇るのである。質のいい抒情に浸った句。 |
| 夏座敷と風の組合せの句はいくつも見てきたが「幅広の風」の表現は.無かったように思う。「幅広の風」――つまり座敷の障子などが取り払われて部屋一杯の風が通っているのである。何ともすがすがしく、眼力の効いた句だ。 |
| 浮人形といえば私の頃はブリキの金魚。たわいのないものだが宝物にも見えたことがあった。「浮いてこい」とはまた楽しい名前である。遊びに来た子供達が帰ってしまった。浮人形の忘れ物を残して。そんな淋しさがよく出ている句である。下五に置いたこの季語の「……来い」の終り方で、子や孫に早くまた帰って来い! と呼びかけるような作者の気持を重ねているうまさである。 |


| 子供の頃見聞きした風景や体験はこの年になっても鮮明で、折々俳句にも投影してくるものだ。私が懐かしく思いだすものの一つに、信州伊那谷の父の生家がある。昭和30年前後のことになるが、当時は集落全部が茅葺屋根の家であった。家の裏は傾斜畑になっていて桑が栽培されていた。その畑の下から清水が湧いており、飲料水はその清水を家に曳き込んで使っていた。まだ水道はなかったのである。 家に入るとかなり広い三和土があり、片隅に五衛門風呂が据えてある。水道がないので風呂水は横の川から馬穴に汲んで何度も何度も運んで満たし、薪で焚く。大変な作業を伴うので何日かおきにしか風呂は焚かない。当然のことだが電気製品などというものは何一つなく、かろうじて家の中には裸電球がいくつかある程度で、それも最小限の明るさであった。家に上がると広い板の間で、隅に囲炉裏が切ってある。裏山で集めた粗朶や薪を焚くが、私には煙たい場所であった。 祖父は織物業と養蚕業が主業で、夏は板間全部が養蚕場になった。三段ほどに組んだ蚕棚があり、日に幾度も桑の葉を摘んで与えた。蚕の食欲は旺盛で、昼の静寂の中、桑の葉を食べる音がひそやかながら潮騒のように聞こえてきたことを憶えている。蚕のことは「お蚕様」と呼んだ。 その頃であったか父の弟に嫁が来た。父が母の生家のある駒ヶ根市に医院を開業したので、弟に家を譲っていたのである。親戚や近所の人が集まり、庭に竈を据えて宴会の馳走を作った。日暮が迫った頃、白無垢に角隠しの嫁が到着し、家に入ると、履いてきた草履を世話役が茅葺屋根へ高々と放り上げてしまう。もう帰れないのだぞ、という意味なのであろう。 思えば父は親孝行な人で、月に1度だけ、15日が休診日という多忙な開業医の生活の中、その日は必ず私を伴って2時間ほどかけてこの家を訪ねた。テレビが普及しはじめた頃も、まず、自分の家ではなく生家に入れた。後から聞いた話だが、いつの頃からか祖父母と嫁の折合いが悪くなり、祖父は私にこの家を継がせたいと言ってきたという。父が置いていく小遣いは全部私の名前で貯金にしてあったという。 祖母が死んだのは、昭和39年、祖父が死んだのは昭和41年であった。傾斜畑の上の屋敷墓に埋葬したが、火葬ではなく、棺桶に座った形で納め、穴を掘って埋めた。その頃までこの地方はまだ土葬が許されていたということであろう。墓地の横に大きな榧の木があり秋には沢山の実を落した。父はそれを拾ってきて炒って食べていた。何であんなものを、と思っていたが、父にとっては思い出の味だったのだと今にして思う。 平成六年 浮人形浮かせしままに路地暮るる
講宿の盛切り飯や鉦叩 吊し柿一夜に冷えし関ケ原 仏壇のちさき障子を貼りにけり 羽繕ふこともせはしく小鳥来る 胸に受く愛の羽根てふ軽きもの 里芋を煮てふるさとに母在す 鵙の贄枝もろともに乾びをり 運動会の小さな椅子に招かるる 桑枯れて出稼ぎ村となりにけり 木莬鳴いて義仲の山暗くする 平成七年 初筑波蓮田に風の鳴りどほし
初東風や産土神に撒く塩と酒 初電話傘寿の父の声透る 尾長の尾紙漉小屋の屋根叩く 鉛筆の木の香の甘し冬籠 春隣飴屋が飴の棒伸ばす 雲雀笛吹けば吹くほどかなしけれ 田楽の味噌辛くして父の国 剪定の枝たちまちに嵩ばれり |




 !
!


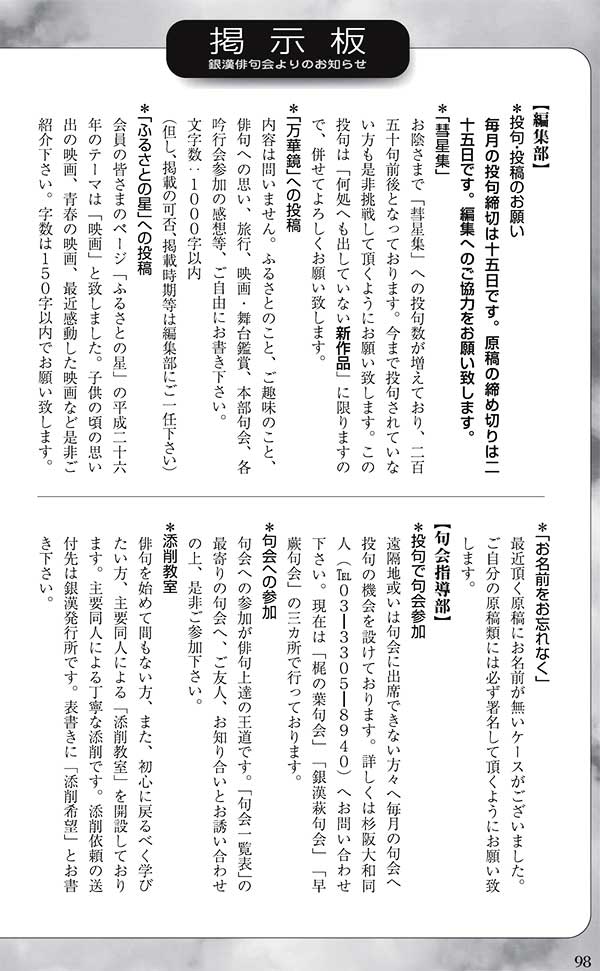
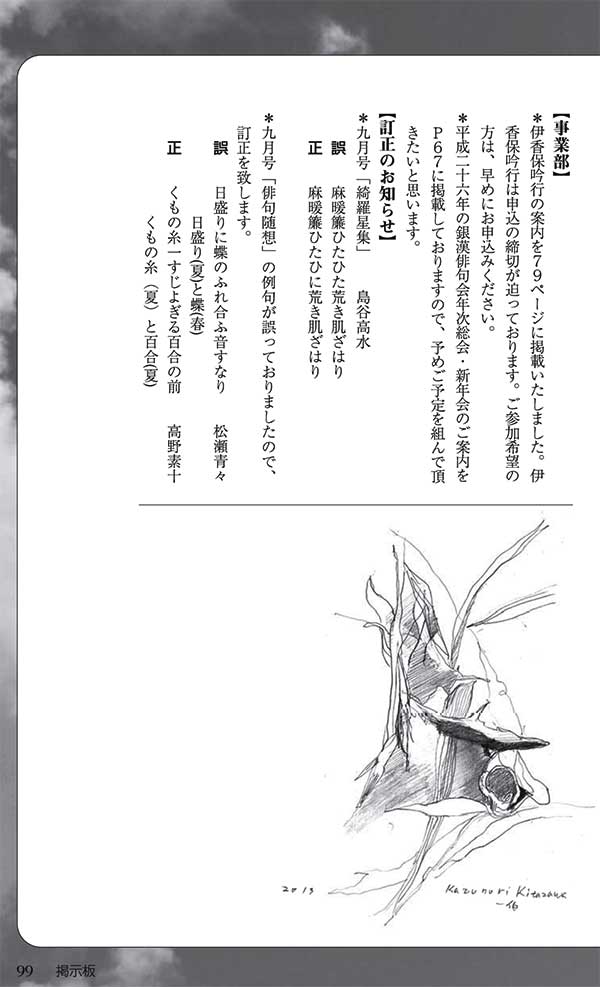




| 6月 6月14日(金) 中根さん家の掃除。特に予約客もなく、ゆっくり出勤。真砂年、健彦、小石、環……さんなど。明日、御嶽山で鍛練会にて早めに閉めることに。と、国会議員のT氏。  6月15日(土)~16日(日) 6月15日(土)~16日(日)「銀漢俳句会鍛練句会」、御岳山荘に41人集合。昼より持ち寄り10句句会。あと席題句会、5句出しを4回。翌朝、5句出し1回。あと事前投句15句の披講。11時より 武蔵御嶽神社にて太々神楽を拝見。雅楽のあとの神楽は天の岩戸の段。山の神より紅白の餅をいただく。下山して「玉川屋」へ有志27人。打上げ、最後、蕎麦。 6月17日(月) このところ俳壇の長老の逝去続く。鈴木鷹夫氏あと、星野麥丘人、山田みづえ、森田峠氏。倉橋羊村氏入院中と。店、男だけの「纏句会」に対してか、女性だけの「足手まとい」句会の集い。米国在住の桜山さんを招いての会。禪次編集長も参加。7名。真砂年、坪井さん。事業部・谷岡さんより鍛練句会分科会の選句預かる。  6月20日(木) 6月20日(木)北村皆雄監督、井上井月顕彰会の平澤副会長、宮下さん、秋の「信州伊那井月俳句大会」の件で来店。復本一郎先生の講演のあと、北村氏と小生が加わって鼎談をしたいと。そのあとの町の井月フェアへの参加要請も。広渡敬雄氏、九大の同級生と5人。「銀漢句会」あと19人来店。 発行所「野村句会」あと5人来店。久々、小島健さんが「河」編集長の鎌田さん、「や」の麻里伊、十朗さんと。「天為」元編集長・対馬康子さん、「未来図」守屋編集長、「街」編集長・竹内宗一郎さん、今日は編集長が揃ったな!ばらばらに。あっ、客は俳句関係者ばかり……。  6月22日(土) 6月22日(土)14時、「纏句会」。ニューヨークの月野ぽぽな(「海程」)、相沢文子(「ホトトギス」)、秋に渡仏する堀切克洋さんをゲストに。17人。あと、茄子と蟹あんかけ、めひかりの唐揚、握り。終って松代展枝家に。月野ぽぽなの歓迎会。「天為」の方など合計15人。終って洋酔、小石さんと新宿西口のワインバー。あとゴールデン街のひろしの店へ行くと大西真一さんが歌っている。そのあとゴールデン街をもう一軒……2時は過ぎていたか。また、やってしまった……。 6月23日(日) 九時、整体。予約の10分前に起床してすべり込む。二日酔で口きけず。午後、桃子、杏子来る。衣類の整理など。 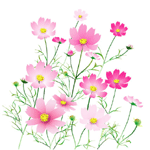 6月24日(月) 6月24日(月)8月号発送日。ずしりと重い。「湯島句会」最終会出句者108名、当日参加者何と714名!句会の前から酒を出すのは今回が初めて。店から溢れ出る。外にレジャーシートを敷く人も。ニューヨークの月野ぽぽな、伊予の片山一行さんも参加。幹事の川島秋葉男、大西真一さんにお礼の花束贈呈。お疲れさま! 6月25日(火) ひまわり館「萩句会」の選句へ。店、毎日新聞・鈴木琢磨さん他。週刊金曜日の伊達さん他。  6月26日(水) 6月26日(水)昨日も今日も昼間の激しい雨。店、カウンター「雛句会」6人。「春耕神保町句会」あとの13人。月野ぽぽなさん来週はニューヨークへ戻ると。「月の匣」水内主宰他。 8月号の原稿執筆終了。中根さん家の掃除に入ってもらう。店、清人さんの「鰹の会」18人。気仙沼港の鰹2本。烏賊焼。郷里の先輩・今井康之氏が「天為」同人の長岡剣太郎氏と。「天為発行所句会」あと日原傅氏。法政大学人間環境セミナーの日程表を届けてくれる。秋に1日講師を要請されている。 6月27日(金) 店、3ヶ月に1度の主宰仲間の「白熱句会」水内慶太、藤田直子、小山徳夫、檜山哲彦、佐怒賀正美さん。発行所「金星句会」終って9人。大阪から中島凌雲君参加。 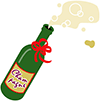 6月29日(土) 6月29日(土)月次収支作成など。午後、成城。娘一家と貸家を2軒見る。鮑の酒蒸しなど持参。シャンペンで酒盛り。村上護先生逝去の報入る。  6月30日(日) 6月30日(日)京王プラザホテル42階・高雄の間にて児玉真知子さんの第一句集『風のみち』の出版記念会。「山繭」の宮田正和主宰、角川の石井編集長とお会いする。 7月  7月1日(月) 7月1日(月)発行所「かさゝぎ」勉強会。井上井月と。あと店へ15人。「月の匣」水内慶太氏他。恒例の富士山開山日の吟行のあと10数名で寄ってくれる。村上護先生逝去で辛い中のことと推察する。中島凌雲君、フィアンセと。 7月2日(火) 名古屋の「円座」主宰武藤紀子さん。父上が野村証券京都支店長在任の1年後、私が京都配属という関係。「街」今井聖主宰、宗一郎編集長。  7月3日(水) 7月3日(水)発行所「きさらぎ句会」あと7人。「宙句会」のあと九人。2つの句会がチャンパン二本開けて私の誕生日を祝ってくれる。村上護先生通夜のあとの山田真砂年、櫂未知子、小島健、阪西敦子さん寄ってくれる。 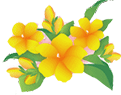 7月4日(木) 7月4日(木)12時、本行寺に村上護先生の告別式。店、「16夜句会」。「高遠句会」の加藤恵介、洋酔さん等4名の男性ゲストを呼び、14人。私のためにバースデーケーキ、花束を用意してくれる。 「大倉句会」あと店へ10人。京都土産を持って麒麟夫妻。紹介した「森庄」に泊り、居酒屋「伏見」に2日通い、「イノダコーヒー三条店」に行き、いずれも大満足と。毎日新聞の鈴木琢磨記者、出身地の大津の町興しに俳句の面で貢献したいと相談あり。東京梅雨明けと。 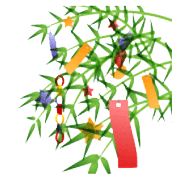 7月7日(日) 7月7日(日)七夕では珍しく快晴。64歳の誕生日。午後、「春耕同人句会」。「平成俳壇」選句選評仕上げる。  7月8日(月) 7月8日(月)国会議員T氏。秋の「信州伊那谷吟行」の下見に行ってくれた事業部・谷岡、津田、谷口さんより報告受く。 7月9日(火) 「火の会」7人。俳句仲間数名、結局一般のお客さんゼロ。トホホ……。 7月10日(水) 発行所「梶の葉句会」。選句に上る。「読む会」(一平、うさぎ、麒麟、真砂年さん)、細見綾子について、と。入沢さん北九州高専の同窓会あと7名程で寄ってくれる。客少なく……。 7月11日(木) 群馬から鈴木踏青子さん。11月の「伊香保吟行会」の件で谷岡事業部長と打合せ。あと店に寄って下さる。  7月13日(土) 7月13日(土)10時、運営委員会。13時、「銀漢本部句会」。この暑いのに52人。終って「和民」にて暑気払いの会、20数名。窪田明先生から山形のさくらんぼ到来。 |



