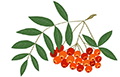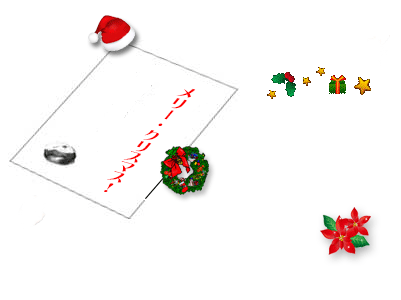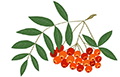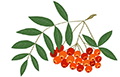銀漢の俳句
伊藤伊那男
◎入院の顛末①
銀漢俳句会の皆様にご心配を掛けている。今回の私の病気の顛末を紹介しておく。
記憶がやや不鮮明だが、八月三十一日に「(竹久)夢二忌俳句大会」の選者に呼ばれて伊香保に入った。温泉街の石段を上り、湯に浸った。その頃から、いやその前から尿の色が異様に濃かったが、身体は極めて元気にて、まあ明日には戻るだろうなどと軽く見ていたのであった。翌日は銀漢北軽井沢句会を訪ね、遅ればせながら柴山つぐ子さんの句集の出版祝いをした。東京に戻って三日ほど、やはり尿が濃く、九月七日主治医に相談しようと、直前にシャワーを浴びると、身体が黄色いのである。朝日の入る浴室で「黄金仏」のような感じであった。主治医は尿と血液を採って明日結果が分かるという。ところが翌日は「井月さんまつり・井月俳句大会」で伊那市へ行く予定があり、結果は月曜日の朝聞くこととした。金曜日の昼伊那に着き、二時間ほど町を散策し、五時過ぎから馴染みの店に仲間が集まった。その中に銀漢の会員で伊那中央病院副院長の中山中さんがいて、私の様子を見て只ならぬ雰囲気であった。「明日会場で検査しましょう」と言う。翌朝会場の控え室のテーブルの上で携帯用超音波検査機で調べて下さった。「①肝内胆管拡張 ②胆嚢緊満 ③胆外胆管拡張 ④膵臓異常なし」という見解であった。「井月さんまつり」を終えて、翌日の俳句大会は欠席として、五時過ぎの高速バスに乗った。双葉サービスエリアから銀漢の清水旭峰医師に電話をし、病状をメールで送ると、一時間もしないうちに「新宿に着いたらそのまま順天堂医院の夜間緊急外来に直行されたし」とメールが入った。九時過ぎに訪ねると清水医師が自宅から駆け付けてくれていた。夜中の二時位まで検査があり、清水医師は病室に入るまで付き添って下さった。伊那と東京と二人の俳縁のある医師に助けられて驚くほど迅速に入院できたのであった。
豊年や吾は老残の黄金仏 (黄疸発症)
一日置いた月曜日から超音波検査、内視鏡検査、MRI、レントゲン、心電図その他の検査を終えて土曜日に退院した。内視鏡検査の折、胆管にストローのバイパスを入れて胆汁が通るようになったので、尿の色や顔色は徐々に戻ってきた。胆管の下部に腫瘍があることは間違い無い。肝臓、膵臓はどうやら無事のようである。
九月二十三日松山市の「子規顕彰全国俳句大会」の記念講演を果たした。会場に銀漢の森羽久衣医師の姿を見付けて驚いた。恐らく心配して私には内緒で松山迄見守りに駆け付けてくれたのである。
|





盤水俳句・今月の一句
伊藤伊那男
鶴川村びつしり雨の枯葎 皆川 盤水
先生は新宿西口の焼鳥屋「ボルガ」で度々酒席を共にしていた石川桂郎に私淑していたようだ。前書に「故石川桂郎を偲ぶ」とある。既に酒を飲めなくなって病臥していた桂郎の七畳小屋を見舞に訪ねている。「生粋の江戸ッ子、お洒落で内に自信とハニカミ、それに自虐を持つ俳人であった。(中略)鳥が啼かない日があってもボルガに桂郎のいぬ日はなかった」「心やさしい氏には艶聞が多かったらしい」と記す。忌日は十一月六日、享年六十六。(昭和五十一年作『定本
板谷峠』所収)
|




彗星集作品抄
伊藤伊那男・選
水澄みて近江八景定まりぬ 中野 堯司
添状に父の忌のこと母の柿 中山 桐里
情つ張りの血脈滾る立佞武多 萩原 陽里
虫の音や枕草子へ指しをり 池田 桐人
木の実降る蝦蟇の膏の口上に 瀬戸 紀恵
子規庵に鶏頭数へ直しゐる 武井まゆみ
黄落にゐて青春を齣送り 杉阪 大和
片べりの天宥の磴秋のこゑ 唐沢 静男
猿酒薪割る音を聞きながら 川島秋葉男
風を撫で風を切る手や風の盆 清水佳壽美
どしやぶりに遭ひたるやうな深川祭 白濱 武子
越中の男踊は月連れて 坂口 晴子
井月のことを語らふ今年酒 堀切 克洋
星の数増えてふくらむ踊の輪 渡辺 花穂
かなかなや見つけてほしいかくれんぼ 池田 桐人
秋耕や律儀なまでの鍬の跡 畔柳 海村
勘平が手締めに出たる村芝居 中島 凌雲
出し物の最初は手品敬老日 飛鳥 蘭
みづからを雁字搦めに藪からし 多田 悦子






|
伊藤伊那男・選
水澄みて近江八景定まりぬ 中野 堯司
| 近江八景は江戸初期に関白近衛信尹(のぶただ)が中国洞庭湖の八景図に倣って選んだ。江戸後期に浮世絵師歌川広重が描いて一般に普及したものである。大田蜀山人に〈乗せたからさきはあわずかただの駕籠ひら石山やはせらせてみゐ〉と詠んだが、この狂歌の中に「瀬田・唐崎・粟津・堅田・比良・石山・矢橋・三井」が入っており、舌を巻くばかりである。さてこの句、淡海の大きな水甕が秋を迎えて澄み始めたという壮大な景である。それによって八景の地も際立っている、と近江を称えている。「水澄みて」の「て」は普通だと因果めくのだが、この句の場合は気にならない。 |
添状に父の忌のこと母の柿 中山 桐里
| この句の場合、他の果実の何を持ってくるよりも、柿が合っているように思う。「母の柿」とあるから、買ってきたものではなく、庭か畑から捥いだものである ころがいいのである。 |
情つ張りの血脈滾る立佞武多 萩原 陽里
| 「立佞武多」は青森県五所川原の八月初めの行事。収穫の前に仕事の妨げとなる睡魔を防ぐ祭とされる。「情つ張り」は津軽地方の方言で「意地を張る」ことを言う。中央政権への反骨の血が騒ぐ祭でもあるようだ。 |
虫の音や枕草子へ指しをり 池田 桐人
取合せの妙ということになろうか。『枕草子』は四季の変化に敏感である。だからこそ「虫の音」との取合せに必然性を感じるのである。虫の音にふと読み止しの本に指を栞に挟んだのである。
|
木の実降る蝦蟇の膏の口上に 瀬戸 紀恵
| この頃は蝦蟇の膏を聞かなくなってしまった。科学の発達で大道芸の口上を信じる人が居なくなってしまったからであろうか。香具師の口上を囃しているかのように「木の実」が降るという。ほのかな滑稽味が滲むところがいい。 |
子規庵に鶏頭数へ直しゐる 武井まゆみ
| 〈鶏頭の十四五本もありぬべし〉は明治三十三年、子規の死の二年前の句で、子規庵での病床句である。句の評価は大きく分れて今日に到っている。この句は子規庵を訪ねて鶏頭の数を確かめている、というのである。子規生前と今と同じである訳が無いのだが、その無駄な行為に子規を偲ぶ心があって愉快である。実は先日松山の子規記念館を訪ねた折、根岸を模した庭の鶏頭を私もついつい数え始めて、苦笑してしまったのであった。 |
黄落にゐて青春を齣送り 杉阪 大和
| 「黄落」に自身の年輪を重ねている。齣送りがうまい。 |
片べりの天宥の磴秋のこゑ 唐沢 静男
| 羽黒山中興の祖天宥上人を偲ぶ。杉並木から天宥の声が。 |
猿酒薪割る音を聞きながら 川島秋葉男
| 山荘の冬仕度。猿酒という謎めいた酒の面白い取合せ。 |
風を撫で風を切る手や風の盆 清水佳壽美
どしやぶりに遭ひたるやうな深川祭 白濱 武子
越中の男踊は月連れて 坂口 晴子
井月のことを語らふ今年酒 堀切 克洋
| 井月に今年酒の句が幾つもある。これからも語り継ぐ。 |
星の数増えてふくらむ踊の輪 渡辺 花穂
かなかなや見つけてほしいかくれんぼ 池田 桐人
日暮の早い秋。蜩に急かされて鬼役に早く見つけて欲しい。
秋耕や律儀なまでの鍬の跡 畔柳 海村
勘平が手締めに出たる村芝居 中島 凌雲
| 忠臣蔵の早野勘平。死んだ筈の勘平の出現が可笑しい。 |
出し物の最初は手品敬老日 飛鳥 蘭
| 年寄の喜ぶものは何か。まずは手品でびっくりさせて。 |
みづからを雁字搦めに藪からし 多田 悦子
| 迷惑な藪からしだが、自らも雁字搦めという視点が発見。 |



|



銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
根の国に近き出雲や蚯蚓鳴く 東京 飯田眞理子
輪になつて正座が出来て地蔵盆 静岡 唐沢 静男
盤水の太文字恋し秋扇 群馬 柴山つぐ子
奥谷戸に小さき谺をばつたんこ 東京 杉阪 大和
鶏頭の風に揺るがぬ重さあり 東京 武田 花果
列島といふ大鯰震災忌 東京 武田 禪次
蟷螂の弓なりに風迎へうつ 埼玉 多田 美記
一幕で帰りし忘れ扇かな 東京 谷岡 健彦
小面に悲喜の陰影夜の秋 神奈川 谷口いづみ
お仕置の蔵の窓より天の川 長野 萩原 空木
鶏頭の斬られて影の生まれけり 東京 堀切 克洋
落人となり八月の山暮し 東京 松川 洋酔
戦争を知らぬ子の子や日雷 東京 三代川次郎






伊藤伊那男・選
吾が産土魚のにほひのやませ吹く 宮城 齊藤 克之
天の川からの風とも信濃路は 埼玉 戸矢 一斗
国生みの島が火種か大夕焼 和歌山 笠原 祐子
楽屋着のお岩も怖し盆芝居 東京 小山 蓮子
松崎逍遊さん
台風のやうな友逝く九月かな 東京 川島秋葉男
柄杓からも水瓶からも星流る 東京 小林 美樹
灯の入りて目がものを言ふ佞武多かな 東京 岡城ひとみ
摩天楼を卒塔婆として盆の月 東京 坪井 研治
大皿に刺身蒟蒻秋祭 東京 中村 藍人
指の間に坊さんの出る衣被 東京 福永 新祇
ブルジョアもプチブルも死語三島の忌 東京 沼田 有希
貴船より生まるる滴水澄めり 兵庫 清水佳壽美
京路に萩のふた色寧々と茶々 千葉 白井 飛露
亀虫のどうでも外へ出たがらぬ 東京 梶山かおり
天の川富士に投網を打つごとく 東京 有澤 志峯
八月や焦土の地図にこの場所も 東京 朽木 直
冥府より二三尺曳く迎鐘 大阪 中島 凌雲
山葡萄たわわと言へど疎らなり 長野 守屋 明
繊月のしづく待ちたる添水かな 東京 矢野 安美
関節で繫がるからだ阿波踊 東京 大住 光汪
杉玉の下に落ち合ふ風の盆 東京 飛鳥 蘭
生きてゐるひと日大事と大根播く 宮城 有賀 稲香
乾びゆく草の香や秋の蝶 神奈川 有賀 理
蚯蚓鳴く土気失せたる石舞台 東京 飯田 子貢
草色となり蟷螂は気配消す 山形 生田 武
あの下にも人のくらしや遠花火 埼玉 池田 桐人
亀岩に脚立の足を松手入れ 東京 市川 蘆舟
ユトリロの白壁恋し残暑の夕 埼玉 伊藤 庄平
天竜河畔
水澄むやことに入舟港跡 東京 伊藤 政
里宮の一樹の杜や盆の市 神奈川 伊東 岬
待宵や合はせ鏡に髪なほし 東京 今井 麦
竜胆の閉ぢたるままや阿蘇は雨 埼玉 今村 昌史
秋風へ毛鉤の棹は弧を放ち 東京 上田 裕
大鍋も小鍋も噴きぬ豊の秋 東京 宇志やまと
箒目に風立つことも今朝の秋 埼玉 大澤 静子
鰯雲年毎に瘦せ力瘤 神奈川 大田 勝行
桔梗なほ五稜を保つ蕾かな 東京 大沼まり子
爽やかや人を笑顔にして帰す 神奈川 大野 里詩
竹伐つて風の賑はふ夕べかな 埼玉 大野田井蛙
川底の石のまろさよ水澄めり 東京 大溝 妙子
唐突に無聊埋めらる敬老日 東京 大山かげもと
開演のベルに駆け込むサングラス 東京 小川 夏葉
方丈に柾目のとほる夜涼かな 愛知 荻野ゆ佑子
休暇果つ小屋一つ分薪割つて 宮城 小田島 渚
篝火の爆ぜて闇濃き踊かな 宮城 小野寺一砂
本物の糸瓜見たくて子規庵へ 埼玉 小野寺清人
木の実落つそれぞれの名の曖昧に 愛媛 片山 一行
地蔵盆三々五々に子ら集ふ 静岡 金井 硯児
掬ふ手のためらふほどに水澄めり 東京 我部 敬子
神南備の水を賜り新豆腐 千葉 川島 紬
短髪に色なき風を捉へたり 神奈川 河村 啓
名月の金婚の旅まどかなり 愛知 北浦 正弘
地虫鳴くかたはらで切る足の爪 長野 北澤 一伯
中心に闇の奔流天の川 東京 絹田 稜
志残す子の名や敗戦忌 東京 柊原 洋征
水澄みて水琴窟の音も更に 神奈川 久坂衣里子
秋風の襟より袖へ抜けゆけり 東京 畔柳 海村
桃むいて新たな桃のあらはれる 東京 小泉 良子
破れ傘一本足で立ちにけり 神奈川 こしだまほ
落日は秋光となり外ヶ浜 青森 榊 せい子
星々のこゑの中なる草泊 長崎 坂口 晴子
鳴くかとも遠野辺りの蚯蚓なら 長野 坂下 昭
法師蟬鎮守の森をふくらます 群馬 佐藤 栄子
一山のふところ深し草の花 群馬 佐藤かずえ
耳許に紙音めきし鬼やんま 長野 三溝 恵子
片陰は深く息吸ふところなり 広島 塩田佐喜子
海風や下駄に砂入る盆踊 東京 島 織布
朝顔や低く始むる読経かな 東京 島谷 高水
秋簾音を残して都電過ぐ 東京 清水 史恵
蓮の実の飛び虚ろなる花托かな 東京 清水美保子
穴まどひ地球沸騰してゐると 埼玉 志村 昌
独尊の子規を励ます鶏頭花 神奈川 白井八十八
丸の付く漁船ばかりや盆休み 東京 白濱 武子
法師蟬飛び去り故郷去りがたし 東京 新谷 房子
うみと呼ぶ大き湖鰯雲 大阪 末永理恵子
風鈴や退屈さうな音鳴らす 東京 鈴木 淳子
どの家も早起き鄙の盆休 東京 鈴木てる緒
敗戦の日も川遊び疎開の日 群馬 鈴木踏青子
残暑光眼鏡のふちをきらめかせ 東京 角 佐穂子
こころ透くかに白萩の風のみち 東京 瀬戸 紀恵
母からの電話鳴りさう秋の夜は 神奈川 曽谷 晴子
ほんたうの空色に咲く露草は 長野 髙橋 初風
土管より男出てくる秋の暮 東京 高橋 透水
桃の実に太郎の鼓動聴こえさう 東京 武井まゆみ
紅玉の剝くをためらふ光かな 東京 竹内 洋平
立秋の夕刊にある熱の量 神奈川 田嶋 壺中
朝顔の種を次なる学年へ 東京 多田 悦子
鰐口の音のこもれる残暑かな 東京 立崎ひかり
桔梗咲く蕾のままのやうに咲く 東京 田中 敬子
穴惑ひ石の積まるる桑畑 東京 田中 道
砂時計刻を吞みこむ秋の暮 東京 田家 正好
八月の運河に油膜漂へり 東京 塚本 一夫
水澄むや五湖にそれぞれ甲斐の富士 東京 辻 隆夫
次々に落とされてゆく夜業の灯 ムンバイ 辻本 芙紗
脇にゐる薄き衣の菊人形 東京 辻本 理恵
大海原銀漢の尾は沈みけり 愛知 津田 卓
瀬戸内に橋なき昔天の川 千葉 長井 哲
水澄みて魞点景の淡海かな 神奈川 中野 堯司
深呼吸して八月の峠かな 東京 中野 智子
味よりも名前が旨しきぬかつぎ 東京 中村 孝哲
啄木鳥や己が木霊を聴いてをり 茨城 中村 湖童
手始めは脚立頼みや盆用意 埼玉 中村 宗男
芋嵐つまづきながら浮く鴉 長野 中山 中
朝顔の咲きぬと母の添手紙 千葉 中山 桐里
湯上がりの匂へる踊浴衣かな 大阪 西田 鏡子
台風の目の中に立つ梯子かな 埼玉 萩原 陽里
枝に座す明恵の寺の夏蛙 東京 橋野 幸彦
一振りの胡椒に噎せる残暑かな 広島 長谷川明子
秋蟬や明日なき声と覚えしか 東京 長谷川千何子
伊吹嶺の翠微に広ぐ花野かな 兵庫 播广 義春
疎開地の山河ありあり終戦日 埼玉 半田けい子
鰯雲馬車で行きたき遠き町 埼玉 深津 博
避暑の宿エレベーターに椅子一つ 東京 福原 紅
野葡萄の郷愁といふ風の色 東京 星野 淑子
処暑となる髪を短く切りにけり 東京 保谷 政孝
含みたしあをき銀河の一掬ひ 岐阜 堀江 美州
山の名に太郎次郎や秋澄めり 埼玉 本庄 康代
新涼や我が身ほとりも片付きて 東京 松浦 宗克
蚯蚓鳴く余白ばかりの日記帳 東京 松代 展枝
水引草修験の道へ紅をさす 神奈川 三井 康有
破れ目を見るともなしに秋扇 神奈川 宮本起代子
霧流る物音全て奪ひつつ 東京 村田 郁子
西鶴忌今宵ルージュの色の濃き 東京 村田 重子
今朝秋の足に親しき畳の目 東京 森 羽久衣
熱き湯になほ瘦せ我慢生身魂 千葉 森崎 森平
野の風の形を成しぬ乱れ萩 埼玉 森濱 直之
訛には訛で答へ秋刀魚焼く 東京 保田 貴子
水澄める余呉湖の底の穴太積 愛知 山口 輝久
秋茄子や夕べの雨の雫垂る 群馬 山﨑ちづ子
秋扇かなめを指で押さへつつ 東京 山下 美佐
古色とも盛りを迎へ吾亦紅 東京 山田 茜
薀蓄を聞く間もどかし鰍酒 東京 山元 正規
酒たんと吸ふや残暑の井月墓 東京 渡辺 花穂
八月大名店屋物にて済ます昼 埼玉 渡辺 志水







銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男・選
吾が産土魚のにほひのやませ吹く 齊藤 克之
| 夏、太平洋側へ吹く冷湿な風が「やませ」である。気仙沼漁港の近くに住む作者であるから、その風には魚臭が混じっている。生活実感の伴う地に足の付いた句であった。 |
天の川からの風とも信濃路は 戸矢 一斗
| 詩情の濃い句である。信濃路に吹く風は満天の天の川から吹く風であるのか、と思う。俳句形式の省略を効かせて信濃の秋を詠み取った爽快な仕上がりの句となった。 |
国生みの島が火種か大夕焼 笠原 祐子
| 神話で言うおのころ島は淡路島であるという。作者の住む和歌山から見る夕焼の先は淡路島の方角なのであろう。「火種」が伊弉諾(いざなぎ)・伊弉冉(いざなみ)の神話を象徴しているようだ。 |
楽屋着のお岩も怖し盆芝居 小山 蓮子
| 四谷怪談は人間の色と欲が絡むだけに何回見ても怖いものである。舞台の上のお岩だけでなく、楽屋に寛ぐお岩もやはり怖いという。この滑稽味が俳句の要諦である。 |
台風のやうな友逝く九月かな 川島秋葉男
| 松崎逍遊君は作者とは秋葉原の仕事仲間であり、私とは信州の伊那北高校の同期生であった。高校時代から突出した行動力を持つ人であった。湯島句会の生みの親で、銀漢俳句会設立にも尽力してくれた。「台風のやうな友」はまさに実感である。〈友逝くや嗚咽のごとく秋の蟬〉も。 |
柄杓からも水瓶からも星流る 小林 美樹
| 北斗七星が柄杓。水瓶座はギリシャ神話の美少年ガニメデスが水瓶を抱いている様子。二つに共通するのは「容器」。そこから星が流れるという知的好奇心を擽られる句だ。 |
灯の入りて目がものを言ふ佞武多かな 岡城ひとみ
| 佞武多絵は武者や鬼などの張子だが、いずれも句のように目が大きいのが特徴である。ことに灯が入れば尚更。「目がものを言ふ」に臨場感がある。 |
摩天楼を卒塔婆として盆の月 坪井 研治
| 福永耕二に〈新宿ははるかなる墓碑鳥渡る〉がある。ようやく新宿西口に幾つかの超高層ビルが建った頃の句である。今や東京中が高層ビルの街となり、寺に林立する卒塔婆のようである。先行句はあるが、この句は一つの句格を持った句と言っていい。超高層の盆の月である。 |
大皿に刺身蒟蒻秋祭 中村 藍人
| 秋祭であれば色々なご馳走が並ぶのであろうが、刺身蒟蒻であるところがいい。秩父とか上州とか山国では手作りの上質な蒟蒻が出される。こんな秋祭に出合いたいものだ。 |
指の間に坊さんの出る衣被 福永 新祇
| 衣被は平安期の身分の高い女人が外出時に顔を隠すため衣を被ったことを言うが、皮を付けたままの里芋をそれに模した言い方。つるりと剝くと真白な芋が顔を出すのだが、それを「坊さん」と見た。比喩に比喩を重ねた面白さ。 |
ブルジョアもプチブルも死語三島の忌 沼田 有希
三島由紀夫が割腹したのは私の大学生時代、数えてみれば五十三年前のことである。学生運動がまだ盛んで、やれブルジョアだのプチブルだのと議論が沸騰していた時代だ。随分昔の事になってしまった。三島の享年は四十五。
|
貴船より生まるる滴水澄めり 清水佳壽美
| 京都貴船の地名は神話時代に大きな石船が漂着したことに由来する。貴船神社は祈雨・止雨を司る。京の町で先駆けとして「水澄む」一滴が生まれる所である。 |
京路に萩のふた色寧々と茶々 白井 飛露
| 何とも豊かな発想の句である。萩は秋の七草の一つ(といっても草ではなく灌木)で古来日本人に愛された。紅白の二色があるが、京に咲く萩ならば、どちらかが寧々(北政所)であり、どちらかが茶々(淀君)であるという。誰も詠んでいない独自の表現であることを称えたい。 |
亀虫のどうでも外へ出たがらぬ 梶山かおり
| 亀虫は放屁虫ともいい厄介な虫である。冬近くなると家に入り込む。山形の法蓮寺では足の踏み場も無い程であった。秩父の宿でも布団の押入れにいて困惑した。「外へ出たがらぬ」はまさにその通りで、只々頷くばかりだ。 |
その他印象深かった句を次に
天の川富士に投網を打つごとく 有澤 志峯
八月や焦土の地図にこの場所も 朽木 直
冥府より二三尺曳く迎鐘 中島 凌雲
山葡萄たわわと言へど疎らなり 守屋 明
繊月のしづく待ちたる添水かな 矢野 安美
関節で繫がるからだ阿波踊 大住 光汪






伊藤伊那男・選
秀逸
鰯雲夕日に鱗焦げてをり 東京 熊木 光代
籠ごしの虫売の目の大きこと 千葉 園部あづき
水を撒く前の挨拶朝顔に 神奈川 山田 丹晴
天の川動かぬものに石舞台 群馬 北川 京子
蟷螂の狩の始めは祈りから 東京 久保園和美
簡単なランチ簡単服の二人 栃木 たなかまさこ
うかつなる雷神雨をともなはず 長野 戸田 円三
天の川佐渡に行き交ふたらひ舟 岐阜 鈴木 春水
電車ゆく夜業の人を照らしつつ 東京 北原美枝子
二枚目のレコード選ぶ夜長かな 東京 倉橋 茂
山小屋の灯りもひとつ星月夜 静岡 山室 樹一
動くより動かぬ暑さありにけり 東京 渡辺 誠子
磁場ゼロの分杭峠蚯蚓鳴く 東京 西田有希子
拾ひたる零余子十ほど飯に炊く 愛知 箕浦甫佐子
ラジオから「信濃の国」が栗むけり 長野 馬場みち子
まがねふく吉備に鬼ノ城唐辛子 東京 髙坂小太郎


星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
夕顔や白き卓布の皺延ばす 東京 尼崎 沙羅
子の代で絶ゆる血筋や墓参 東京 井川 敏
扉無き農機具小屋に蚯蚓鳴く 長野 池内とほる
梅雨寒や二の腕からも脛からも 東京 石倉 俊紀
浅草の空にあきつや神谷バー 東京 一政 輪太
虫売と籠を交互に覗きけり 東京 伊藤 真紀
年寄るを忘るるための昼寝かな 広島 井上 幸三
新米やおかはり三度と孫の報 愛媛 岩本 青山
吹き込みの吹き込むままに大夕立 長野 上野 三歩
野分去り風に瞬く熱海の灯 東京 上村健太郎
包丁の音にひやひや南瓜かな 長野 浦野 洋一
虫食ひの葉つぱの陰に赤まんま 群馬 小野田静江
堀端にマラソンの人道灌忌 静岡 小野 無道
鳥海山や海へ落ち入る天の川 埼玉 加藤 且之
擦れ違ふ人うろ覚え秋彼岸 長野 唐沢 冬朱
立山を仰ぐ胡座や天の川 愛知 河畑 達雄
進むこと勿体ぶつてゐる御輿 神奈川 北爪 鳥閑
落鮎や竿の数だけ魚籠ありし 群馬 黒岩伊知朗
葉脈を伝ふ朝露キャベツ畑 群馬 黒岩 清子
銀漢に凭れて波の浜に立つ 愛知 黒岩 宏行
晩年の母のさびしさ吾亦紅 東京 黒田イツ子
遠花火闇の向かうに戦火かな 東京 小寺 一凡
林檎むく皮の床まで届く迄 千葉 小森みゆき
きのふとは同じ日ならず秋一日 神奈川 阪井 忠太
蚯蚓鳴く見ゆるはず無き眼を開き 長野 桜井美津江
烏瓜木々を絡めて色深む 東京 佐々木終吉
リハビリのゴールは間近秋高し 群馬 佐藤さゆり
なくなればそれも寂しき残暑かな 東京 島谷 操
迎火を焚く子らが居ぬ故郷に 東京 清水 旭峰
それらしき気配はあらず今朝の秋 千葉 清水 礼子
廃線の車止めより枯野かな 大阪 杉島 久江
茅屋の小窓抜くるや去ぬ燕 東京 須﨑 武雄
天高く漁船のくぐる橋の下 愛知 住山 春人
処暑の風入れて夕刊拾ひ読み 東京 関根 正義
草の花笑ひて負くる泣き相撲 埼玉 園部 恵夏
手相見のそばに居るらし虫売り屋 東京 田岡美也子
川宿の離れにひとつ秋簾 東京 髙城 愉楽
阿武隈の天蓋として星月夜 福島 髙橋 双葉
団栗が落ちてきさうな露天の湯 埼玉 武井 康弘
水音の込められてゐる新豆腐 東京 竹花美代惠
蚯蚓鳴く皆が耳鳴り持つ齢 埼玉 内藤 明
捨つるもの捨てて秋立つ四畳半 東京 中込 精二
山鳩やここは避暑の地軽井沢 群馬 中島みつる
津波跡に波音を聞き震災忌 神奈川 長濱 泰子
不揃ひに下駄音走る宵祭 京都 仁井田麻利子
盆灯や新住職の正信偈 東京 西 照雄
蟋蟀や直訴のやうな声のして 宮城 西岡 博子
爽やかや調律終へしピアノの音 神奈川 西本 萌
かなかなのひとしほ胸に夕間暮れ 静岡 橋本 光子
白桃に吉備の伝説憧れぬ 東京 橋本 泰
健診を終へて固めの栗ご飯 神奈川 花上 佐都
妻の忌の菊日和とぞなりにけり 千葉 針田 達行
蟷螂や流人の島に風凄まじ 神奈川 日山 典子
みどりごの足の産毛や涼新た 千葉 平野 梗華
待宵や物干に出て人の声 千葉 深澤 淡悠
昨日より今日又増ゆる刈田かな 長野 藤井 法子
夕間暮れ九月の瀬音遠くより 福岡 藤田 雅規
竹の春引き返すには鬱蒼と 東京 幕内美智子
蟷螂の鎌も借りたき空き地かな 東京 松井はつ子
枝ぶりの良き影かかる今日の月 神奈川 松尾 守人
夜を通し下駄減るまでを盆の舞 東京 棟田 楽人
尾瀬沼やとんぼのとまる登山地図 東京 無聞 益
秋場所やつはものどもの神の域 宮城 村上セイ子
名を呼びて夕餉知らせる秋の暮 東京 家治 祥夫
欄干に草絡ませる野分かな 群馬 山﨑 伸次
蘭鋳や槽の底から動かざる 群馬 横沢 宇内
蟷螂や組み敷けば頤逞しく 神奈川 横地 三旦
好きな雲選びて秋のベンチかな 神奈川 横山 渓泉
竜胆や咲きて修験の道標 千葉 吉田 正克
秋の声月の山より降りて来る 山形 我妻 一男
夏の牡蠣寿司屋の玻璃に鎮座せり 東京 若林 若干
カレー屋に今日も来てをり秋暑し 埼玉 渡辺 番茶


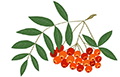




星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
鰯雲夕日に鱗焦げてをり 熊木 光代
| 日没前の鰯雲に残照が当たると、雲の一部があたかも焦げたように見えたという。「鱗が焦げた」と魚の比喩を用いたところが技倆である。秋空の一景によく目が行き届いた。 |
籠ごしの虫売の目の大きこと 園部あづき
| 目の付けどころの面白い句である。籠の中の虫よりも、籠の中を覗き込む虫売の目に作者は注目しているのだ。虫の居場所を探す見開いた目に焦点を当てたのがいい。 |
水を撒く前の挨拶朝顔に 山田 丹晴
| 朝顔が動かない句である。朝顔を楽しむために早朝に起きる。労いの水を遣るのだが、その前に「挨拶」をする。朝顔の「顔」があるからこそ「挨拶」という表現が効くのである。 |
天の川動かぬものに石舞台 北川 京子
| 飛鳥の石舞台は一説には蘇我馬子の墓で、乙巳の変の後暴かれて今の状態になったという。だが巨石は揺るがない。虚子に〈天の川のもとに天智天皇と臣虚子と〉があるが、その反歌のような趣を持つ、地名を生かした句だ。 |
蟷螂の狩の始めは祈りから 久保園和美
| 蟷螂を擬人化して、その動作の実態を見事に捉えた名作である。立ち上がって前肢を摺り合わせるようにして獲物を狙うのだが、それを「祈り」と見立てたのは卓見。 |
簡単なランチ簡単服の二人 たなかまさこ
| 簡単服は関西でいうアッパッパと同じで、貫頭衣のような、まさに簡単な作りで、関東大震災の後あたりから普及したようである。この句は、「簡単」の字を使い分けて巧み。 |
うかつなる雷神雨をともなはず 戸田 円三
| 雷が鳴ったあと空が暗くなって雨が降るのが一般的な気象現象である。ところがこの句では迂闊にも只単発で鳴っただけだという。空砲に雷神自身も驚いているのだ。 |
天の川佐渡に行き交ふたらひ舟 鈴木 春水
| 不確かな記憶だが、恋人に会うためにたらい舟で日本海を渡る、というような悲恋の話を聞いたことがある。天空の逢瀬の物語と、現世の逢瀬の話が交錯する。 |
電車ゆく夜業の人を照らしつつ 北原美枝子
| 町工場の多い沿線を通過したのであろうか。線路沿いの工場は煌々と灯り、また電車の光もそれを照らして過ぎる。いかにも都会の夜業である。 |
二枚目のレコード選ぶ夜長かな 倉橋 茂
| 秋は物理的にも夜が長くなるが、夏を越して涼しく快適な夜であることが「夜長」の季語の本意であろう。次のレコードに針を置く。まさに夜長を楽しむ心である。 |
山小屋の灯りもひとつ星月夜 山室 樹一
| 山小屋の灯りという人工の明りも、自然の一つの明りのように詠まれているのがいい。慎ましやかに点り、自然と一体化したような灯であることが好ましい。 |
動くより動かぬ暑さありにけり 渡辺 誠子
| 確かに実感のある句だ。恵林寺の快川和尚は「心頭滅却すれば火も自ずから涼し」と言ったけれど、凡夫はそうはいかない。動かないことの焦燥感の方が暑さが増すのだ。 |
磁場ゼロの分杭峠蚯蚓鳴く 西田有希子
| 分杭峠は伊那谷の赤石山脈の下を辿る秋葉街道の峠の一つ。この辺りを中央構造線が走り、磁石が狂う不思議な場所である。それだけに「蚯蚓鳴く」ことも有ろうかと。 |
拾ひたる零余子十ほど飯に炊く 箕浦甫佐子
| 零余子は自然薯の玉芽。風雅なものだが特に旨いものではない。炊き込みご飯などにするが「十ほど」に零余子らしさがあっていい。そこにあったからという「拾ひたる」もやはり零余子らしいのである。 |
ラジオから「信濃の国」が栗むけり 馬場みち子
| 「信濃の国」は長野県歌で、これを歌えるかどうかで、信州人であるかどうかが解るという証明書のような歌。「栗むけり」がいい。山に自生する柴栗なのであろう。 |
まがねふく吉備に鬼ノ城唐辛子 髙坂 小太郎
| 「真金吹く」とは鉄を精錬することで「吉備」の枕言葉である。白村江の戦いに破れた天智天皇が防衛の為に築いたのが鬼ノ城。「唐辛子」の季語の斡旋が、精錬の火の色のようでもあり、天皇の意志のようでもあり、効果を発揮している。枕言葉を使ったこともあるが、一度で憶えてしまう調べの良さ、口誦性を持っている。 |


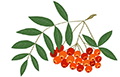





伊那男俳句 自句自解(95)
分校を持ち上げてゐる霜柱
最近の東京では霜柱を見ることはほとんど無い。私の育った伊那谷は雪が少なかったものの山脈から下りてくる冷気は凄まじく、朝は霜柱の世界であった。当時の子供は黒足袋に下駄履きで、ざくざくと踏みしめて通学したものである。場所によって違いはあるが、驚くほど高く伸びている霜柱もあった。そんな思い出があったので右の句が生まれたのである。私の学校は分校ではなかったが、句としては分校の方が実感が出そうである。俳句は舞台設計や強調も大事なのである。正確に詠むとするならば「分校を持ち上げさうな(・・・)」と比喩にしなくてはならないのだが、一歩踏み込んで「持ち上げてゐる」と断定表現にしたのである。この辺りの匙加減が雁字搦めの写生派で育った私には実は結構な冒険なのである。写生派は「物理的に持ち上がるわけが無いだろう。嘘を言うな」と言う。詩的強調は許されなかったのである。「俳句」誌に発表したが幾つもの結社誌で褒めていただいた。
餅搗の影を大きく海鼠塀
母の生家は伊那谷の街道沿いの古い商家で、母の育った頃はかなり裕福であったようだ。戦後一気に没落し、土地の割譲などもあったようだが、敷地には蔵が五つほどあった。悪戯をして閉じ込められたりもしたものだ。当時は蔵の前に大釜を据えて味噌も家で作ったものだ。もちろん餅搗きも。今は二つ年上の従兄が家を守っているが、餅搗きの伝統は連綿として欠かさない。毎年私達にも送ってくれるので大量に搗き上げるようである。ある年の暮、たまたま郷里にいて運よくその餅搗きに立ち合うことができた。餅米を蒸籠で蒸し上げて湯気ごと臼に移して搗く。私も杵を握ってみたが、なかなか重たいもので足許がおぼつかない。高校生の頃から搗いている従兄は馴れたもので、軽々と振り上げて次々に搗いていく。歳晩の日が傾くと海鼠壁や海鼠模様の蔵壁に従兄の影が伸びていくのであった。普通の家庭からは消えてゆく風景であり、行事である。 |







更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。



リンクします。
aishi etc



挿絵が絵葉書になりました。
Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組
8枚一組 1,000円
ごあいさつにご利用下さい。

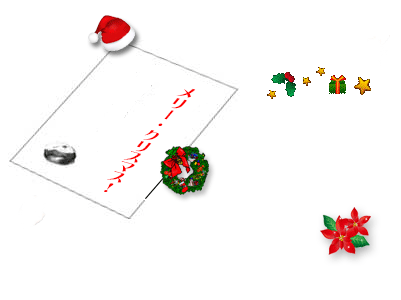






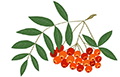




|
![]()
![]() 12月号 2023年
12月号 2023年 




























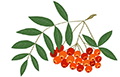




![]()