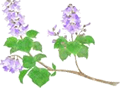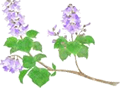銀漢の俳句
伊藤伊那男
◎熊野随感
四十歳の頃だからもう四半世紀前、五月の連休に思い立って熊野を訪ねたことがある。熊野本宮大社を訪ねた辺りで日が傾き、慌てて宿を探したが、どこも満室で途方に暮れた。まだ体力もあったので夜の熊野古道を歩くことにして翌朝継桜に辿り着いたのだが、遅霜の降りた寒い夜道を薄着で辿るという語るも涙の体験をしたことがある。
それはさておき、昨年末の煤逃吟行会はその熊野であった。私は大阪から紀勢本線で海岸線を辿って合流したのだが、しみじみ熊野は僻遠の地であることを実感した。木の国とも根の国とも言われた古代からの異界の地である。記紀神話では、一旦は長髄彦に敗退した神武天皇は熊野から太陽を背にして大和に攻め入り勝利を得た。平安中期から熊野信仰が盛んになり、後白河法皇は生涯に三十四回詣でているから只事ではない。今でも遠いのに足腰が頼りの時代である。往復一ヶ月以上はかかる旅だ。距離もさることながら重畳たる熊野山地の山襞深く分け入る難儀な旅だ。法皇の好む今様に〈熊野へ参らむと思へども徒歩より参れば道遠し〉とある。しかし続けて〈広大慈悲の道なれば紀路も伊勢路も遠からず〉とあり、苦難の末に至福の霊験を得たのであろう。
熊野で気付くのは奇岩、巨石が多いことだ。往古大規模な造山運動、火山活動がもたらした独特の風景で、至る処に温泉が湧く。那智の滝やごとびき岩のような圧倒的で人智の及ばない景観が展開する。当然自然崇拝、原始宗教の原点となる。今回の旅で、伊勢と熊野の違いについて思うことがあった。伊勢は稲作や社会秩序をもたらせてくれた大祖の感謝と畏敬を形にしたもの。熊野は圧倒的な自然への恐怖、底知れない力に対する鑚仰ということになろうか。伊勢は弥生時代の神で、主神が天照大神であることは誰もが知るところだ。一方熊野は誰を祀っているのか、というと答えられる人は少ない。熊野那智大社は熊野夫須美大神、熊野速玉大社は熊野速玉大神、熊野本宮大社は家津御子大神で、大和朝廷の先祖神とは別である。那智は那智の滝そのものが神なのであろう。那智の滝を詠んだ次の句がある。
神にませばまこと美はし那智の滝 高浜虚子
滝落ちて群青世界とどろけり 水原秋桜子
虚子の句はこの滝を神として崇め、一人の衆生として平伏するという伝統の系譜である。秋桜子の句はその因果を断ち切って、美だけに着目して近代絵画風に、まだ乾かない油絵のように描いたものである。どちらの句を好むかによって各俳人の作句姿勢が決まってくるかもしれない。 |





盤水俳句・今月の一句
伊藤伊那男
夕暮れの富士に笠雲新茶買ふ 皆川 盤水
| 東海道新幹線が静岡県に入ると、車窓に端正に刈り込まれた茶畑が展開する。但しその歴史はそう古いことではない。幕末江戸を開城した徳川慶喜は静岡(駿府)に蟄居していたが、後を追って多くの幕臣が静岡に入った。とてもその人数を養うことはできず、色々な殖産を探ったのだが、その一つが茶の栽培であった。それはさておき、新茶が出るのは梅雨に入るまでの束の間。「笠雲」の斡旋でその頃の気象状況が伝わってくるのである。(平成十一年作『山海抄』所収) |



彗星集作品抄
伊藤伊那男・選
渇筆の軸に声あり臥龍梅 本庄 康代
足袋つぎし久女の針も納めしや 坂下 昭
曲るたび電車はみ出す春の海 曽谷 晴子
缶切りの行方知れずや多喜二の忌 本庄 康代
将門の終の猿島の野火高し 多田 美記
お松明身内を火の粉吹く思ひ 笠原 祐子
紐一本手古摺る着付久女忌や 川島 紬
じやんけんのグーは三寒パー四温 西田 鏡子
剝がしたきバウムクーヘン春の雪 今井 麦
白息の綺羅を頻りに雲母坂 中島 凌雲
梅咲くと誘ひの声が垣越しに 秋津 結
千両の万両よりも殖え易く 小泉 良子
筑波東風浦舟の帆を孕ませて 中村 湖童
磯城島の宮居いづこも梅の花 武田 禪次
ドアノブに纏ふ余寒をまはしけり 保田 貴子
初花や御籤捲かれしところより 堀切 克洋
福耳のやうな春子をひと口に 伊藤 庄平
上達のままならずゐて針供養 山田 茜
揚綱の撓みも凧の高さかな 戸矢 一斗
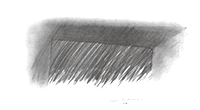




|
伊藤伊那男・選
渇筆の軸に声あり臥龍梅 本庄 康代
| 渇筆とは「かすれた感じを出すために用いる筆。また、その技法」のことをいう。想像するところ書院造りのような座敷の床の間に渇筆で書かれた書か絵がある。枯山水風の庭に臥龍梅が咲き初めている。その典雅さに思わず声を上げる思いなのだが、背後の軸からも感嘆の声が聞こえるようであった、ということであろうか。「軸に声あり」の断定には賛否がありそうだが(私は普通なら反対するのだが)、この句に籠っている力には諾わざるを得ない。調べがよく、句全体から湧き上がる品格が決め手である。 |
足袋つぎし久女の針も納めしや 坂下 昭
| 杉田久女の〈足袋つぐやノラともならず教師妻〉の本歌取りである。ノラはイプセンの戯曲『人形の家』の女主人公で、夫に仕える女性ではなく、一個の独立した人間として再出発する物語である。久女の句はそうした思いに共鳴した作品。その足袋をついだ針も針供養に納めたのであろうか、と展開し、併せて久女の成仏を祈る気持を籠めた句であると思う。発想もよく緻密な構成の句である。 |
曲るたび電車はみ出す春の海 曽谷 晴子
| 海岸の緑を縫うように走る電車の窓外の景色である。見え隠れしていた漁港や小さな岬を過ぎて大きく曲ると、一面海だけとなる。まるで電車がレールを外れて海の上にあるような錯覚を起こす。春の海の明るさと温かさ、抱擁力がいい。「電車はみ出す」の奔放な表現が楽しい春の旅。 |
缶切りの行方知れずや多喜二の忌 本庄 康代
| 言うまでもなく『蟹工船』の作家小林多喜二である。プロレタリア作家として活動したが、官憲の拷問により虐殺された。昭和八年二月二〇日死去、享年二十九歳であった。句の缶切りの発想は『蟹工船』が糸口であろう。思えば最近は缶切りを使うことがない。ほとんどがプルトップ式に変ってしまった。小林多喜二という作家のことも、その作品のことも、その悲惨な死のことも忘れられようとしている。日本の暗い歴史のことも……。そのような思いがこの句に籠められているのであろう。 |
将門の終の猿島の野火高し 多田 美記
| 平将門は一族の紛争から内乱に発展し、自らを新皇と称したことから賊軍として討伐された。その居館が今の茨城県の猿島にあった。「野火高し」に将門の志を重ねているのである。ちなみに神田明神は将門を祀る。成田山新勝寺は逆に将門調伏を祈禱した寺。 |
お松明身内を火の粉吹く思ひ 笠原 祐子
| 奈良東大寺二月堂の修二会の火。その火の粉が吾が身の中に吹き込み、吹き抜ける思いだという。古代から連綿と続く火による浄化作用。「身内」に取り込んだのがいい。 |
紐一本手古摺る着付久女忌や 川島 紬
じやんけんのグーは三寒パー四温 西田 鏡子
剝がしたきバウムクーヘン春の雪 今井 麦
白息の綺羅を頻りに雲母坂 中島 凌雲
| 雲母は比叡山への登り口。言葉遊びだが嫌味は無い。 |
梅咲くと誘ひの声が垣越しに 秋津 結
千両の万両よりも殖え易く 小泉 良子
| 本当かどうか解らぬが……。「万両の千両より」なら駄目。 |
筑波東風浦舟の帆を孕ませて 中村 湖童
磯城島の宮居いづこも梅の花 武田 禪次
ドアノブに纏ふ余寒をまはしけり 保田 貴子
| 初春のドアノブはまだまだ冷たい。余寒と見たのがいい。 |
初花や御籤捲かれしところより 堀切 克洋
福耳のやうな春子をひと口に 伊藤 庄平
上達のままならずゐて針供養 山田 茜
揚綱の撓みも凧の高さかな 戸矢 一斗

|


銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
粥の湯気上がる太梁臘八会 東京 飯田眞理子
寒卵割ればふるへる玉の張り 静岡 唐沢 静男
予期せずと湯宿の氷柱落ちまくる 群馬 柴山つぐ子
風花や風説今に八瀬童子 東京 杉阪 大和
追儺会はまづ将門の一矢より 東京 武田 花果
越生四句
村境越せば日溜まる梅林 東京 武田 禪次
梅沢フミさん
除夜の鐘三つほど余しゆかれけり 埼玉 多田 美記
順風に枕を乗せて宝船 東京 谷岡 健彦
初比叡みえぬ灯に手を合はす 神奈川 谷口いづみ
嘴開けて啼かずままなり寒鴉 長野 萩原 空木
探梅のみな良き顔をしてゐたる パリ 堀切 克洋
毛氈に膝を正しく梅見茶屋 東京 松川 洋酔
臘梅に翳りひとつもなかりけり 東京 三代川次郎




伊藤伊那男・選
水仙や故人予約のランドセル 宮城 小野寺一砂
橋なくて花冷えの世へひきかへす 東京 桂 信子
一辺のみ使ふ暮しや春炬燵 東京 我部 敬子
くづし字の寺請証文をんなの名 長野 三溝 恵子
家系図のごとく並んで初写真 東京 保田 貴子
遠くとも行かずとも佳き梅日和 東京 辻 隆夫
春の風邪ただの年波かも知れず 埼玉 池田 桐人
寝込むには日差しの惜しき春の風邪 千葉 川島 紬
思ひ付くだけのわがまま春の風邪 千葉 白井 飛露
綾取りの川に戻りて久女の忌 東京 小山 蓮子
手を上げて春呼んでをり招き猫 青森 榊 せい子
人日の胃袋に似る水枕 宮城 小田島 渚
初旅の御礼参りや伊勢うどん 愛知 津田 卓
阿と吽の日がな一日老うらら 東京 田家 正好
遊び方忘れ八十路の夕永し 東京 竹内 洋平
ふるさとの富士が一番山笑ふ 兵庫 清水佳壽美
日脚伸ぶはちみつ色に街景色 埼玉 秋津 結
春遠からじ靴紐を新しく 東京 飛鳥 蘭
晩学の月日尊し草青む 宮城 有賀 稲香
大息を整へて追ふ初日の出 東京 有澤 志峯
太閤の苦労話も針供養 神奈川 有賀 理
喪の家の遺影を入れて初写真 東京 飯田 子貢
豆撒に隣家の人の声を知る 東京 生田 武
一椀に力をたのむ蜆汁 東京 市川 蘆舟
焚火の輪一会の温み分け合うて 埼玉 伊藤 庄平
孤高てふ象成したる黄水仙 東京 伊藤 政三
寒禽や三浦一族眠る浦 神奈川 伊東 岬
息災とだけの返信寒明くる 東京 今井 麦
急磴に二の音待ちたき初音かな 埼玉 今村 昌史
歩み出すまでの二三歩春寒し 東京 上田 裕
はじまりは紙の音なり春時雨 東京 宇志やまと
塗装屋の刷毛のいろいろ春隣 埼玉 大澤 静子
汐引かば島へつながる恵方道 東京 大住 光汪
白魚は梵字の如く煮えにけり 神奈川 太田 勝行
竹箒傾きしまま日脚伸ぶ 東京 大沼まり子
針納め仕立て直せし物を着て 神奈川 大野 里詩
寒明や手首に残る輪ゴム痕 埼玉 大野田井蛙
飴切りの春を呼ぶ音高らかに 東京 大溝 妙子
しんしんと春雪接種針並ぶ 東京 大山かげもと
紅梅の枝先はまだ咲き兼ねて 東京 岡城ひとみ
神木に光差し込む初詣 東京 小川 夏葉
残雪へスナックの灯の濃むらさき 埼玉 小野寺清人
息合はせ一枚紙の障子貼る 和歌山 笠原 祐子
梅三分どの枝となく香りけり 東京 梶山かおり
この森に鶯餅の雛の居る 愛媛 片山 一行
山焼く日消防隊の待機せり 静岡 金井 硯児
今誰も居らぬ部屋へも豆を撒く 東京 川島秋葉男
水仙や墓誌のまはりを突き上ぐる 長野 北澤 一伯
頬杖の当たる指先余寒かな 東京 絹田 稜
名にし負ふ久寿餅の香や初大師 東京 柊原 洋征
父の忌の夕映え梅の咲く頃か 神奈川 久坂衣里子
雪掻のしまひは大地叩く音 東京 朽木 直
寒の入ひなた探して人を待つ 東京 畔柳 海村
探梅の日向日向を伝ひゆく 東京 小泉 良子
顔見世の桟敷ばかりを見てしまふ 神奈川 こしだまほ
凍蝶の羽ばたき翅を砕くかに 東京 小林 美樹
餌台や鳥語辞書欲し初雀 宮城 齊藤 克之
侘助や見舞はぬといふお見舞も 長崎 坂口 晴子
待針は供花の如くや針供養 長野 坂下 昭
生涯をこの一枚の歌がるた 千葉 佐々木節子
来し方をあれこれ偲び毛糸編む 群馬 佐藤 栄子
ころころと転がる薬茂吉の忌 群馬 佐藤かずえ
これよりは一方通行魞を挿す 東京 島 織布
春泥のひよいとはゆかぬ齢かな 東京 島谷 高水
緋の衣八重にかさねて寒牡丹 埼玉 志村 昌
名残雪車窓隔てる眼と眼と眼 神奈川 白井八十八
春一番打ち付く絵馬の嘶けり 東京 白濱 武子
書初めの上手にどんどの火と上がれ 東京 新谷 房子
寒牡丹風あるはうに傾ぎけり 大阪 末永理恵子
落ちそうな空の暗さや節分会 静岡 杉本アツ子
焼け過ぎの頭真つ黒やいかがし 東京 鈴木 淳子
一輪の水仙活くる正座かな 東京 鈴木てる緒
雪降るや越後の濁り酒やよし 群馬 鈴木踏青子
箱の中中に箱あり春の夢 東京 角 佐穂子
響かせて谷のめざめの雪解どき 東京 瀬戸 紀恵
薄氷に時に濃くなる魚の影 神奈川 曽谷 晴子
下張りの俳句透けたる襖かな 長野 髙橋 初風
鶯や少し傾く子規の墓 東京 高橋 透水
被せ藁を踏み出すやうに冬牡丹 東京 武井まゆみ
回文や音に目覚むる宝船 神奈川 田嶋 壺中
御簾の奥のぞく心地も寒牡丹 東京 多田 悦子
春来るペンキの香る船溜り 東京 立崎ひかり
竜の玉冷気集めて青となす 東京 田中 敬子
相輪の届かぬ影や寒牡丹 東京 田中 道
店先に二階貸します枇杷の花 東京 塚本 一夫
遠くまで行かずとも佳き梅日和 東京 辻 隆夫
春立つや一息に抜くしつけ糸 東京 辻本 芙紗
鶯餅つまめば顔のあるごとく 東京 辻本 理恵
翻り際の鋭角冬の鳥 東京 坪井 研治
夕暮と夜の束の間の梅の白 埼玉 戸矢 一斗
御神籤はなべて小吉梅の花 千葉 長井 哲
隠国の初瀬の御灯寒牡丹 大阪 中島 凌雲
魞挿せば近江八景定まりぬ 神奈川 中野 堯司
お手玉は昔の色にひなたぼこ 東京 中野 智子
一日を旅として終へ春を待つ 東京 中村 孝哲
早梅や待てば日和とある神籤 茨城 中村 湖童
呼び鈴のいらへに間あり冬牡丹 埼玉 中村 宗男
羽搏きの鶴晴天へ嘴を突く 東京 中村 藍人
大寒や厨の壁の火廼要慎 千葉 中山 桐里
人の輪を炙り出したる大とんど 大阪 西田 鏡子
旧正の紅連なれる中華街 東京 西原 舞
気の張らぬ客ばかりなり豆の飯 東京 沼田 有希
(4月号延着分)
鷽替やほど良き嘘を手に収む 埼玉 萩原 陽里
枝に添ふ音符のやうに猫柳 埼玉 萩原 陽里
大寒の山彦山に籠りけり 東京 橋野 幸彦
男手の欲しき柊挿しにけり 広島 長谷川明子
いち早く咲きたる梅の蒼さかな 東京 長谷川千何子
豆を撒くひと振り小さき米寿の手 神奈川 原田さがみ
水涸れて池の鯉揚げ盛んなり 兵庫 播广 義春
初富士をもつたいなくも車窓から 東京 福永 新祇
去年今年主夫と化したる夫の居り 東京 福原 紅
富士裾の陽炎を踏む畷みち 東京 星野 淑子
春寒の風に走るや磯千鳥 神奈川 堀 備中
吉凶は神に委ねて初山河 岐阜 堀江 美州
相づちにきな粉くづして蕨餅 埼玉 本庄 康代
忍冬咲く挿し木をせしは雨の去年 東京 松浦 宗克
節分や豆粒ほどの声を撒き 東京 松代 展枝
冬夕焼八百八橋染め切れず 京都 三井 康有
荒川線でのんびり春の来たりけり 東京 宮内 孝子
家中がこの日のためと大試験 神奈川 宮本起代子
別れ悼むことの多さよ雪しづる 東京 村田 郁子
寒明や選りても捨てぬ古写真 東京 村田 重子
大寒の拳おほかたポケットに 東京 森 羽久衣
海鳴りのふいに間近し探梅行 千葉 森崎 森平
寒造醪の声を蔵の闇 埼玉 森濱 直之
庭の闇にも直球の鬼の豆 長野 守屋 明
磐座の光背として滝凍る 愛知 山口 輝久
目刺焼くしづかな夕でありにけり 群馬 山﨑ちづ子
香煙にまさる白息朝勤行 東京 山下 美佐
鬼やらひ五色の鬼の打ち揃ふ 東京 山田 茜
初漁の入船に舞ふ鳶かもめ 群馬 山田 礁
山なりのやさしき兄の雪つぶて 東京 山元 正規
達磨市香煙の香を運気とす 東京 渡辺 花穂
めらめらと登り竜めく大焚火 埼玉 渡辺 志水
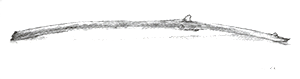



銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男・選
初比叡みえぬ灯に手を合はす 谷口いづみ
| 「初」に山を付ければ何でも季語になるわけではない。「初富士」「初筑波」「初比叡」の三つだと思っていた方が潔い。この句は京都の町中から手を合わせているようだ。眼目は「みえぬ灯に」。延暦寺根本中堂には不滅の法燈がある。開山以来絶えたことの無い灯火といわれる。一説には織田信長の焼討の折消えたが、以前に山形県の山寺に分けておいた灯火を戻して繫がっているという。町からは見えぬこの火を詠んだのが手柄。また伝教大師最澄の教えである「一隅を照らす」にも通じる、清浄感の漂う句となった |
探梅のみな良き顔をしてゐたる 堀切 克洋
| まだ咲いているかも解らない梅を求めて散策する一団。「みな良き顔をしてゐたる」に春を探す期待や、ささやかながら至福の楽しみが描かれている。同時出句の〈心配になるほど膨れ寒雀〉も、おかしみを湛えながらも対象物の実態をよく把握している。 |
水仙や故人予約のランドセル 小野寺一砂
| 気仙沼出身の作者であることを思うと、あの三月十一日の東日本大震災の惨禍の回想ではないかと思う。小学校に入学する子の祝に注文しておいたランドセルがあの災害の後に届いたのであろう。誰にどんな運命が襲ったのかは解らないが「故人予約」の言葉は重みがある。今年も被災の地に花を開く水仙が悲しい。 |
橋なくて花冷えの世へひきかへす 桂 信子
| 現実の風景なのか、幻視の世界の風景なのか、不思議な句である。「花冷えの世(・)」とあるので、根の国への道、三途の川の手前から現世に戻ったということであるかもしれない。濁世とはいえ、桜の咲く現世には楽しみも多い。花冷えもまた良いではないか。 |
一辺のみ使ふ暮しや春炬燵 我部 敬子
| 「一辺のみ」で一人暮しであることが解る実に上手い表現の句である。俳句はこまごま説明をしないで、一語で読み手を理解させることが要諦で、そこに腐心するのだが、この句は一つの手本となる表現がされていると思う。「春炬燵」の温か味の取合せもいい。 |
くづし字の寺請証文をんなの名 三溝 恵子
「寺請証文」の季語を使った句を初めて目にした。「踏絵」の副季語で、寺がキリシタン信徒ではなく檀徒であることを証明させた制度のことを言う。本人の署名が残っていたのであろうか。女の崩し書きの字の着目が手柄。
|
家系図のごとく並んで初写真 保田 貴子
| 三代か、あるいは四代か、一族打ち揃っての記念写真であるが、その並び方がまるで家系図のようだ、というのが独自の発想で斬新である。この発見が勝負所、勘所である。「家系図のやうに並んで」「家系図のままに並んで」「家系図の同じ並びに」……まあ、原句のままがいいかな。 |
遠くまで行かずとも佳き梅日 辻 隆夫
| 俳句の技法には様々あるが、この作者は欲張らずに淡々と日常を詠むところに持ち味があるようだ。力を入れず、目の届く範囲を穏やかに詠む。「遠くまで行かずとも佳き」の静けさと充足感がいい。 |
春の風邪ただの年波かも知れず 池田 桐人
寝込むには日差しの惜しき春の風邪 川島 紬
思ひ付くだけのわがまま春の風邪 白井 飛露
| いずれも「春の風邪」の本意をうまく捉えている。冬の風邪と違い深刻さが薄く、のどかな感じがある。また、うっかり者の雰囲気もある。桐人句は年のせいかもしれないとやや自虐的な詠み方。紬句は割合元気なのに寝ていることの口惜しさ。飛露句はこの際勝手気儘に過ごそうという奔放なおかしさ。各々持ち味を発揮した力作。 |
綾取りの川に戻りて久女の忌 小山 蓮子
| 「綾取り」は歳時記によって立項されていたり、しなかったりする。久女忌は一月二十一日。私は芭蕉他誰もがその忌日を知っている人物以外の忌日句には別の季語が重なっても構わないと思っている。この句は様々に形を変えて結局は一本の紐となってしまう綾取りと久女忌の取合せが微妙な均衡を保っているようだ。天才的な句を次々と繰り出した久女のイメージと繫がるようだ。 |
手を上げて春呼んでをり招き猫 榊 せい子
| 招き猫が春を呼ぶ、としたところに意表を突く面白さ、新鮮さがある。幸せや財貨でないのがいい。詠み手を朗らかにさせてくれる句である。 |
その他印象深かった句を次に
人日の胃袋に似る水枕 小田島 渚
初旅の御礼参りや伊勢うどん 津田 卓
阿と吽の日がな一日老うらら 田家 正好
遊び方忘れ八十路の夕永し 竹内 洋平
ふるさとの富士が一番山笑ふ 清水佳壽美
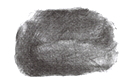





伊藤伊那男・選
秀逸
星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
鬼ごつこ鬼はどこかに春の暮 京都 秋保 櫻子
鶯を真似て返答損ねけり 東京 尼崎 沙羅
頰にふれる風や春とは名のみにて 愛媛 安藤 向山
銭湯に富士聳えたる初湯かな 東京 井川 敏
払暁に消えゆく星座春近し 長野 池内とほる
千句詠み一句残せと花菫 東京 石倉 俊紀
宍道湖のひとかたまりの蜆舟 広島 井上 幸三
諏訪人にあらねど待てる御神渡 長野 上野 三歩
北岳の白き温容春兆す 東京 上村健太郎
畑焼の匂ひ漂ふ梓川 長野 浦野 洋一
おれおまえ親しき仲の喧嘩独楽 東京 岡田 久男
換気扇逆流音の虎落笛 長野 岡村妃呂子
梅開花待たずに友は逝きにけり 神奈川 小坂 誠子
青空の青を取り込み崖氷柱 埼玉 小野 岩雄
草萌や地境の杭打ち直す 静岡 小野 無道
蕗味噌をなめて故郷の地酒かな 東京 桂 説子
膨らみて落つる点滴寒明くる 埼玉 加藤 且之
箒目の続く参道梅の花 東京 釜萢 達夫
雪のひまもらひ田畑ざわつきぬ 長野 唐沢 冬朱
明け暮れの真澄の声は寒鴉 愛知 河畑 達雄
母衣打ちの背なに確かな畦火かな 愛知 北浦 正弘
自転車の鍵穴固し冬の朝 長野 北出 靖彦
兄弟で足絡め合ふ春炬燵 群馬 木下 誠司
縁先からおとなふ声や春障子 東京 久保園和美
臘梅の蕩けてをりぬ雨の朝 東京 熊木 光代
節分の豆のおまけの鬼の面 東京 倉橋 茂
豆打ちの浅間に向ひ子等の声 群馬 黒岩伊知朗
死後のこと夫と語りて春炬燵 群馬 黒岩 清子
冬うらら神の榊はきらきらと 愛知 黒岩 宏行
春めくや日差し明るき目覚め時 東京 黒田イツ子
小魚は抜けてくれろと魞を挿す 東京 髙坂小太郎
村人の祈りにどんどいや高く 東京 小寺 一凡
去る鳥や梅の未熟を謗るかに 神奈川 阪井 忠太
針箱のすみに小銭や針供養 長野 桜井美津江
亡き猫の鳴き出しさうな春炬燵 東京 佐々木終吉
春の雪夫と足跡重ねけり 群馬 佐藤さゆり
握力を総動員の雪つぶて 東京 島谷 操
待春の山の息吹を待ち除染 東京 清水 旭峰
寒梅の蕾の尖り痛いほど 東京 清水美保子
スイートピー八十歳を寿がれ 千葉 清水 礼子
谷川の久々の晴れ残り雪 群馬 白石 欽二
草萌や合唱部員募るビラ 大阪 杉島 久江
竹林に春一番のうねり立つ 東京 須﨑 武雄
凍滝や時堰き止めて屹立す 岐阜 鈴木 春水
天使飛ぶステンドグラス春隣 埼玉 園部 恵夏
寒日和歩けば我が身軋む音 東京 田岡美也子
春の夢ふるさとの友あまたゐて 東京 髙城 愉楽
繕ひの仕事ばかりの供養針 福島 髙橋 双葉
麦踏の手を組むはうがふらつきぬ 埼玉 武井 康弘
下萌や子等に伝へる竹とんぼ 東京 竹花美代惠
家事ひとつふたつはづして春の風邪 東京 田中 真美
ものの芽は幼子の指天を指す 神奈川 多丸 朝子
街路樹の蕾膨らむ二月かな 愛知 塚田 寛子
一人居の卒寿春眠ほしいまま 広島 藤堂 暢子
風邪猛る待合室の膝送り 東京 中込 精二
囀やつい空見上げ影捜す 神奈川 長濱 泰子
刻々と木落し坂の春隣 長野 中山 中
耳鳴りの波も凪ぐ日や春立ちぬ 東京 永山 憂仔
国造り見下ろす岬夕霞 京都 仁井田麻利子
雪割の牛方宿や塩の道 東京 西 照雄
生へ変はるまつ毛は黒く梅香る 宮城 西岡 博子
蠟梅に乾ききつたる大地かな 東京 橋本 泰
初午や苞の団子の光たる 神奈川 花上 佐都
こちらは白紅はあちらに梅日和 千葉 針田 達行
炬燵には睡魔の住めり試験前 長野 樋本 霧帆
年男女難の相のまま撒けり 神奈川 日山 典子
鶯のまろき余韻を床に聴く 千葉 平山 凛語
冬菜畑男出て摘む夕日中 千葉 平野 梗華
書留を寝巻のままで春の風邪 千葉 深澤 淡悠
皺深き手に火消し棒山火燃ゆ 福岡 藤田 雅規
鎖たどり出世石段初詣 東京 牧野 睦子
急磴の一段ごとの梅見かな 東京 幕内美智子
春泥の長靴土間に散乱す 神奈川 松尾 守人
三絃の糸を替へたる夜半の春 東京 水野 正章
不意打ちに急拵への雪礫 東京 棟田 楽人
如月の闇を焦がして二月堂 東京 家治 祥夫
大寒やマリアに瑠璃の瞳あり 東京 矢野 安美
大寒の鰑嚙みしむ奥歯かな 東京 山口 一滴
アメ横の隅に積まれし目刺買ふ 群馬 山﨑 伸次
正月の色は紅白金添へて 神奈川 山田 丹晴
寒造二の腕太き杜氏かな 静岡 山室 樹一
山国の浅間の鬼へ鬼は外 群馬 横沢 宇内
高麗人の上陸の浦春の海 神奈川 横地 三旦
探梅とて知らぬ路地裏曲りゆく 神奈川 横山 渓泉
一歩二歩滑りつ歩む雪間かな 千葉 吉田 正克
正月の越後より来し行商女 山形 我妻 一男
利尻富士どかりと座り烏賊を釣る 東京 若林 泰吉
臘梅の一つ残らず日の当る 東京 渡辺 誠子





星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
二煎目に茶柱の立ち春隣 丸山真理子
私は起床と共に濃い緑茶を飲むのが日課だが、お茶パックに分包しているので、茶柱を久しく見ていない。たまに旅先の食堂などで見つけると嬉しいものだ。昔から茶柱は吉事の兆しとされている。茎の多い番茶が立ち易いようだ。この句は「二煎目」というところがいい。二番煎じという言葉があるように、眉唾物のようなおかしさを伴っている。ともかくもうすぐ春。ほのかな俳諧味がいい。同時出句の〈春めくや色鉛筆の削り屑〉も「春めくや」の季語を生かした色彩感のある秀逸。
|
凩の尽くる辺りか遠筑波 深津 博
高層ビルが林立している今では実感が無いが、江戸時代は富士山はもちろ
んだが、筑波山も町のどこからも大きく見えたという。深田久弥の日本百名山の中で標高の一番低い山だが、江戸庶民には親しみのある山で、その歴史を遡ってみると実感が深い。もちろん柴又辺りの土堤から見た今の実景としてもいい。同時出句の〈割に合はぬ長子と生れ冬田打つ〉も実感がある。中村草田男の〈蟾蜍長子家去る由もなし〉を易しく読み解いた感じである。 |
下萌や半ば埋もれし百度石 清水 史恵
| 「百度石」は心願成就のために、社寺の境内の標識の石を百度巡ること。時代劇などで見る。今やそうした信仰も廃れ、踏み固められていた道や石の周りも草叢になっているのであろう。時代の変遷と、芽吹きの力を合わせて読後の感慨が深い。同時出句の〈算盤も枡も現役種物屋〉も、今もある古い町の古い商家。「種物屋」の季語が効いた。 |
護符受くる雪解しづくの御堂より 塩田佐喜子
| 雪国の迎春の景が的確である。有馬朗人の〈光堂より一筋の雪解水〉と同じような新鮮な感覚がある。庇から落ち続ける雪解雫を避けながら受ける護符。雪から解放された人々の喜びが伝わってくる。 |
探梅の気が早すぎることいつも 荻野ゆ佑子
| 俳句は季節を先取りして詠む――という人もいる。春隣とか、夜の秋とかはそんな気持が出た季語なのであろう。探梅もそうで、冬なのにどこかに咲いていないだろうかと探し廻る心である。この句はそれにしてもあまりにも早すぎたか、今年もまた……と逸る心の出ている句だ。 |
秒針の音迫り来る大試験 北原美枝子
| 私ごとだが受験で一番厳しかったのは高校受験ではなかったかと思う。ともかく算数は植木算位で挫折しているので算数の試験では頭の中が白くなった記憶がある。大学受験は文科系数科目であるからむしろ楽であった。この句の秒針の音は脈拍とか、動悸とか、絶望感とかそんな記憶を蘇らせる。もう五十年以上前のことなのに。同時出句の〈日脚伸ぶ吾子の帰りもさらに伸ぶ〉も面白い構成だ。 |
かんざしに欲しき紅梅ありにけり 橋本 光子
| 梅の花は「花の兄」とも呼ばれ、桜に先駆けて咲く花である。平安初期までは中国文化の影響もあり、桜よりも梅が珍重されていた。この句の簪ならやはり紅梅の方が相応しそうだ。『源氏物語』にも禁苑の庭木として紅梅が描かれている。女性文芸の系譜の句である。 |
自問する自答に閊へ餅焦がす たなかまさこ
| 餅を焼く時は目が離せないので一点を見詰めていて、あれこれ考えることがある。あの時あの選択でよかったのかどうかなどと考えていて、結局焦がしてしまった、というところであろう。そんな様子が面白く捉えられている。 |
全山を水琴窟に雪解水 住山 春人
| 山そのものを大きな水琴窟と見立てた壮大な比喩の句である。この発想は多分類例が無く、手柄と言ってよかろう。俳句は人が見逃していた発見と発想が一番大事なこと。 |
春炬燵昔話に終り無く 北川 京子
| 春炬燵はただ寒さを凌ぐばかりではなく、心の弾みと安らぎもあるようだ。お伽話か思い出話か、尽きることが無い。春炬燵だからこその気分の出ている句だ。同時出句の〈時を積むやうに降るなり今日の雪〉も感慨深い仕上 |
女正月相槌打ちて居れば良く 内藤 明
| 正月に忙しかった女性を、一段落着いた一月十五日に労るのが「女正月」。正月の過ごし方や男女平等化などで消滅していく行事の一つとなった。この句はその日の男達の控え目な過ごし方を捉えた俳諧味の漂う句である。なお「めしょうがつ」と詠む人がいるが、この句のように上五に置いて「おんなしょうがつ」と詠みたい。 |
その他印象深かった句を次に
飼犬も加勢に吠ゆる追儺かな 伊藤 真紀
年表を手に鎌倉へ春立ちぬ 北爪 鳥閑
薪積みて鹿尾菜の口開け待つばかり 小池 天牛
淋しさは背中あはせに二月尽 馬場みち子






伊那男俳句 自句自解(76)
鳴く前の喉ふるはせて雨蛙
子供は残酷なもので、雨蛙を摑まえて、麦の茎で尻から息を吹き込んで腹を膨らませて遊んだものである。お玉杓子も蛙も身近な生き物であった。ただし牛蛙のような大物となると恐くて手が出せないから、弱いもの苛めであった。ともかくそのような生活の中で蛙の生態は見ていたことになる。この句はそうした思い出の回想句である。よく見ると蛙はいきなり鳴くのではなく、それなりの準備をしているのだ。一瞬のことであるが、幽かに喉を震わせるので「あっ鳴くな」と解るのである。と、今まことしやかに解説したのだが、思い出は混沌としていて、もしかしたら見てきたような嘘、というか思い込みであるのかもしれない。だが、きっとそうだと思わせる力は持っている句だと思う。一物仕立ての句というものは一つの対象物を十七音全部を使って一気に詠み下すので、信憑性が出てくるものである。実態の程は定かではないが、まずまずの句に成ったのである。
うたかたの世の片隅の缶ビール
七十二歳になるまでに、どれ程のビールを飲んできたことか。外人は「とりあえず」という銘柄のビールがあると思い込んでいるそうだが、私もまずは「ビール!」から始まる。一番好きな酒は日本酒だが、若い頃はビールをチェイサー替りにして並行に飲んでいたものだ。この句は人生の酸いも甘いも知ってきた頃の句である。癌の経験もし、会社は倒産状態となり、ビールの苦みも身に沁みるようになってきたのである。会社の整理に入ったころは、内部状況を外部に漏洩する輩ももり、緊張の解けない日々が続いた。家に帰ってそんな愚痴をこぼすのが嫌で、帰宅前に一人で酒を飲んで気持を落着かせることもあった。「缶ビール」を配したのは創作であるが、「うたかたの世の片隅」は当時の吾が身の実感である。振り返るとバブル劇場の端役を演じていたのであり、四十代後半で、まだ子育ての義務もあり、倒産後の身の振り方など、心細い思いをしていたのである。 |






更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。



リンクします。
aishi etc


挿絵が絵葉書になりました。
Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組
8枚一組 1,000円
ごあいさつにご利用下さい。




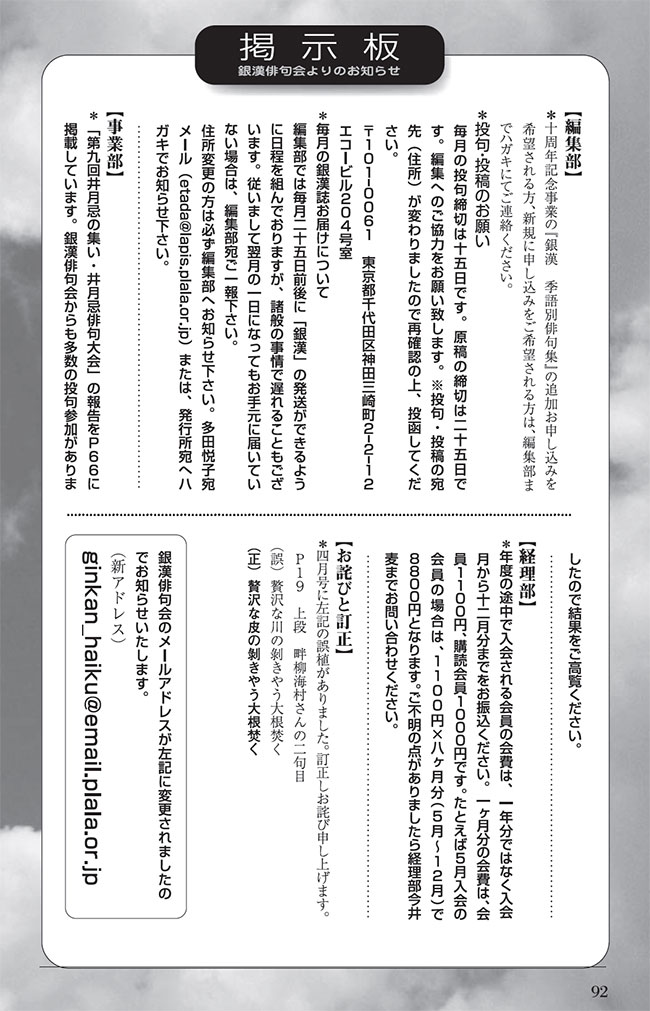



|
![]()
![]() 5月号 2022年
5月号 2022年 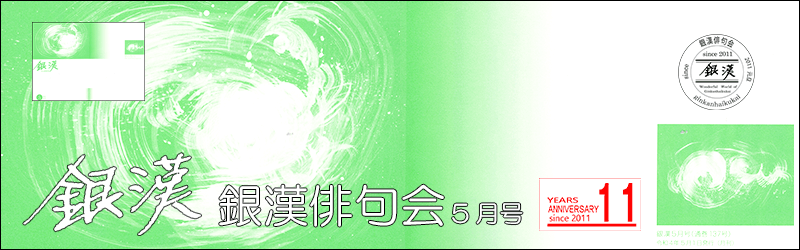
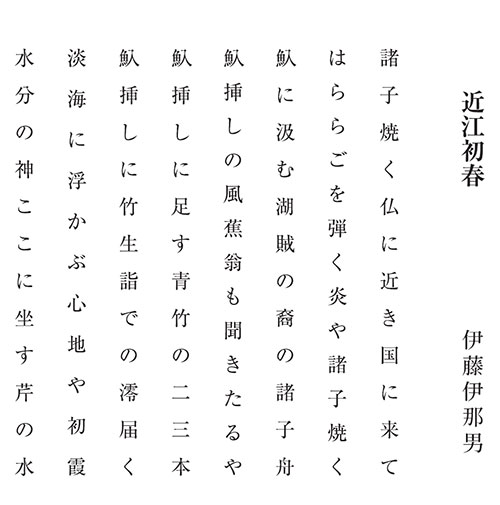
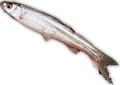

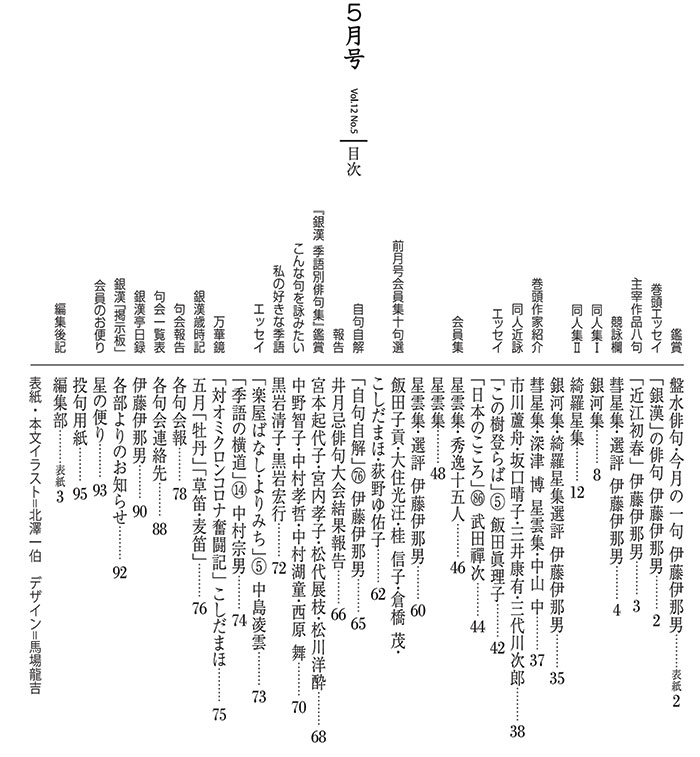

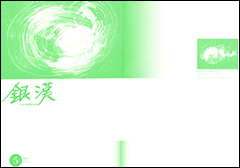


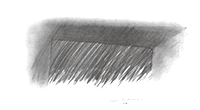







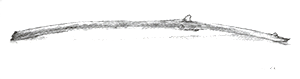


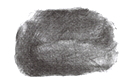



























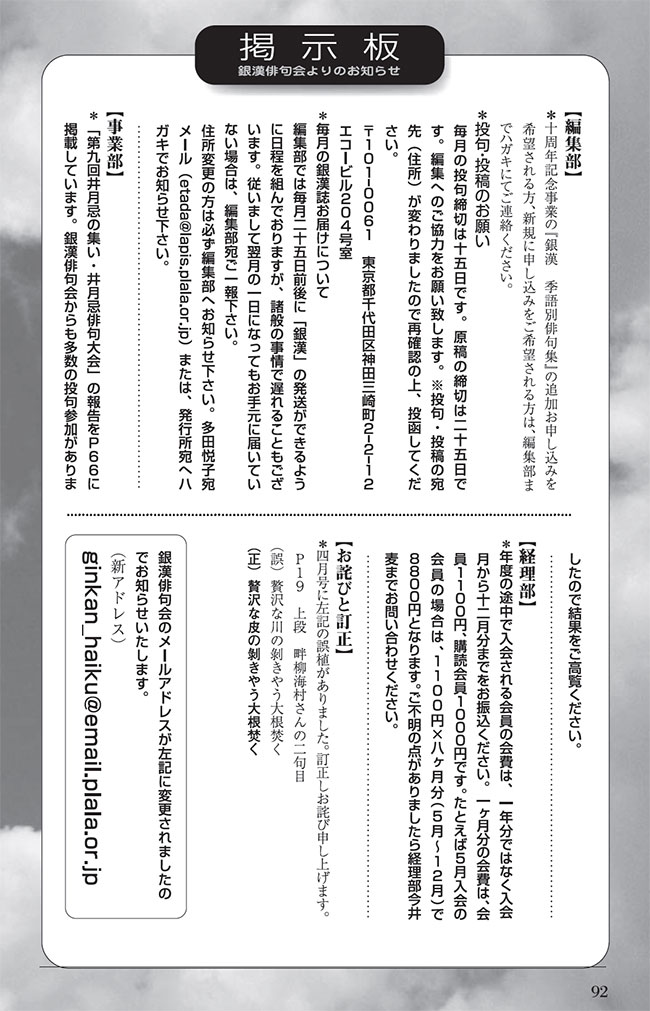


 26
26