


銀漢の俳句
伊藤伊那男
◎近江の車窓
近江が好きで若い頃から随分歩いた。渡来人の時代からずっと歴史の中心か、中心に近い土地である。それにもかかわらず滋賀県出身の作家姫野カオルコの『忍びの滋賀 いつも京都の日陰で』を読むと、滋賀の出身だと言うと、千葉? 佐賀? と聞かれ、酷いのになると信州の志賀高原と間違えられる。新幹線で通過しても知らない県、最も忘れられている県の第一位だという。旅行会社のパンフレットでも「京都と琵琶湖の旅」や「京都と比叡山の旅」はあるが、たいがい京都との抱き合わせで単独の「滋賀の旅」は皆無だという。琵琶湖も比叡山延暦寺も実は滋賀県のものなのに……と嘆く。確かに国宝重要文化財の数は日本有数なのだが。
さて私は関ヶ原を過ぎ、新幹線の車窓に伊吹山が現われる頃から目を離せないでいる。伊吹山は「日本百名山」の中では筑波山に次いで低い山だが、日本海の寒気が直撃するので気象は荒い。日本武尊もこの山の神の霊気に屈服したのである。米原駅を過ぎる頃、目を凝らすと彦根城の天守閣が見える筈だ。〈鮒ずしや彦根が城に雲かかる 蕪村〉。その後方に琵琶湖があり、その奥に衝立のように比良山系が横たわる。すぐ目の前には石田三成の居城であった佐和山城址がある。少し進むと近江商人を輩出した五個荘があり、反対側に佐々木源氏発祥の地、六角氏の居城である観音山があり、向かいに安土城址がある。〈城瓜やここにし安土セミナリオ 森澄雄〉。ここを過ぎると豊臣秀次の居城があった近江八幡山があり、山頂へのケーブルカーの軌道も解る。次の平野が蒲生野で、大津京時代に詠まれた天智天皇の妃の額田王と天智天皇の弟、大海人皇子(後の天武天皇)の相聞歌〈あかねさす紫野ゆき標野ゆき野守はみずや君が袖ふる〉〈紫草のにほへる妹を憎くあらば人妻ゆゑに我恋ひめやも〉の舞台である。近江富士と呼ばれる端正な容の三上山は俵藤太の百足退治で知られる。そうこうしていると壬申の乱を始め、数々の攻防戦のあった要衝、瀬田の唐橋を過ぎて大津市に入る。源義仲が討たれた粟津野の反対側には芭蕉が滞在した幻住庵のあった小山がある。〈先づ頼む椎の木も有り夏木立 芭蕉〉。なお義仲と芭蕉の眠る義仲寺は比叡山が眼前に迫る辺りにあるが、新幹線はその直前からトンネルに入り、抜けるとそこはもう京都市山科区となる。
米原駅から京都駅まで、新幹線ひかり号の所要時間は十九分間と短く、缶ビールを飲む間も無いほどである。私は新幹線に乗るたびにこの十九分間に気が抜けないのである。
|





盤水俳句・今月の一句
伊藤伊那男
紅梅の満開の艶真砂女逝く 皆川 盤水
| 真砂女逝去は平成十五年三月十四日。享年九十六。九十二歳で蛇笏賞受賞。その授賞式に私も出席した。車椅子で来て、手を引かれて壇に上ったが「昔は男によろめいたけれど今はこんな階段によろめいちゃって……」と笑わせた。この日の着物について「お祝いに匿名の方から着物が届いて、おやっ、どの男かしら、と思っていたら瀬戸内寂聴さんだったのよ」と。見事な年の取り方だ。春耕の祝賀会に駆け付けてくれたのも懐かしい。(平成十五年作『花遊集』所収) |



彗星集作品抄
伊藤伊那男・選
いつ見ても逆光冬の煙突は 朽木 直
母よりも叔母思ひ出す近松忌 上村健太郎
鰭酒のつぎ酒のごとき余生かな 北爪 鳥閑
煤払一日埃の仏かな 清水佳壽美
母の死を短くしるし日記果つ 小野寺清人
薬喰生きむためより死なぬため 小野寺一砂
まちまちに灯す元町クリスマス 島 織布
冬来る列車の走り去る音に 長谷川明子
日向さへ寄辺無きかな冬の蝶 三井 康有
一枚のはがきの重し冬の雨 松浦 宗克
冬ひばり嬥歌の山は晴れ渡り 武井まゆみ
奥能登の道の詰まりて波の花 久保園和美
神事前鹿遠巻きの大焚火 塩田佐喜子
極月の芥も浮かべ神田川 福永 新祇
千両も万両も殖ゆ蔵屋敷 大野 里詩
易々と口を割らぬも寒蜆 中島 凌雲
ぼろ市に素通りできぬロレックス 多田 悦子
年の煤仏陀に涙らしき跡 萩原 陽里
またひとつ消える湯屋の灯一葉忌 本庄 康代




|
伊藤伊那男・選
いつ見ても逆光冬の煙突は 朽木 直
| 当然逆光ばかりではないはずだが、「いつ見ても」と言い切ったことで成功した句と言ってよかろう。冬は日差しを求める気持が強いせいか逆光の風景が目立つのである。逆光の中に黒々と立つ煙突が冬の象徴のようにも思われてくる。それにしても一昔前のような工場の煉瓦造りの煙突は見られなくなったし、銭湯の数も減ってしまった。そういえば東京千住のおばけ煙突などももう遠い昔のものとなった。 |
母よりも叔母思ひ出す近松忌 上村健太郎
| 近松門左衛門は江戸中期の浄瑠璃、歌舞伎の脚本作家。『出世景清』『国性爺合戦』の他、義理人情の絡んだ心中物『曾根崎心中』『心中天網島』『女殺油地獄』など、今に残る作品を発表した。忌日は陰暦十一月二十二日。この句はその忌日と聞いて、ふと母ではなく叔母のことを思い出したという。叔母であるから母の妹であるが、多分美貌で艶聞を残した人なのであろう。色々なことを読み手に想像させる良質の人事句であった。 |
鰭酒のつぎ酒のごとき余生かな 北爪 鳥閑
| 鰭酒は一杯目はほどよく色が出たところで、鰭を取り出しておく。つぎ酒は二杯目の熱燗で、鰭を戻してつぐ。この二番煎じを余生のようだ、二度目の人生のようだというのだから、常識では思い付かない特異な比喩である。私見だが、つぎ酒であともう一回、計三回まではいける。人生もまだまだ、ということだ。余談だが、鰭は焦がし過ぎかなと思う位まで焼くのがいい。 |
煤払一日埃の仏かな 清水佳壽美
| 煤払は、先ずは長い竹箒などで天井や梁の掃除から始めるので、その埃が仏像にかかってしまう。そのことを詠んでいるのである。大寺であれば二日がかりということもあろうし、仏像が一年で一番埃を浴びる日でもあるということであろう。面白い角度から見た煤払である。 |
母の死を短くしるし日記果つ 小野寺清人
| 「短くしるし」というけれど決して疎かにしているのではない。むしろ短くしか書けない、というところに嘆きの深さがあることが読み手に伝わるのである。思い出の多さ、悲しみの深さは字の数に比例するものではないのだ。その余白、行間にこそ滲み出てくるものなのであろう。 |
薬喰生きむためより死なぬため 小野寺一砂
| やや常套的な言い回しだが、薬喰の季語で生きている句である。たとえばもう肉などを欲しがらない親に勧めている場面などを想像すると、話し言葉のようにも聞こえてくるのである。 |
まちまちに灯す元町クリスマス 島 織布
冬来る列車の走り去る音に 長谷川明子
日向さへ寄辺無きかな冬の蝶 三井 康有
一枚のはがきの重し冬の雨 松浦 宗克
冬ひばり嬥歌の山は晴れ渡り 武井まゆみ
| たまさかの冬の暖かな一日か。筑波山麓が目に浮かぶ。 |
奥能登の道の詰まりて波の花 久保園和美
極月の芥も浮かべ神田川 福永 新祇
千両も万両も殖ゆ蔵屋敷 大野 里詩
易々と口を割らぬも寒蜆 中島 凌雲
ぼろ市に素通りできぬロレックス 多田 悦子
年の煤仏陀に涙らしき跡 萩原 陽里
| 煤掃きで目近かにした仏陀。涙らしきに味わいがある。 |
またひとつ消える湯屋の灯一葉忌 本庄 康代


|


銀河集作品抄
伊藤伊那男・選
対馬・壱岐
外敵に矢面の島寒夕焼 東京 飯田眞理子
辻々に火の粉舞ひ立つ酉の市 静岡 唐沢 静男
火の山の影は枯野に移りけり 群馬 柴山つぐ子
湖心まだ残照に映え鴨雑炊 東京 杉阪 大和
大根焚てふ有難き寄り道も 東京 武田 花果
色の無き石庭の渦冬日波 東京 武田 禪次
笛吹きのふしくれの指里神楽 埼玉 多田 美記
逆立てしこともありしが木の葉髪 東京 谷岡 健彦
小津映画にありさうな家八手咲く 神奈川 谷口いづみ
蔵壁の音よく返す鵙日和 長野 萩原 空木
おでん種迷ふ不惑を前にして 東京 堀切 克洋
今朝散りてゐたるきのふの帰り花 東京 松川 洋酔
奥の細道むすびの地
行く秋の雲を見るかに翁像 東京 三代川次郎

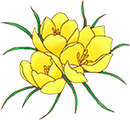



伊藤伊那男・選
しぐるるや秩父のみやげみな重し 東京 小泉 良子
息白きほどには物を言へずをり 東京 飛鳥 蘭
榾足して満蒙の悲話語り継ぐ 長野 坂下 昭
俎板の表も裏も師走なり 東京 宇志やまと
紀捲るやうな熊野の旅始 埼玉 戸矢 一斗
蛤になる仲間外れの雀 広島 長谷川明子
一粒が大きと思ふ風邪の粥 神奈川 原田さがみ
箒目の踏まれし跡や神迎 東京 山下 美佐
冬鷗浚渫船をつかみさう 東京 飯田 子貢
宴席の隣は無口海鼠食ふ 東京 生田 武
倒れぐせ直す冬菊声を添へ 東京 大山かげもと
小春日や猿のズボンの穴から尾 千葉 白井 飛露
打たるるを待つといふのも冬の蠅 長野 北澤 一伯
鳶の輪の松は定点冬日和 東京 市川 蘆舟
雑用の雑には出来ぬ年用意 神奈川 大野 里詩
直実の像に泪の時雨かな 大阪 末永理恵子
隙間風手で戸を閉める飯田線 長野 守屋 明
雑炊を温めるだけ妻の留守 埼玉 渡辺 志水
晩歳を生きよ学べよ万年青の実 宮城 有賀 稲香
木の葉散る木の葉の影を重ねつつ 東京 有澤 志峯
日記買ふ忘れ上手を身につけて 神奈川 有賀 理
職探す子にも勤労感謝の日 埼玉 池田 桐人
継がぬ田の風に冬帽飛ばさるる 埼玉 伊藤 庄平
嚙み切れぬ一片のある海鼠かな 東京 伊藤 政
編み掛けのままのセーター三回忌 神奈川 伊東 岬
落柿舎に蓑笠は古り初時雨 東京 今井 麦
社会鍋古書肆の釣りを音立てて 埼玉 今村 昌史
牛頭馬頭を詣で小春の山日和 東京 上田 裕
神々の山たたなはる寒夕焼 埼玉 大澤 静子
冬ざるる灯る一戸の大間崎 神奈川 太田 勝行
山茶花の散るを急かるる花の数 東京 大沼まり子
父から子代はる担ぎ手熊手市 埼玉 大野田井蛙
ぼろ市や客のあるなしこだはらず 東京 大溝 妙子
塵取に入りたがらぬ朴落葉 東京 岡城ひとみ
平凡に暮らす一日や大根煮る 東京 小川 夏葉
日短や本題らしき追伸が 愛知 荻野ゆ佑子
黒紐に綴ぢる書類や火事とほし 宮城 小田島 渚
国粋の国酔となり憂国忌 宮城 小野寺一砂
船縁の烏賊の墨拭く雪催 埼玉 小野寺清人
見開きの子規が横向く漱石忌 和歌山 笠原 祐子
着ぶくれてせめてバックは小さめに 東京 梶山かおり
捨案山子斜めに空を仰ぎをり 愛媛 片山 一行
大釜の木蓋押し上げ大根焚き 静岡 金井 硯児
望郷の一刻籠の蜜柑食ぶ 東京 我部 敬子
時雨るるや猟銃包む油紙 東京 川島秋葉男
梟の森の吐息のやうに鳴く 千葉 川島 紬
亥の子突記憶の底に音のあり 神奈川 河村 啓
落ち椿老いのひと花咲かせゐる 愛知 北浦 正弘
餅搗の臼の木目の粗さかな 東京 絹田 稜
小春日や一遍像は前のめり 東京 柊原 洋征
帰り花唐招提寺の水面にも 神奈川 久坂衣里子
しぐるるや翁罷りし時もやと 東京 朽木 直
炬燵出す合はせて無精てふものも 東京 畔柳 海村
常の店つねの社名の大熊手 神奈川 こしだまほ
水煙の飛天の舞や初時雨 東京 小山 蓮子
神棚へ小鮒供へて恵比須講 宮城 齊藤 克之
雪催煮含めるもの面を取り 青森 榊 せい子
解くほどに絡まる紐や十二月 長崎 坂口 晴子
擦れ違ふ墨の香仄と秋遍路 群馬 佐藤 栄子
定まらぬ未来でも良し日記買ふ 群馬 佐藤かずえ
阿弥陀像膝の木目に冬日差す 長野 三溝 恵子
茶の花や石に刻みし葷酒不許 広島 塩田佐喜子
渡し守ゐし頃よりの都鳥 東京 島 織布
落葉掃く箒の長さ使ひ切り 東京 島谷 高水
鳰浮き出るまでは立ち去れず 兵庫 清水佳壽美
熱燗やふるさと棄てて来たる夫 東京 清水 史恵
笹鳴や竹箒の手休めをり 東京 清水美保子
杵の先軒より高く餅を搗く 埼玉 志村 昌
音も無く地軸を戻す冬至かな 神奈川 白井八十八
神木の銀杏落葉は紙垂のやう 東京 白濱 武子
浅間山雪の便りや亜浪の忌 東京 新谷 房子
ショーウィンドーの中は暖色冬に入る 東京 鈴木 淳子
小春日を存分に浴び母逝けり 東京 鈴木てる緒
積りたる落葉の温し掃かずおく 群馬 鈴木踏青子
坂一つ曲りてまたも時雨けり 東京 角 佐穂子
寒柝の音に居住まひ正しけり 東京 瀬戸 紀恵
襤褸市の羽織の鷲の睨みたる 神奈川 曽谷 晴子
これ以上吹けば無粋な虎落笛 長野 髙橋 初風
晩学や昌平坂に帰り花 東京 高橋 透水
松手入足場の枝をみきはめて 東京 武井まゆみ
鴨の水脈番の水脈に重なれり 東京 竹内 洋平
立ち話すこし長引く小春かな 神奈川 田嶋 壺中
小春日や熊野にかつて渡海船 東京 多田 悦子
手水鉢動かぬ落葉底にあり 東京 立崎ひかり
履けぬほど大き靴下子の聖夜 東京 田中 敬子
猟犬の血筋を守る熊野かな 東京 田中 道
全集の足らぬ一冊漱石忌 東京 田家 正好
ポン菓子の来し路地裏の花八手 東京 塚本 一夫
伊吹嶺に雲の集まる冬隣 東京 辻 隆夫
知らぬ間に止まる目覚し神の留守 東京 辻本 芙紗
やはらかくふくろふは背をむけしまゝ 東京 辻本 理恵
嵩減りて切干の香の匂ひ立つ 愛知 津田 卓
柿落葉ルルドマリアの祈る手に 東京 坪井 研治
剝製の鹿と眼の合ふ冬座敷 千葉 長井 哲
酢海鼠の潮を噴くかの嚙みごたへ 大阪 中島 凌雲
セーターの一編みごとの日のぬくみ 神奈川 中野 堯司
息災の感謝を喜捨に社会鍋 東京 中野 智子
憂愁の化身のごとき海鼠かな 東京 中村 孝哲
縋りつき遊びせんとやゐのこづち 茨城 中村 湖童
定年の日の夢勤労感謝の日 埼玉 中村 宗男
八百万の神神その他神の留守 東京 中村 藍人
間をもたせ代り代りに初電話 長野 中山 中
掌に余る鈴緒も七五三 千葉 中山 桐里
藪漕ぎの熊笹匂ふ神の留守 大阪 西田 鏡子
気がつけば長老の座や山笑ふ 東京 沼田 有希
榾木焼べ津軽三味線撥激し 埼玉 萩原 陽里
風紋の変はる一瞬神の旅 東京 橋野 幸彦
背なに知り足裏に知る小春かな 東京 長谷川千何子
水脈に沿ひ細長くなる鴨の陣 兵庫 播广 義春
退きて仰ぐ神木天高し 東京 半田けい子
ゴルフ場抱へて山の寝そびれし 埼玉 深津 博
冬ぬくし踊り出しさう一遍像 東京 福永 新祇
労らるる老いも良きかな根深汁 東京 福原 紅
反論の返らぬ今朝の寒さかな 東京 星野 淑子
畝に鍬嚙まししままや小春凪 岐阜 堀江 美州
瀬戸際で手招きしたる風邪の神 埼玉 本庄 康代
落葉掃く背に落葉のとぎれなし 東京 松浦 宗克
空白は平穏な日々古日記 東京 松代 展枝
黒谷の坂を一気に十夜婆 神奈川 三井 康有
眠る山へ子守唄めく鳶の笛 東京 宮内 孝子
夢の色含みて丸き毛糸玉 神奈川 宮本起代子
訃報手に戸惑ひ仰ぐ冬銀河 東京 村田 郁子
古暦母の忌日の残りをり 東京 村田 重子
肘胼胝に触るるペン胼胝懐手 東京 森 羽久衣
悟り顔して梟の鉄の爪 千葉 森崎 森平
毛糸編む陽だまりの香を含ませて 埼玉 森濱 直之
茶の花の香りぞ通るにじり口 東京 矢野 安美
短日や目薬頰を伝ひ落つ 愛知 山口 輝久
いつか来たこの道に居て暮早し 群馬 山﨑ちづ子
青首の高さ違へて大根畑 東京 山田 茜
初冬や日の淡ければ影もまた 東京 山元 正規
法隆寺の鐘空耳に熟柿吸ふ 東京 渡辺 花穂



 


銀河集・綺羅星今月の秀句
伊藤伊那男・選
しぐるるや秩父のみやげみな重し 小泉 良子
| 師の皆川盤水が秩父を好きであったことに触発されて、若い頃から随分秩父を訪ねた。この句のように、秩父の土産は確かに重いのである。杓子菜漬をはじめとする漬物の数々。蒟蒻、おっきりこみの麵、豚肉の味噌漬……どれもみな重いのである。こんな所に目が行ったのは面白い。 |
息白きほどには物を言へずをり 飛鳥 蘭
| 確かに、駆け寄ってきた子供など、顔が隠れてしまうほどの白息に包まれていて、それに較べると言葉は少ない。白息の中だからこそ、その対比によって感じるのであり、日常生活の些事の中からの発見の句である。 |
榾足して満蒙の悲話語り継ぐ 坂下 昭
| 戦前、満蒙の地を王道楽土と謳って多くの開拓民を送り込んだ。信州からも随分大勢が大陸に渡ったのである。結局戦争に負けて着の身着のまま日本に戻り、また山間地の開拓地に入植するという悲しい歴史があった。小学校の頃、その子供さんと同級生であった。家は山峡の掘立小屋で、小学校の途中でどこかに転校した。悲しい歴史である。 |
俎板の表も裏も師走なり 宇志やまと
| 師走の師とは僧のことを言ったようであるが、町中が忙しい時期である。この句では人ばかりではなく、俎板も忙しいとしたところが眼目である。次々に作らねばならない料理に俎板の両面を使う。珍しい角度で詠んだ師走である。 |
記紀捲るやうな熊野の旅始 戸矢 一斗
| 熊野は神々の存在を間近に感じる土地である。火山活動の造形による奇抜な地勢も神々しさを感じさせるのである。神武天皇は最終的に熊野側から大和に攻め入ったのである。この句は初旅の熊野で「記紀捲るやう」に神話の世界に入り込んでいくのである。 |
蛤になる仲間外れの雀 長谷川明子
| 七・七・三のリズムの破調の句であるが、合計十七音に納まっている。七十二候の一つ「雀蛤になる」は寒露の頃雀が少なくなるのは、海に入って蛤になるからだ、という解釈。作句するには言葉遊びの能力を試される季語であるが、これは逆を突いた詠み方で、類例の無い成功例。 |
一粒が大きと思ふ風邪の粥 原田さがみ
| 風邪で寝込んでいる時の心理状態がよく出ている句だ。粥になった米の粒までが大きく見えるという。少し気弱になった心が投影しているのであろうが、風邪を詠んで、今までに目にしたことの無い、実感のある句であった。 |
箒目の踏まれし跡や神迎 山下 美佐
「踏まれし跡」が謎めいている。神迎であるから、戻ってきた神の足跡であるのかも知れない。そんな興味を起こさせる楽しい句であった。
|
冬鷗浚渫船をつかみさう 飯田 子貢
| 隅田川辺りを往き来する浚渫船であろう。冬鷗が船に纏わりついているのだが、その様子を「つかみさう」と捉えたのは手柄である。有り得ない事なのだが、もしかしたら……と思わせるのは技倆。言葉の力である。 |
宴席の隣は無口海鼠食ふ 生田 武
| 入れ込みの席で、宴会の集まりもあれば一、二人の客もいる。酢海鼠を肴に酒を飲んでいるのである。そこだけが静かなのである。いかにも海鼠が効いて孤愁を深めている。 |
倒れぐせ直す冬菊声を添へ 大山かげもと
| 咲き残った冬菊を労る気持のよく出ている句だ。「倒れぐせ」とあるから時々手を掛けていることが解る。「声を添へ」に凜と生きているものへの哀惜の情が籠められている。 |
小春日や猿のズボンの穴から尾 白井 飛露
| 一読笑ってしまう句だ。確かに猿廻しの猿は衣装を着けていて尻尾が出ているのである。つまり当り前なのだ。その当り前の事を詠んでいて、実は誰も目を付けていなかったという隙を突いたところが可笑しいのである。 |
打たるるを待つといふのも冬の蠅 北澤 一伯
村上鬼城に〈冬蜂の死にどころなく歩きけり〉がある。掲出句はもはや動くこともなく、抵抗することもなく、ただ打たれることを待っているようだという。鬼城句にしてもこの句にしても蜂や蠅を詠みながら人の世の寓意にも感じさせる深みを持つのである。
|
その他印象深かった句を次に
鳶の輪の松は定点冬日和 市川 蘆舟
雑用の雑には出来ぬ年用意 大野 里詩
直実の像に泪の時雨かな 末永理恵子
隙間風手で戸を閉める飯田線 守屋 明
雑炊を温めるだけ妻の留守 渡辺 志水





伊藤伊那男・選
秀逸
短日や缶蹴りの缶もう見えぬ 岐阜 鈴木 春水
はらわたを抜かれ芯無き海鼠かな 東京 丸山真理子
クッキーの缶の針箱日脚伸ぶ 東京 尼崎 沙羅
まづ医者に厚着をわびて聴診器 東京 中込 精二
嫌な事柚子湯の湯気となりしかな 東京 北原美枝子
会津紙の活字纏ひし餅届く 千葉 園部あづき
うたた寝の肘のかくんと神の留守 千葉 小森みゆき
大根焚にはか信徒の大食らひ 東京 髙城 愉楽
塵取りをはみ出してゐる朴落葉 東京 橋本 泰
冬木立見るも身軽な一遍像 神奈川 北爪 鳥閑
短日や朝刊追つて夕刊来 愛知 河畑 達雄
水軍の磯に隠れし海鼠獲る 神奈川 日山 典子
日に一つ良き事入れむ新日記 長野 桜井美津江
思ひでの数多みつかる煤払 東京 桂 説子
海底の難破船とも海鼠かな 東京 西田有希子
雲一つ見る想ひにも十二月 長野 唐沢 冬朱
鍋焼の蓋取り蓋を持て余す 東京 野口 光枝
寒の雨石庭の石孤高なり 千葉 吉田 正克

星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
冬ざれや川に鴉の鳴き交す 愛媛 安藤 向山
瀬戸の潮苦汁につかふ新豆腐 東京 井川 敏
思案して結局同じ日記買ふ 長野 池内とほる
悪意なき類句類想獺祭忌 東京 石倉 俊紀
凩に煽り煽られペダル漕ぐ 東京 一政 輪太
枯蘆や幻に聴く笛の音 東京 伊藤 真紀
大根の輪切り干さるる匂かな 広島 井上 幸三
そばへ来てすべて紅葉を奪ひけり 愛媛 岩本 青山
手の温み日差しの温み吊し柿 長野 上野 三歩
始発より冬田を窓の飯田線 東京 上村健太郎
晦日蕎麦信濃の酒に夜明け前 長野 浦野 洋一
盆路を夫訪ね来る風の音 神奈川 小坂 誠子
雪吊の心棒先づは天に挿し 静岡 小野 無道
尾を上げて助走に入る雉子かな 群馬 小野田静江
銭湯のいつになく混む冬至かな 埼玉 加藤 且之
山眠る故山に母の墓残し 東京 釜萢 達夫
始めから終りまで雨一茶の忌 群馬 北川 京子
思ひ出し笑ひ幾つか毛糸編む 東京 久保園和美
冬夕焼引込線に入る車輌 東京 熊木 光代
おでん屋の屋台飛び交ふ人生訓 東京 倉橋 茂
雪吊の縄の数だけ竹の杭 群馬 黒岩伊知朗
いとをかし仏間に聖樹ああ日本 群馬 黒岩 清子
仏壇の来光となり冬日差す 愛知 黒岩 宏行
落葉掃く作務衣泣かせのつむじ風 東京 黒田イツ子
友来る熊の肉提げ丹後より 神奈川 小池 天牛
虎落笛流行り病の喉が変 東京 髙坂小太郎
七五三お札納めに通りやんせ 東京 小寺 一凡
感慨の辿り着きたる冬山河 神奈川 阪井 忠太
日記買ふ三日坊主にならぬやう 東京 佐々木終吉
しばらくは一人の時間暖炉燃ゆ 群馬 佐藤さゆり
休めてふ雨の勤労感謝の日 東京 島谷 操
福島の汚染槽脇冬萌も 東京 清水 旭峰
曇り後薄曇り後紅葉晴 千葉 清水 礼子
暗き道北風切つて配達す 群馬 白石 欽二
老い猫の老いの淑気の髭の先 大阪 杉島 久江
城崎の宿の重ね着外湯かな 東京 須﨑 武雄
鷹匠の腕に残る爪の跡 愛知 住山 春人
煮凝や鰈崩れず鍋底に 東京 関根 正義
白旗神社界隈
弁慶塚護る枯木も立往生 埼玉 園部 恵夏
帰り花日差しを芯に蓄へし 東京 田岡美也子
雪催夕支度にはまだ早し 福島 髙橋 双葉
霜柱歩く後から光りをり 埼玉 武井 康弘
身にほしき翅の軽さよ年暮るる 東京 竹花美代惠
男体山風のさゝくれ猟期来る 栃木 たなかまさこ
灰色の重たき空や懐手 東京 田中 真美
いつ見てもドラマの主婦は葱をさげ 広島 藤堂 暢子
ボロ市の値切り値切られ笑顔かな 埼玉 内藤 明
植木屋の鋏高鳴る年の暮 神奈川 長濱 泰子
秋祭雲跳ね返す大漁旗 京都 仁井田麻利子
噴煙を望む駅舎や冬木の芽 東京 西 照雄
翻車魚の悠然と浮き冬ぬくし 宮城 西岡 博子
ベネチアの露店に求む皮手套 神奈川 西本 萌
老猫の死もありにけり年送る 静岡 橋本 光子
豊作に柿も軒並み熟し落つ 神奈川 花上 佐都
かの月のまま掛かりをる古暦 千葉 針田 達行
ふいに飛び紙片と思ふ冬の蝶 千葉 平野 梗華
冬晴や味醂の町の一茶庵 千葉 深澤 淡悠
冬の雲三度四度色替へ暮るる 長野 藤井 法子
権禰宜のほつと一息三の酉 福岡 藤田 雅規
忙しなき虫の出入りや花八手 東京 牧野 睦子
ストーブに大鍋据ゑて子らを待つ 東京 幕内美智子
落葉にもあり生きざまのやうなもの 神奈川 松尾 守人
日向ぼこ膝に猫とはありきたり 愛知 箕浦甫佐子
桟橋に繕ふ網や小春凪 東京 棟田 楽人
煮凝の鯛の目玉が睨みをり 宮城 村上セイ子
寒茜空にくすぶる熾火とも 東京 家治 祥夫
狩人の軒端に晒す猪の骨 東京 山口 一滴
また一つ灯る街灯暮早し 群馬 山﨑 伸次
冬麗西武と東武乗り比べ 神奈川 山田 丹晴
干し竿の二本で足りぬ小春かな 静岡 山室 樹一
一献の酒を温めて翁の忌 群馬 横沢 宇内
爪を切る冬日に拡げ新聞紙 神奈川 横地 三旦
冬の蝶昨日召されし君かとも 神奈川 横山 渓泉
大杉の中の伽藍の寒さかな 山形 我妻 一男
千歳飴腕に余り引き摺れり 東京 若林 若干
単身もこれが三度目年惜しむ 神奈川 渡邊 憲二
万葉の夢を現に鹿とをり 東京 渡辺 誠子





星雲集 今月の秀句
伊藤伊那男
短日や缶蹴りの缶もう見えぬ 鈴木 春水
| 缶蹴りなどという遊びは今や消滅しているのであるから、回想の句ということになる。戦後の昭和三十年中頃までは金のかかる遊びなどというものは皆無であった。その頃を懐かしく思い出させる句である。塾などというものもほとんど無かったから、学校が終れば、夕飯に呼ばれるまで外で遊ぶだけである。こんな遊びでも楽しくて、あっという間に日暮れになったものである。子供は風の子で寒空の下でも外を走り廻っていたのである。同時出句の〈湯ざめしてまた温泉に戻りをり〉はほのかな可笑しさも持つ。 |
はらわたを抜かれ芯無き海鼠かな 丸山真理子
| 能登半島に行くと、海鼠の腸を塩辛にした海鼠腸(このわた)がある。貴重品である。また海鼠子(このこ)といって卵巣だけを抜いて干したものはもっと貴重である。去来に〈尾頭のこころもとなき海鼠かな〉があるが、はらわたも抜かれたらもう踏んだり蹴ったりである。そんな海鼠の哀れさが「芯無き」に捉えられている。同時出句の〈日向ぼこ相槌の間の長きかな〉〈はちみつの結晶厚き冬の朝〉もいい感覚である。 |
クッキーの缶の針箱日脚伸ぶ 尼崎 沙羅
| 信州にいた子供の頃、東京の洋菓子店のゴーフルやチョコレート、クッキーなどの空き缶は貴重品であった。この句のように針箱や小物入れなどに転用したのである。それを今も使い続けているのであろうか。「日脚伸ぶ」に縁側のある家なども想像され、ほのぼのとした気分になる。 |
まづ医者に厚着をわびて聴診器 中込 精二
| 実感のある句だ。私は月に一度血圧の薬を貰いに医者に行くが、先生を待たせるのが嫌なので、外套の下は薄いシャツにしてすぐ血圧を計れるようにしている。だが聴診器となると少し厄介そうである。「厚着をわびる」の措辞に作者の人柄が偲ばれるようである。同時出句の〈おほかたは好日とあり古日記〉も平穏に過ぎた一年の安堵感である。
|
嫌な事柚子湯の湯気となりしかな 北原美枝子
| 柚子湯は冬至の日に柚子の薬効で無病息災を祈るもの。この句ではそれだけではなく、心の憂さまでもその薬効で身体から離れていくようだという。湯気になって消えていくという発想に独自性のある句だ。 |
うたた寝の肘のかくんと神の留守 小森みゆき
| 頬杖をついてうとうととしたのであろう。肘が外れて我に帰る。日本人は八百万神がいて様々な神が自分を監視し、或いは見守っていると思っている。神が出払っている神無月はついつい気が抜けてしまったということであろうか。現代でもその感覚が根強く残っているのが面白い。 |
大根焚にはか信徒の大食らひ 髙城 愉楽
| 大根焚きは十二月九・十日京都鳴滝の了徳寺で親鸞上人の徳を偲んで行われる。この作者は物珍しさに見物に押し掛けたのである。にはか信徒にして大食らい、というのだから困ったものである。だが親鸞上人のことであるからあたたかく許してくれることであろう。 |
塵取りをはみ出してゐる朴落葉 橋本 泰
| いい構図である。塵取りもそれなりに大きさがあるのだが、朴の葉はもっと大きい。朴の葉という「物」に焦点を当てて、平明で具体的である。俳句はこういう単純さが大事である。 |
冬木立見るも身軽な一遍像 北爪 鳥閑
| 私の一番好きな一遍像は松山宝厳寺のものであったが、三十年ほど前に燃えた。だが京都の東山山麓の長楽寺の一遍像があることを有難く思っている。あの強靱な脛、削ぎ切った背筋を冬木立と喩えたところが手柄である。 |
短日や朝刊追つて夕刊来 河畑 達雄
| 誠に短絡的な句なのである。ここまでの省略が、と驚くのだが、これが俳句の妙ということなのであろう。朝刊が来て、あれ、もう夕刊が来た!まさに短日である。俳句という世界最短の詩型の極限を追った佳句である。 |
日に一つ良き事入れむ新日記 桜井美津江
| 人生の残り時間を意識する年代の私には、しみじみと心に沁みる句だ。私は「今日は残りの人生の最初の日」という言葉を毎朝噛みしめて心を奮い立たせている。このあとは一日に一つは楽しい事を見付けて生きる、この句のように生きていきたいものだ、と思う。 |
その他印象深かった句を次に
会津紙の活字纏ひし餅届く 園部あづき
水軍の磯に隠れし海鼠獲る 日山 典子
思ひでの数多みつかる煤払 桂 説子
海底の難破船とも海鼠かな 西田有希子
雲一つ見る想ひにも十二月 唐沢 冬朱
寒の雨石庭の石孤高なり 吉田 正克
鍋焼の蓋取り蓋を持て余す 野口 光枝
冬晴や味醂の町の一茶庵 深澤 淡悠





伊那男俳句 自句自解(86)
母の日をこのごろ妻の日とも思ふ
結婚して三十年。五十五歳になったばかりで妻は死んだ。この時代の男はたいがいそうであったと思うが、私も企業戦士の一人であった。中途採用のハンディを跳ね返すように実によく働き、成績も上げた。同期生でトップで課長に昇格し、ヘッドハンティングに乗って金融会社を設立し役員に就任していた。当然子育てについても家事についても全て妻に丸投げであった。そういうことは妻の仕事なのだと思い込んでいたのである。その挙句の果て、バブル崩壊により失業者になったのであるから結局は妻に心労を掛けてしまったのである。もちろん高い給料を取り、贅沢な旅行などもしていたけれど、その期間は短く、普通のサラリーマンであった方が、妻は幸せだったのかもしれない、と思う。その浮沈のある生活の中でも妻はいつも励ましてくれたし、泣き言を言うこともなかった。妻というものはいつでも頼れる母のような存在であった。母の日にそんなことを思った。
露の世に生きて三ノ輪の浄閑寺
浄閑寺は東京都荒川区南千住にある浄土宗の寺。安政の大地震で遭難した吉原の遊女が投げ込まれるように葬られたことから「投込寺」と呼ばれるようになったという。新吉原総霊塔があり、花又花酔の川柳〈うまれては苦界、死しては浄閑寺〉が刻まれている。鈴ヶ森と並ぶ処刑場小塚原も近い。人の世には常に光と影があり、表と裏がある。それは古から現代に至るまで変わらない。我々の世代は戦争を体験していないし、恐らく日本史の中でも最も経済的に恵まれた時代を生きてきた。人類史の中でも稀な好運の中にいたことを先祖と八百万の神に感謝しなければならない。それでもなお苦界に生きる人々がいることも知っておかなくてはならない。「露」は気象現象としての「露」と、そこから転じて、「露の命」「露の世」などと、命の行方の頼りなさの譬えとして用いられる。つまり二つの意味を持つ特殊な季語である。 |





更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。



リンクします。
aishi etc



挿絵が絵葉書になりました。
Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組
8枚一組 1,000円
ごあいさつにご利用下さい。








|
![]()
![]() 3月号 2023年
3月号 2023年 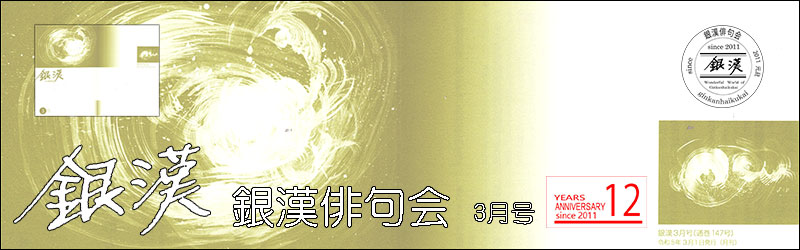





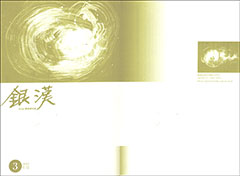









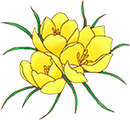































 26
26







