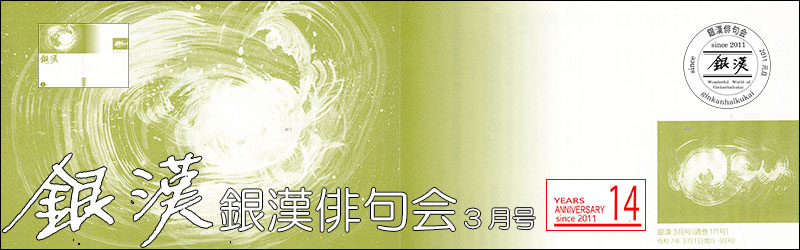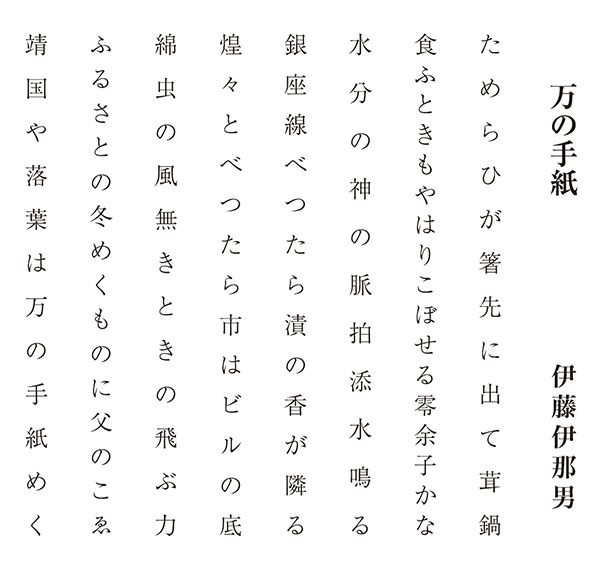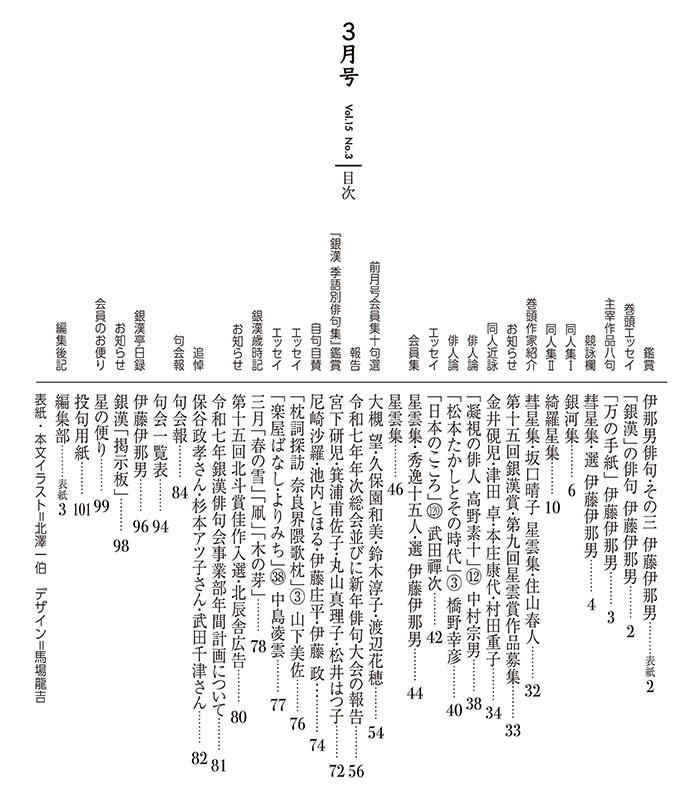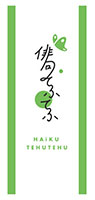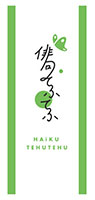伊藤伊那男
伊藤伊那男・選
来世より帰りしごとく日向ぼこ 大沼まり子
伊藤伊那男・選 巻きもどす寺の縁起絵大根焚 東京 飯田眞理子
伊藤伊那男・選
てつちりや浪花ことばが酔ふほどに 東京 飛鳥 蘭雑司ヶ谷
伊藤伊那男・選
伊藤伊那男・選 秀逸
浮き気味の尻は残して鴨潜る 東京 橋本 泰
星雲集作品抄
伊藤伊那男・選
片時雨眉山ぼかす薬指 東京 尼崎 沙羅
伊藤伊那男
伊那男俳句 その3 草石蚕の紅一点として残る
更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。
aishi etc 挿絵が絵葉書になりました。
![]()
![]() 3月号 2025年
3月号 2025年